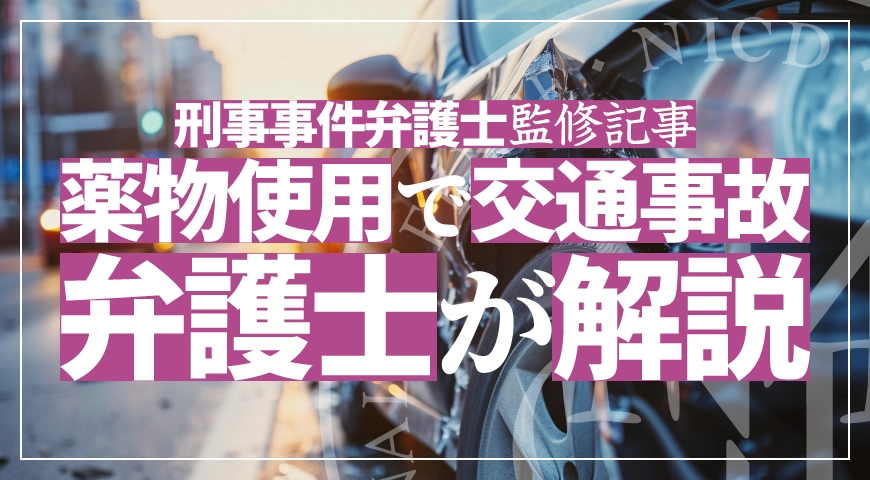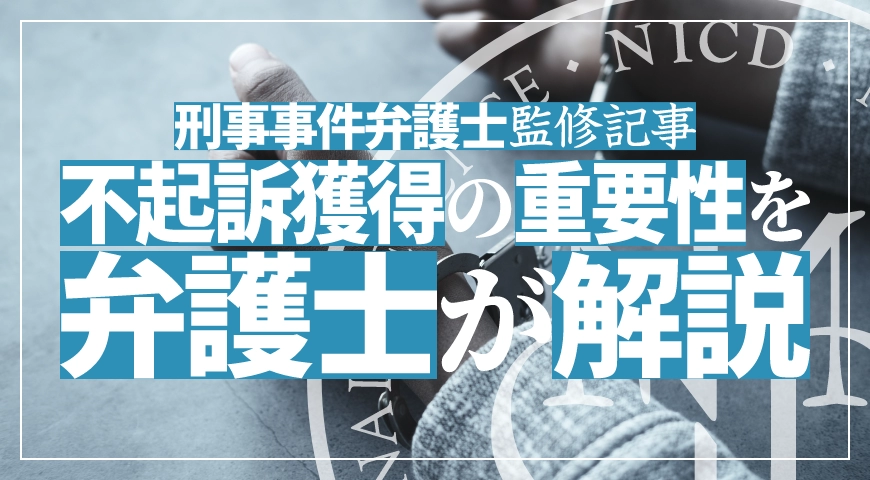道路交通法とは、道路上の危険を防止し、交通が安全かつ円滑に行われるように、また道路交通に起因する障害の防止を目的として定められた法律です。
では、どのような行為が道路交通法違反となるのでしょうか。また、違反した場合にはどのような罰則が付くのか、逮捕されることはあるのかを弁護士・坂本一誠が解説します。
道路交通法違反に該当する行為
道路交通法は、以下のように第2章から第6章に交通ルールを設けています。
これらの規定に違反すると、道路交通法違反となります。特に件数が多いのは、一時停止違反(令和5年は1,267,094件)、最高速度違反(888,500件)、通行禁止違反(616,174件)などです。
第2章 歩行者等の通行方法
第3章 車両及び路面電車の交通方法
第4章 車両等の運転者及び使用者の義務
第5章 道路の使用等
第6章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
◇一時停止違反
3灯式信号機が設置されておらず、警察官が交差点で手信号を行っていない交差点において、道路標識などに従って停止線の直前または交差点の直前で一時停止しなかった場合には、道路交通法43条違反となります。
◇最高速度違反(スピード違反)
道路標識や表示で指定された最高速度がある場所では、その最高速度を超える速度で走った場合、道路交通法22条1項違反となります。
◇通行禁止違反
道路標識や道路標示によって通行が禁止されている場所を通行した場合は、道路交通法8条1項違反となります。たとえば、車両通行止めや一方通行道路の標識を無視した場合が該当します。
また、道路交通法は社会問題に対応して都度改正がなされています。車の運転中にスマートフォンやカーナビを操作する「ながら運転」による事故は2013年から2019年には2000件を超える高い水準にあり、2019年の道路交通法違反改正により、罰則が強化されました。2024年からは、自転車運転中のながらスマホについても罰則が強化されています。また、2020年の道路交通法改正では、あおり運転は「妨害運転」として取締りの対象となり、罰則が創設されました。
◇飲酒運転・無免許運転
その他にも、悪質性・危険性の高い違反として、以下のようなケースが該当します。
飲酒をして体内にアルコールが残っている状態で運転をした場合には、「酒気帯び運転」「酒酔い運転」に該当し、道路交通法違反となります。
他にも、運転免許を持たない人が運転をした場合は、無免許運転として道路交通法違反に該当します。運転免許の停止や失効を受けた人が車両を運転して発覚するケースが多いです。なお、運転免許を取得したことが一度もない場合だけでなく、免許停止期間中や免許の有効期限が切れているにも関わらず運転を行った場合も、無免許運転となります。
◇ひき逃げ・当て逃げ
交通事故を起こしてしまった場合、運転者や同乗者は、運転を停止して負傷者を救護するなどの措置を行い、警察に報告しなければなりません。「ひき逃げ」とは、車両等の運行中に人身事故があった場合に、このような必要な措置を講ずることなく事故現場から逃走する行為のことをいいます。また、人身事故ではなく物損事故があった場合に逃走する行為は「当て逃げ」に該当します。
交通違反に関する法律は、道路交通法だけではありません。
アルコールや薬物により正常な判断ができない状態での運転や、制御できないほど高速度での運転、あおり運転などは、「危険運転」に該当します。このような行為により人を死傷させてしまった場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称「自動車運転死傷行為処罰法」)に定められている危険運転致死傷罪が適用されて逮捕・起訴される可能性があります。
道路交通法違反の罰則
道路交通法に反すると、刑事処分として懲役や罰金、行政処分として反則金、違反点数に基づく免許停止や免許取り消しといったペナルティを受ける可能性があります。以下で詳しく解説します。
刑事処分
刑事処分は、道路交通法違反が犯罪として扱われる場合に、刑事手続を経て科される刑罰です。違反行為に対する制裁が目的とされています。道路交通法の第8章(第115条~第124条)には、各種違反に対して懲役・罰金などの罰則が定められています。
刑事処分の対象となるのは、比較的重大な違反行為です。たとえば、以下のようなケースが該当します。
- 酒気帯び運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第117条の2第1号)
- 無免許運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条の2の2第1項第1号)
- ひき逃げ(救護義務違反):10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第117条第1項)
これらは、運転者本人だけでなく、他人の生命・身体を脅かす行為であるため、社会的な非難も大きく、重く処罰することが求められています。また、信号無視や速度超過によって、重大な人身事故や物損事故を起こす可能性も高く、このような場合にも刑事処分が科されます。死亡事故につながった場合には、過失運転致死傷罪が適用され、7年以下の懲役又は禁錮、もしくは100万円以下の罰金が科されます。
刑事処分は、まず警察の捜査を経て、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴された場合は、刑事裁判を経て判決が言い渡されます。ただし、全ての案件が法廷に持ち込まれるわけではなく、略式手続によって罰金刑のみが科されるケースもあります。これは通常、刑罰が比較的軽く、違反者が行為を認めている場合に利用されます。
刑事処分が科されると、たとえ罰金のみであっても前科が付き、将来的に不利益を被る可能性があるので注意が必要です。また、刑事処分は行政処分と並行して科されます。刑事罰を受けた場合も違反点数(以下で解説)が付され、免許停止や免許取消などの処分を同時に受けます。
行政処分
行政処分は、刑罰とは異なり、道路交通上の危険の防止を目的として、公安委員会が運転免許の停止や取り消しといった「運転資格」に対する制限を科すものです。行政処分は点数制度の上に成り立っており、一定期間の累積点数と処分回数をもとに処分内容を決定します。以下、点数制度と反則金について解説します。
点数制度
全ての交通違反には違反点数が設定されており、過去3年間の累積点数と行政処分回数(前歴)をもとに、処分内容が決定します。点数には、基礎点数と付加点数の2種類があります。
基礎点数とは、個別の違反行為に対して、あらかじめ定められた標準的な点数です。たとえば、一時不停止は2点、速度超過(20㎞/h未満)は1点、速度超過(25㎞/h以上30㎞/h未満)は3点など、違反の内容や程度に応じて点数が異なります。一時不停止や速度超過、信号無視などは一般違反行為として、1~25点、より悪質・危険な違反行為である酒酔い運転や運転障害などは特定違反行為として35~62点が割り当てられます。
付加点数は、交通違反の結果として事故を発生させた場合に加算される点数です。たとえば、速度超過のみでは基礎点数の加算にとどまりますが、その違反行為が原因で人身事故を起こした場合は、事故の重さ(被害の程度)と違反者の不注意の程度に応じて、さらに10点、20点といった高い点数が加算されます。
点数制度においては、以下のような累積点数によって行政処分が行われます。
前歴が多くなるにつれて、処分内容も厳しくなります。以下、前歴がない場合と、1回ある場合の処分内容です。
前歴がない場合
・6~8点…30日間の免許停止
・9~11点…60日間の免許停止
・12~14点…90日間の免許停止
・15点以上…免許取消し前歴1回の場合
・4~5点…60日間の免許停止
・6~7点…90日間の免許停止
・8~9点…120日間の免許停止
・10点以上…免許取り消し
反則金
刑事処分としての罰金の他に、行政処分として反則金を求めることもあります。両者の違いは、対象となる違反行為の重大性にあります。罰金は刑事罰なので、裁判所での手続きが必要です。しかし、道路交通法違反の取締りは年間448万4,894件も起こっていますので(令和5年)、これら全てについて裁判所が審判によって刑事罰を科すことは不可能です。
そこで、行政制度として、交通反則通告制度が設けられています。交通反則通告制度とは、比較的軽微な道路交通法違反行為を反則行為とし、一定期間内に反則金を納めることで裁判所の審判を受けずに事件が処理されるという制度です。
「比較的軽微な道路交通法違反」とは、たとえば、信号無視、速度違反、一時不停止などを言います。ただし、このような違反行為であっても無免許運転、酒酔い運転、違反行為により交通事故を起こした場合などは、悪質な行為として通常の刑事手続きをすることになります。
反則行為をした場合、警察官から交通反則告知書(いわゆる「青キップ」)と反則金の納付書を渡されます。渡された日を含めて8日以内に反則金を銀行または郵便局に納付すると、手続きが完了します。反則金の納付は強制ではありません。反則者は交通反則通告制度の適用を拒否し、刑事手続を選択することもできます。
反則金の金額は、違反行為の種類や車両の種類によって異なります。最も安い反則金は3,000円、最も高い反則金は40,000円です。
たとえば普通車の場合、赤色信号の無視は9,000円、25㎞/h以上30㎞/h未満の速度超過は18,000円、一時不停止は7,000円の反則金が科されます。
道路交通法違反で逮捕されるか
道路交通法違反行為を行った場合、全ての行為が直ちに逮捕につながるわけではありません。一般的に、一時停止違反や速度超過といった軽微な交通違反については、交通反則通告制度で手続きが完結することが多いです。しかし、悪質・重大な違反行為に該当する場合には、現行犯逮捕や通常逮捕が行われることがあります。
たとえば、飲酒運転、無免許運転、危険運転致死傷、ひき逃げといったケースでは、人身事故や重大な被害につながる危険性が大きいため、捜査機関による身柄拘束の対象となります。
現行犯逮捕は、違反が発生した直後に警察官などが違反者を発見した場合に認められる逮捕形態です。職務質問や自動車検問により、酒気帯び運転・酒酔い運転が発覚した場合や、無免許運転は現行犯逮捕されるケースに該当します。
一方、現場では逮捕されなかったとしても、後日、通常逮捕が行われることがあります。これは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に、裁判所の逮捕状を取得して行われるものです。
また、青切符を交付されても反則金を納めなかった場合には、交通反則通告制度ではなく通常の刑事手続によって処分されることになり、逮捕される可能性もあります。2024年には警視庁は、長期未納者で住所が把握でき、5回以上はがきでの呼び出しに応じない違反者292人を道路交通法違反の疑いで逮捕し、簡裁で罰金刑を科しました。
道路交通法違反での刑事弁護士の役割
道路交通法違反が刑事事件に発展した場合、刑事弁護士によるサポートは極めて重要です。
身柄解放
逮捕された場合は、通常、48時間以内に検察庁に送致され、検察官は送致から24時間以内に勾留請求の判断をします。勾留が認められれば最大で20日間、身体拘束が続く可能性があります。勾留されてしまうと、社会的信用を大きく損なうおそれがあり、職場を解雇されたり、家族関係に悪影響が及んだり、重大な法的リスクを伴うといえます。
勾留されずに在宅で手続きを進めることができれば、このようなリスクが軽減され、処分も軽くなる傾向にあります。逮捕後72時間以内に勾留が決定されるため、迅速な対応が必要です。弁護士は接見を行い、勾留阻止や早期釈放に向けた活動を行います。
勾留請求前の段階では、検察官と直接面談する、勾留の必要性がないことを主張し、意見書を提出するなどの手段を講じて、検察官に対し、勾留請求をしないように働きかけを行うことができます。勾留請求後であっても、裁判官が勾留決定をするまでに、勾留請求却下を求め、裁判官との面談や意見書の提出をすることができます。勾留が決定された場合でも、裁判所に対し準抗告を行い、起訴後の段階では保釈請求をするなど、身柄解放の可能性を最大限に追求します。
交通事件は、自動車の損傷状況や事故現場の防犯カメラ映像など、客観的な証拠が捜査機関に早期に収集されることが多いです。そのため、被疑者本人による罪証隠滅の余地が乏しいことが多く、他の事件と比べると、仮に逮捕されたとしても、弁護人が身柄解放の活動を迅速に行うことで勾留を回避できる場合が少なくありません。こうした弁護士の活動によって早期の身柄解放が実現すれば、仕事や学業への影響、社会的信用の失墜を最小限に抑えることができます。そのため、ご家族などが交通事件で逮捕された場合には、速やかに弁護士に相談することが必要です。
示談交渉
道路交通法違反により事故を起こして被害者がいる場合には、被害者との示談交渉を行っていくことになります。示談が成立すれば、不起訴または略式命令となる可能性が高まります。起訴された場合でも、示談が成立していることは量刑判断に大きく影響し、罰金刑や執行猶予付き判決となるなど、処分の軽減に寄与します。
道交法違反の事案では、被疑者・被告人側が任意保険に加入していることも多いです。この場合、保険会社の担当者が被害者と賠償について交渉してくれることが殆どです。しかしながら、保険会社は社内基準に則って賠償を提示するだけであり、処罰感情を緩和することを明示した内容の示談を取り付けてくれるわけではありません。
不起訴処分や刑の減軽を目指すためには、示談交渉によって処罰感情の緩和を明示した示談書を作成する必要性が高いです。
そのため、保険会社が示談交渉を行ってくれるとしても、刑事手続の事を考えると刑事事件に精通した弁護士に別途示談交渉を依頼するメリットがあります。加害者本人に対して、被害者が示談を拒否するケースも多く見られます。弁護士が間に入ることで、感情を整理した冷静なやり取りが可能になり、示談の成立が期待できます。また、弁護士は示談金額の相場、支払い能力と誠意の伝え方、謝罪文の添え方などの知識や経験を活かした示談交渉を行うことができます。
道路交通法違反の解決実績・感謝の声
当事務所で道路交通法違反が解決された実績をご紹介いたします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。道路交通法は、誰もが違反行為を行ってしまう可能性のある法律です。刑事事件に発展すれば、人生に大きな影響を与えかねません。
違反行為を行ってしまった場合は、まずは警察の出頭要請や反則金の納付に素直に応じることが重要ですが、もしも刑事処分が科される場合は、早期に弁護士へ相談してください。