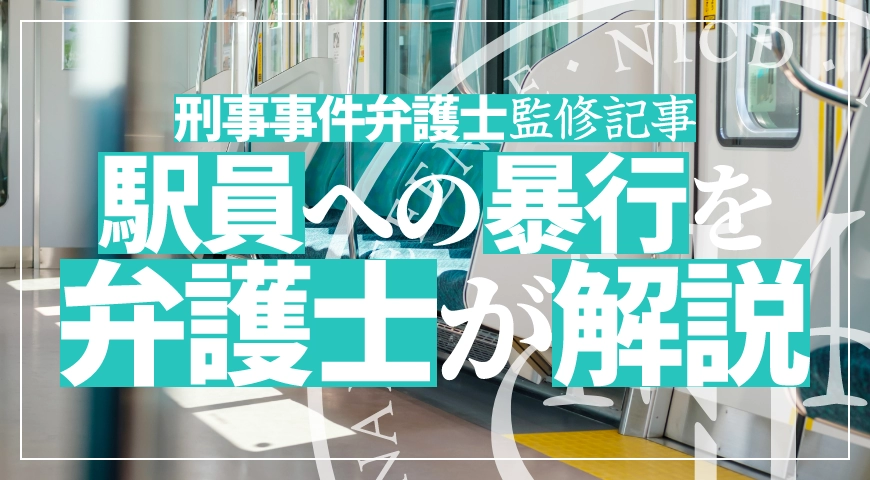事件を起こしてしまったとき、最大の関心事は逮捕されるかどうかです。諸外国と比べても我が国では「逮捕」という響きは絶望的なほど大きく、しかも逮捕は報道を伴うことが多いため、逮捕される人やその周囲の人々に与える影響は大きいです。
しかし、法律上は任意捜査が原則であり(刑事訴訟法197条1項ただし書き)、捜索・差押えや逮捕・勾留などの強制捜査は全くなされず最後まで終わるケースも多々あります。とはいえ、「強制捜査」と言われれば先ほど挙げたような捜索・差押え、逮捕・勾留などがイメージできても、「任意捜査」と言われてもその具体的な内容はあまりイメージできないという人も多いと思います。
そこで、今回は、任意捜査をテーマに代表弁護士・中村勉が解説いたします。
任意捜査とは
任意捜査とは、強制捜査以外の捜査をいいます。強制捜査とは、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産などに制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為(強制処分)による捜査のことをいい(最判昭和51年3月16日刑集30-2-187)、先ほど挙げた捜索・差押えや逮捕・勾留が代表的ですが、他にも検証などがあります。
一方、任意捜査は、例えば、被疑者や参考人の取り調べ、任意出頭、任意同行、張り込み、聞き込み、実況見分などがあります。ただし、被疑者取調べについては、逮捕・勾留されている場合については、実務上取調べ受忍義務があるとされていることに注意が必要です(刑事訴訟法198条1項但し書反対解釈)。
任意捜査になじむ事案
任意捜査になじむ事案としては、痴漢・盗撮といった条例違反の事件、刑法犯でも暴行、器物損壊、侮辱のように法定刑の比較的軽い事件、法定刑は軽くなくても万引きのように事案が軽微な事件などがあります。また、交通事故についても在宅捜査となることが多く、死亡事故であっても逮捕はされたが勾留はされなかったというケースは多いです。
もっとも、一般的には任意捜査が多い事件だとしても、証拠隠滅行為をしたり、現場から逃走したりした場合や、事件の内容によっては、逮捕・勾留される可能性が十分あります。勾留の理由のほとんどは、罪証隠滅のおそれ(刑事訴訟法60条1項2号)か逃亡のおそれ(同項3号)だからです。
任意捜査と強制捜査の違い
強制捜査は、先ほど挙げたように、身体、住居、財産など重要な権利を制約する処分であり、一部の例外(逮捕に伴う捜索・差押えなど)を除き、令状主義(憲法35条)が妥当します。したがって、捜査機関の独断で実行することができず、原則として裁判官の発付する令状が必要とされています。
一方、任意捜査は令状主義が働きませんが、任意捜査に該当する処分であれば何をやっても適法というわけではありません。具体的には、必要性・緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるとされています(最判昭和51年3月16日刑集30-2-187)。
任意捜査を拒否する注意点
任意捜査はあくまで「任意」ですから協力する義務はありません。しかし、任意捜査を拒否する場合は、先ほど挙げた罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれが疑われないかという点について十分注意する必要があります。任意捜査に協力しないと、捜査機関からは、「何かやましいことがあるから応じられないのではないか」と思われてしまい、任意捜査で進める予定が強制捜査に切り替わるという可能性も考えられます。
特に、任意捜査から強制捜査に移行するということは、すなわち逮捕・勾留されることを意味しますので、任意の取調べを拒否する場合、ただ面倒だから、自分は関係ないからなどといった理由で応じないのは非常に危険です。当事務所にご依頼いただいた事案の中でも、当初捜査機関は任意捜査で進めるつもりで対象者の呼出しをしていたものの、対象者が呼出しを何度も拒否してしまったために逮捕されてしまったのだろう、という事案もあります。
無実であると主張するならば、積極的に捜査に応じるほうが、結果的には早く捜査から解放されることにもつながります。ただし、供述した内容は供述調書として証拠となり、裁判の資料にもなります。否認する場合は、事前に弁護士のアドバイスを受けておくことが大切です。また、弁護士に相談しアドバイスを受け、積極的に捜査に協力したために、本来予定されていた家宅捜索を回避できた例もあります。
任意捜査はいつまで続くか
強制捜査の場合、逮捕は72時間、勾留は20日間と拘束できる時間が法律上限られているため、いつ終わるのか見通しがつきやすいです。ところが、任意捜査の場合、時間制限がありません。そのため、実情としては時間制限のある強制捜査を優先し、任意捜査は後回しになりがちで、集中的に捜査すれば何週間もかからないような捜査が何か月もかかることがよくあります。その時の警察署や担当検察官の立て込み具合にも左右されます。
ただ、やはり事件が単純であるほど、早く終わる傾向にあり、また、認め事件(自白事件)は否認事件より早く終わる傾向にあります。痴漢・盗撮や万引きなどのさほど複雑ではない事件であれば、短い場合1か月~3か月程度で終わることもあります。責任能力や過失の有無に問題がある事案など、高度な法律的判断が必要な事案では1年以上かかることもあります。
任意捜査で時間がかかっている場合、不安に思われるのも仕方ありません。しかし、必ずしも、「時間がかかっている=起訴するための証拠を一生懸命に集めている」というわけではありません。むしろ、その逆で、不起訴の決裁を通すための証拠集めに時間がかかっているというケースもよくあります。自分で警察官や検察官に捜査状況を確認するのは難しくとも、弁護士であれば本人ではまず教えてもらえないような捜査状況を率直に教えてくれることもよくあります。在宅捜査の終わりが見えず、不安という方は、積極的に弁護士を活用しましょう。
任意捜査の弁護活動
一口に任意捜査といっても次に挙げる3つのパターンがあります。
1つ目として、当初から最後まで任意捜査をすることが想定されている場合です。先述したような元々任意捜査になじむ事案については、途中で罪証隠滅や逃亡を疑われる行為をするなどのことがない限り、途中で逮捕されることはあまり想定されません。
2つ目として、当初は強制捜査であったが、勾留請求却下などの事情で釈放され、在宅捜査に切り替えられるような場合があります。このような最初に逮捕されるような事案では、途中から在宅になっても、検察は捜査処理を急ぐと思われるので、示談などの弁護活動は速やかにする必要があります。
3つ目として、当初は任意捜査で、後に強制捜査に切り替えることが予定されている場合があります。事件が複雑なために、身柄拘束期間の間に事件を終了できないような場合に、任意捜査を先行して行うことがあり、例えば贈収賄のような組織犯罪に多くみられます。この場合で、特に証拠が少なくて逮捕状がとれないような場合には、任意といっても、実質強制のような取調べがなされるおそれがあるので、注意する必要があります。
弁護士としては、この3つのどの場合にあたるのかを分析したうえで、事案にあった的確なアドバイスをすることが重要です。特に3つ目のケースでは、途中で逮捕されることも想定して、それまでにできるだけ示談等の弁護活動を進め、逮捕の理由を少しでも減らすことが重要です。事案を分析しつつ行う必要があります。
まとめ
今回は、任意捜査と強制捜査の違い、任意捜査に協力しなかった場合などについて解説しました。任意捜査の場合、最後まで弁護士を付けないという方も多いですが、刑事手続がよくわからず、何もしなかった結果、起訴されてしまったという方も見かけます。
任意捜査で、在宅事件として捜査が進んでいる場合、自分から弁護士に連絡しないと、弁護士のアドバイスを受けることはできません。弁護士に相談し、示談を試みたり、取調べに対する適切なアドバイスを受け、起訴前にきちんと弁護活動をしていれば不起訴にできた可能性が高い事件もあります。
しかし、一度起訴されてしまえば、そこから弁護活動をしても起訴される前には戻れません。自分の置かれている状況がよくわからない、先行きが不安だという方は、刑事事件に詳しい弁護士に早めに相談した方がよいでしょう。