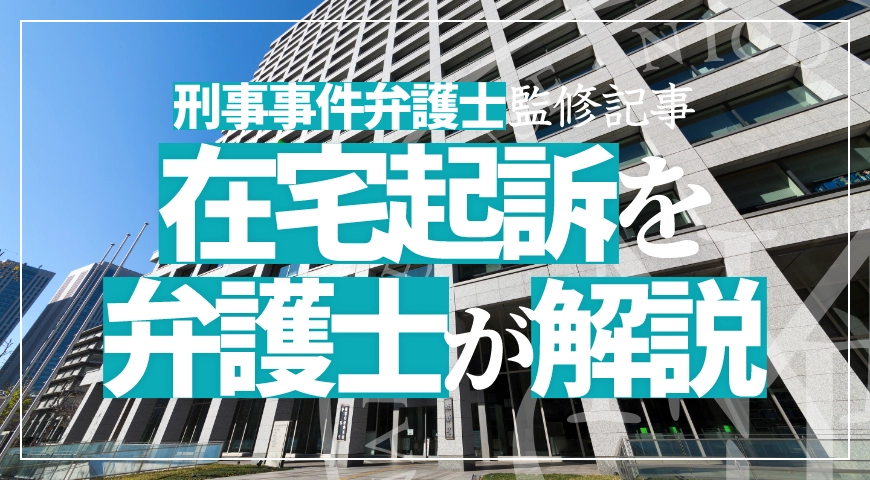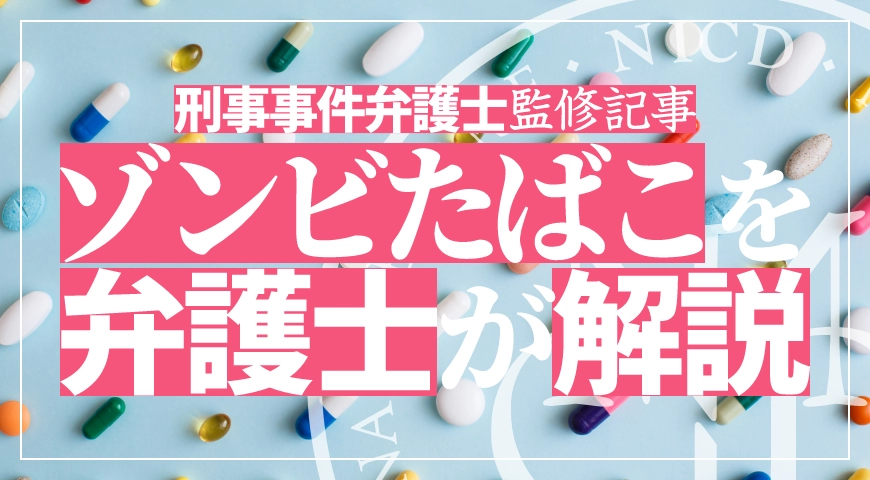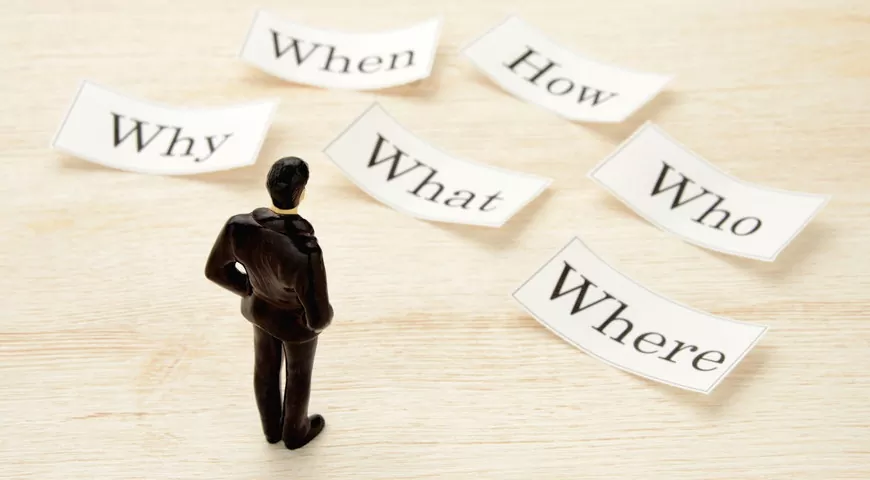裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件について、身柄拘束されている被疑者の取調べの全過程の録画を義務付ける改正刑事訴訟法301条の2が令和元年6月1日から施行されました。
このような取調べの録音・録画制度は「取調べの可視化」とも言われています。
本コラムは弁護士・中村勉が執筆いたしました。
取調べの録音・録画制度導入の経緯
日本では、取調べに弁護士の立会いが認められていません。
取調べ室でどのようなやり取りがされたかは、その場にいた警察官や検察官、及び被疑者等にしか分かりません。取調官である警察官や検察官による威圧的、あるいはミスリーディングな働きかけにより、もともと否認していた被疑者が犯罪事実を認めたという経緯があったとしても、供述調書にそのような事実は当然記載されませんし、刑事裁判でそのような働きかけがあったものと被疑者が主張したとしても、取調官がそれを否定する限り、被疑者はほとんどの場合で信用してもらえないでしょう。
そして、日本の刑事裁判では、そのような状況のもとで作成された供述調書の内容に過度に依存した事実認定が長らく行われ、数々のえん罪が生み出されてきました。
日弁連においては、このような刑事司法の実態を抜本的に改革するために、「取調べの可視化」(取調べの全過程の録画)を長年にわたって強く求めてきており、その結果、平成28年の通常国会で一部の事件につき取調べを可視化する法律がようやく成立し、令和元年6月1日に施行されるに至りました。
原則として取調べの録音・録画を実施する事件
冒頭にも述べましたが、法律上、原則として録音・録画を実施しなければならない事件は以下の通りとなっています。
- 裁判員裁判対象事件(刑事訴訟法第301条の2第1号、第2号 ※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項1号、2号参照)
- 検察官独自捜査事件(刑事訴訟法第301条の2第3号)
また、録音・録画が義務付けられるのは、これらの事件の捜査のために行われる取調べのうち、身柄拘束されている被疑者の取調べに限られます(刑事訴訟法第301条の2第1項柱書本文括弧書き)。身柄拘束されていない、いわゆる在宅扱いの事件のうちは、録音・録画は義務付けられていません。
このほかにも、犯罪捜査規範第182条の3第2項によって「逮捕または勾留されている被疑者が精神に障害を有する場合」には、必要に応じて、取調べの録音・録画をするように努めなければならないとされています。
なお、録音・録画が義務付けられていない一般事件であっても、最近では、身柄拘束中の被疑者の検察官による取調べは録音・録画される傾向にあります。特に、通訳人を介して行う外国人被疑者の事件の取調べや否認事件の取調べなどは、基本的に録音・録画が行われています。
取調べの録音・録画制度の例外
以下にあたる場合には、例外的に取調べの録音・録画義務が免除されます(刑事訴訟法第301条の2第4項)。
- 記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により、記録をすることができないとき
- 被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき
- 当該事件が都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員による犯罪に係るものであると認めるとき
- 犯罪の性質、関係者の言動、被疑者がその構成員である団体の性格その他の事情に照らし、被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき
取調べの可視化(録音・録画)のメリット・デメリット
弁護人の立会いが許されていない現制度のもと、取調べの録音録画は、適正な取調べを確保するために必要不可欠なものといえます。録音・録画がされることにより、取調官においては自白を強要する取調べはできず、また、捜査機関側に都合のよいストーリーを作文する「作文調書」も作成しづらくなります。
他方で、録音・録画がされると、一度供述すれば、その供述内容及び供述態度がありのままに記録されますので、場合によっては、被疑者側に不利益に使用されることもあり得ます。
すなわち、録音・録画制度があるからこそ、取調べでの対応は非常に重要となってくるのです。ですので、取調べの録音・録画が実施される事件においては、なおさら刑事事件の経験が豊富な弁護士の取調べアドバイスが必須といえるでしょう。
取調べを自分の携帯で録音・録画してもいいか
身柄が拘束されていない、いわゆる在宅事件の被疑者となっている方からこのような質問がされることがあります。
録音・録画をしてはいけないという法律は特にありませんが、捜査機関側は通常これを拒否します。特に、警察での取調べにあたっては、取調べ開始前に所持品をチェックしたり、携帯を出させたりして、録音等がされないように予防線を張っている例もしばしば見られます。
ですので、基本的には自分の携帯で録音・録画はできないと考えた方がよいでしょう。
この場合の取調べは任意ですので、必要に応じて取調べを中断してもらい、取調べ室を一旦出てから弁護士に電話して相談すること等はできます。ですので、取調べの態様や内容に不安を感じた場合には、そのようにして対処するのがよいでしょう。
弁護士に依頼して録音・録画の申入れをしてもらうことはできるか
申入れ自体は可能です。特に身柄拘束されている事件ですと、弁護士による申入れに応じ、検察官による取調べにおいて録音・録画が履践されたケースもしばしばあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。取調べの録音・録画の意義をお分かりいただけたかと思います。録音・録画は適正な取調べの確保のために重要である一方で、被疑者側にとっても取調べにおける対応につき細心の注意を払わなければならないことにもなります。
逮捕・勾留されているご家族がいらっしゃる場合には、お早めに刑事事件の経験が豊富な弁護士にご相談・ご依頼ください。