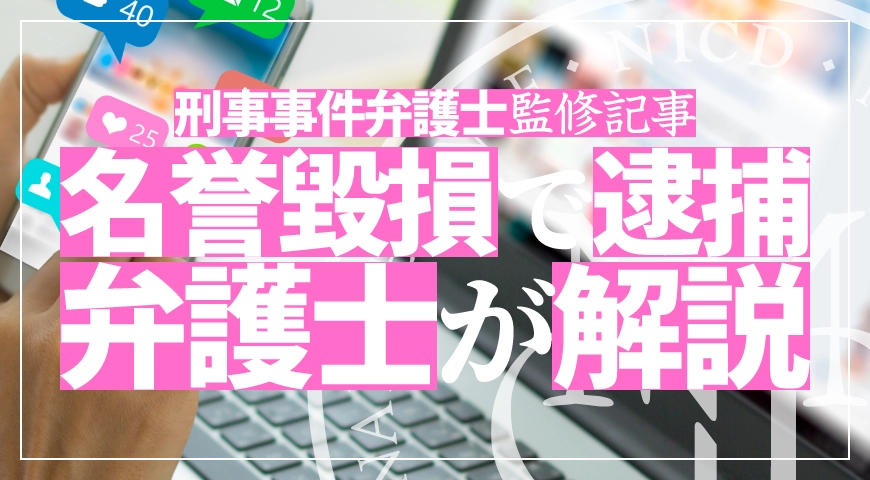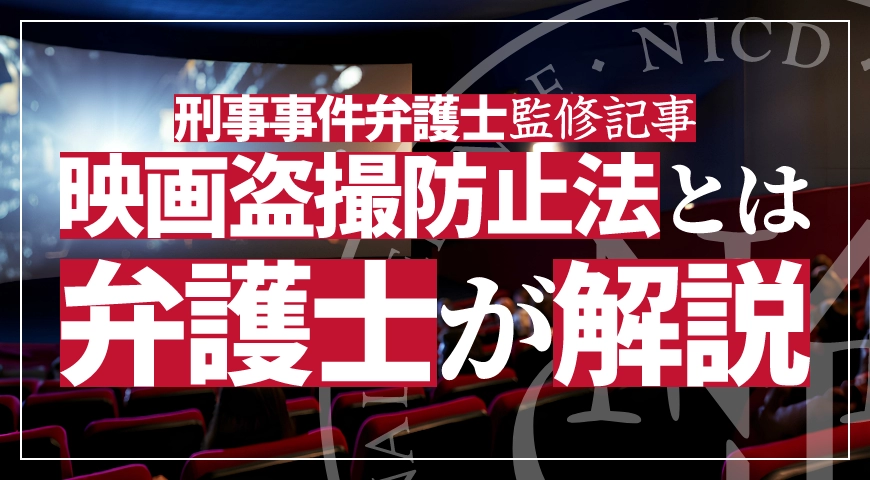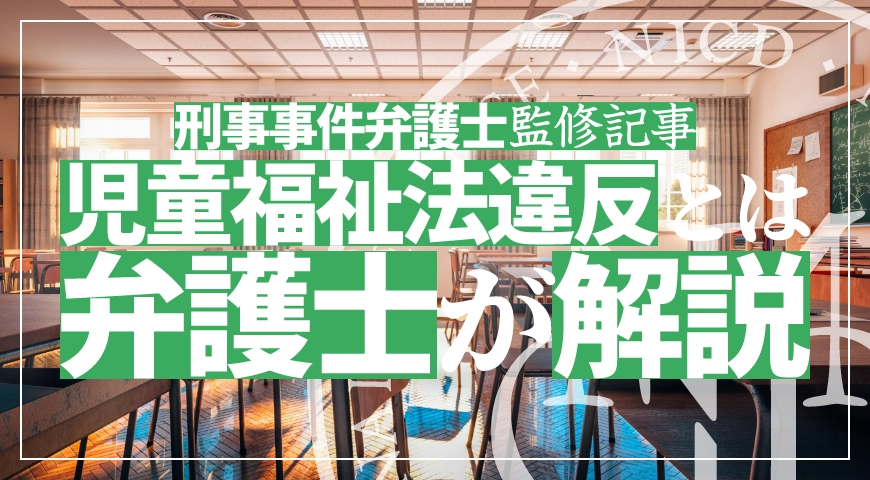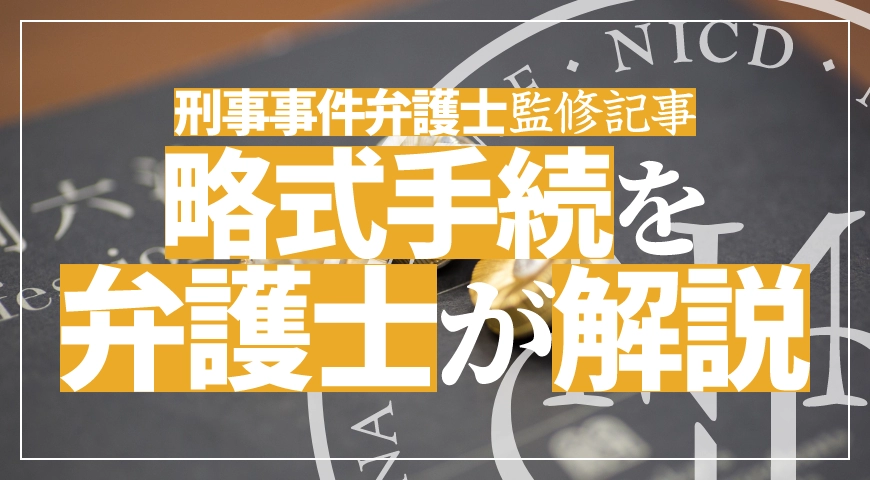「前科」とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。懲役刑や禁錮刑だけでなく、罰金刑や科料も前科に含まれます。また、執行猶予付きの判決も前科に含まれます。法令の定めによるものではありませんが、市町村役場で運用されている犯罪人名簿に登録されます。
前科があると、各種の法律によって資格制限の事由になります。どのような資格制限があるかついては、後ほど詳しく解説します。また前科がある状態で再犯に至ると、一定の場合は、執行猶予の欠格事由(刑法25条)、累犯加重の事由(刑法56条)となり、重い刑が科せられることになります。
「前科」、「前科者」という言葉は、社会生活を送っていく上で、マイナスの響きをもつ言葉の一つです。一度捕まると社会復帰はできず、家族や親戚に多大な迷惑が生じるという認識の方も多いでしょう。今回は、前科がついた場合の影響について代表弁護士・中村勉が解説いたします。
前科は消えないのか
上記のとおり、「前科」は各種の法律により、資格制限を受け、一定の職業に就けないなど、更生の障害となる場合があります。そこで、昭和22年の改正(法124)により刑の消滅の規定(刑法34条の2)が設けられ、執行終了又は免除後一定期間を罰金以上の刑に処せられることなく経過したとき、その抹消が認められ、刑が消滅するとされました。禁錮以上は10年、罰金以下は5年、刑の免除は2年です。
刑法第34条の2
1. 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2. 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
この期間を経過すると、犯罪人名簿からも抹消されて、警察も無犯罪証明書を出してくれるようになります。また、履歴書の賞罰記入欄に「なし」と書いてもよくなります。ただし、刑が消滅したとしても警察と検察庁に犯歴記録は残るため、新たに罪を犯した場合は当然刑事処分や判決を決める上で不利な事情になってしまいます。
執行猶予付き判決の場合は、取り消されることなくその猶予の期間を経過すれば、刑の言渡しは、効力を失い刑務所に行く必要はなくなりますが、この場合も警察や検察庁の記録には残り続けます。
刑法第27条
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
前科と前歴の違い
「前科」と「前歴」は混同されやすい言葉ですが、その意味は大きく異なります。「前科」とは確定判決で刑の言渡しを受けたことをいうのに対し、「前歴」とは捜査機関に捜査の対象とされた履歴のことをいいます。
前歴の代表例としては、逮捕歴が挙げられます。逮捕されたからといって、必ずしも起訴され、刑の言渡しを受けるとは限りません。そのため、逮捕されても、必ずしも前科が付くわけではありません。しかし、逮捕されれば、警察から被疑者として捜査の対象とされていることにはなりますので、前歴はその時点で付くことになります。
前歴は単なる捜査の対象とされた履歴に過ぎないので、就職や就業に与える影響はさほど大きくありませんが、前科が付いてしまうと就職ができなくなる職業があり、また、現にそのような職に就いている場合は今の職業を続けることができなくなる可能性があります。
前科が就職や就業に与える影響
企業に前科・前歴を知られることはあるのか
一般の企業では、本人からの申し出がなければ、その事件が実名報道されたような場合でない限り、前科・前歴の有無を確認する方法はありません。したがって何らかの事件の被疑者となってしまった場合には、弁護士に依頼し、その事件の報道を防ぐよう、逮捕を避けるなどの弁護活動を行ってもらうことが大切です。
一部の企業によっては、前科・前歴を本人に確認する場合があります。その際に、前科・前歴があるにもかかわらず「ない」と答えてしまうと、経歴詐称となり、懲戒や解雇の理由となりえます。ただし、経歴詐称だからといって、常に懲戒や解雇ができるわけではありません。懲戒も解雇も「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は権利の濫用として無効となるからです(労働契約法第15条、第16条)。
経歴詐称についての重要裁判例によれば「労働者の経歴詐称が、もし使用者が労働者の真実の経歴を知っていたならば労働契約を締結しなかったであろうと認められるほど重大なものである場合には、それは当事者の信頼関係を基礎とした労働契約関係あるいは労働者の採用方針や配置計画に重大な影響を及ぼすものであるから、右(前記)経歴詐称が労働契約締結時に生じた事由であり、また、そのため業務遂行に現実的、具体的な支障が生じていなかったとしても、使用者は労働者を懲戒処分することができる。」と判示されています(東京地裁昭和54年3月8日判決(出典:「労働判例」320号43頁、スーパーバッグ事件))。
前科を申告する必要があるのか
一般的に、履歴書には学歴、職歴、そして賞罰を記入することになっています。そのため、もし前科があるのであれば、賞罰の欄に記入しないといけません。しかし、賞罰の記入欄のない履歴書には、書く必要はありません。ただし、賞罰の記入を会社が事前に要求していたり、記入欄があるのにもかかわらず「賞罰なし」と書いたりしてしまった場合は、先ほどと同じ経歴詐称になってしまいます。
賞罰欄に書かなければならない前科とは刑事罰であり、少年犯罪(これは「前歴」と言います)や行政処分は書く必要はありません。例えば、交通違反による免許取消や免許停止は行政処分なので賞罰欄に記載する必要がありません。ひき逃げなど交通違反が重大な場合、行政処分のみならず罰金刑や懲役刑などの刑事罰も併せて受けることがあります。この場合、刑事罰の部分は前科になりますので、賞罰欄に記載すべき事項になります。
前科があると就けない職業
先ほど触れたとおり、前科は資格制限の事由になるため、就けなくなってしまう職業はあります。以下、詳しくみていきましょう。
禁錮以上の刑で欠格事由になる職業
国家公務員
国家公務員は禁錮以上の刑に処せられた場合、その執行が終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまで採用試験を受験できず、現職に就いている場合は当然に失職します(国家公務員法第38条1号、43条、76条)。
地方公務員
地方公務員も、禁錮以上の刑に処せられた場合、その執行が終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまで採用試験を受験できず、現職に就いている場合はやはり失職します(地方公務員法第16条1号、28条4項)。
教職員
教職員が禁錮以上の刑に処せられた場合、公立学校の場合は、先ほどの地方公務員法が適用され、失職します。私立学校の場合でも、禁錮以上の刑に処せられた場合、教員免許状が失効するため、結局、教職員を続けることは困難です(教育職員免許法10条1項1号、5条1項3号)。なお、教員免許状の失効については公立学校も同様です。
保育士
保育士が禁錮以上の刑に処せられた場合、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者は、保育士となることができず、保育士の登録が取り消されます(児童福祉法18条の19第1項1号、18条の5第2号)。ただし、あくまで登録が取り消されるだけであり、資格そのものを失うわけではないため、欠格の期間が過ぎれば再登録することができます。
執行猶予付き判決の場合は、執行猶予期間が満了すれば刑の言渡しの効力が失われるため(刑法27条)、その時点で再登録ができます。
法曹関係者
弁護士は、禁錮以上の刑に処せられると欠格事由に該当し、弁護士名簿の登録を取り消されます(弁護士法7条1項、17条1号)。検察官、裁判官も禁錮以上の刑に処さられると欠格事由に該当し、任命されることができなくなります。(検察庁法20条1号、裁判所法46条1号)
罰金以上の刑で欠格事由になる職業
医師
医師は、罰金以上の刑に処せられた場合、免許が与えられないことがあり、また、既に与えられている免許についても、厚生労働大臣により、医道審議会の意見を聴いた上、取り消されることがあります(医師法4条3号、7条1項3号、同条3項)。
薬剤師
薬剤師も、罰金以上の刑に処せられた場合、免許が与えられないことがあり、また、既に与えられている免許についても、厚生労働大臣により、医道審議会の意見を聴いた上、取り消されることがあります(薬剤師法5条3号、8条1項3号、同条4項)。
看護師
看護師も、罰金以上の刑に処せられた場合、免許が与えられないことがあり、また、既に与えられている免許についても、厚生労働大臣により、医道審議会の意見を聴いた上、取り消されることがあります(保健師助産師看護師法9条1号、14条3号、15条1項)。
前科が海外旅行や出国に及ぼす影響
出国について
海外旅行をするためにはパスポートが必要ですが、日本では、一定の犯罪歴があることにより、パスポートの発給が制限される場合があります。
旅券法第13条
外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者(以下省略)
入国について
入国許可に関する基準は諸外国の法律の定めによって異なっており、犯罪歴によって入国制限を行っている国もあります。一般的に、アメリカは審査が厳しい傾向にあるようです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。以上のように、前科が付くと、就職や海外旅行に及ぼす影響は小さくありません。しかし、重要なことは、刑事事件の被疑者として検挙されたとしてもすぐに前科が付くわけではないということです。前科が付いてしまうまでの間の弁護活動で不起訴になれば前科が付くことはありません。
ただし、一度起訴されてしまえば、無罪になるケースは非常に珍しいため、起訴前の弁護活動で不起訴を勝ち取ることが重要です。検察庁の出している起訴率の累年比較を見ると、2021年・2020年は33.2%、2019年は32.9%であり、3人に2人程度の割合で不起訴になっていることがわかります。前科を付けたくない人はとにかく起訴される前に、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。そして、不起訴に向けてすぐに動いてくれる刑事事件に強い弁護士に依頼しましょう。