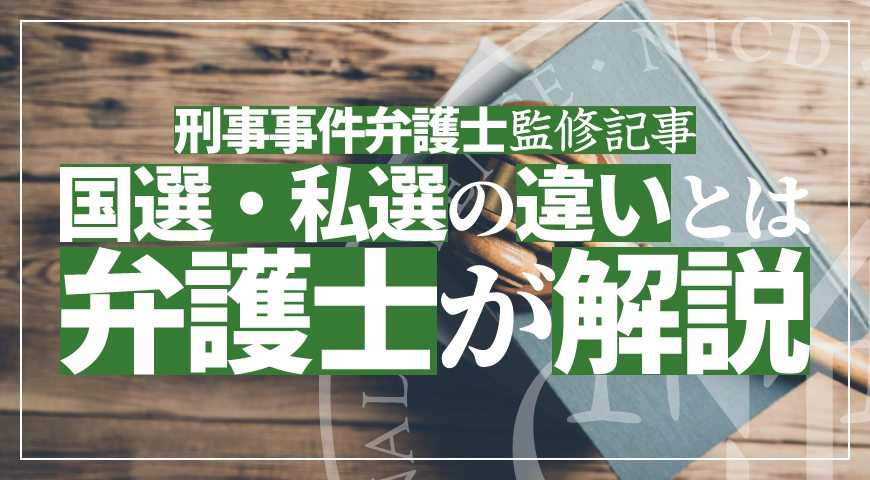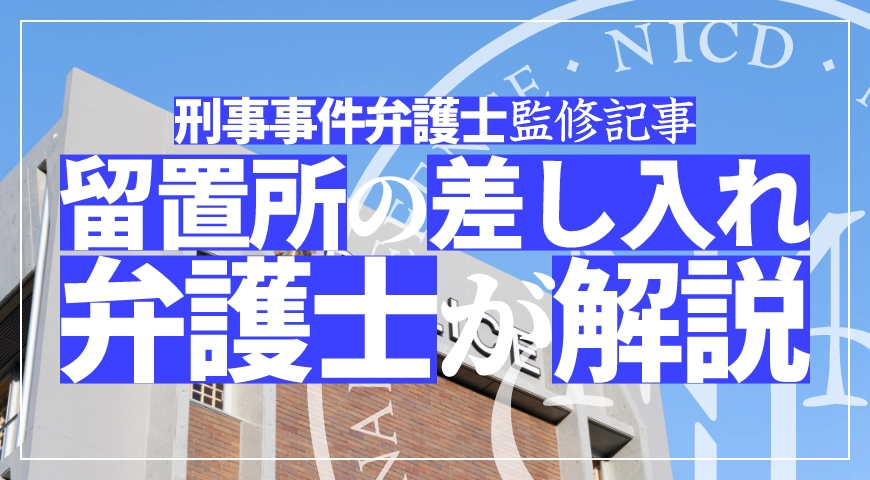国選弁護人と私選弁護人の違い
国選弁護人も私選弁護人も、いずれも弁護人として、被疑者・被告人を擁護する存在であり、その職務や権限に違いはありません。しかし、国選弁護人は国が選任する弁護人であり、制度を利用する場合には国選弁護人名簿に登録された弁護士の中から自動的に割り当てられる仕組みになっています。そのため、私選弁護人のように、被疑者・被告人本人又はそのご家族が自ら弁護士を選択することはできません。
また、国選弁護人の場合、被告人に資力が無ければ、国が弁護士報酬を負担しますが、資力のある被告人の場合には、弁護士報酬は自己負担となります。
国選弁護人はすべての被疑者や被告人につくのですか?
起訴された被告人については、刑事訴訟法上は軽微な事件など一部の事件については弁護人を付けることが必要的とはされていないものの、現在、全ての事件について、私選弁護人が付いていない場合には国選弁護人を選任する運用となっています。
また、国選弁護制度は、当初は起訴された被告人のみを対象とした制度でしたが、刑事訴訟法の改正により被疑者国選弁護制度が導入され、平成18年10月に一定の重大事件について、平成21年5月からは「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件」について、被疑者が勾留されている場合には、被疑者段階でも国選弁護人が就くことができるようになりました(刑事訴訟法37条の2)。
被疑者国選弁護対象事件の拡大によって、殺人・放火・強盗・強制性交等(旧 強姦)といった重大事件だけでなく、傷害・窃盗・詐欺・横領・自動車運転過失致死傷・覚せい剤取締法違反・児童ポルノ規制法違反など、多くの事件が被疑者国選の対象事件となりましたが、全ての事件が対象事件ではありません。
たとえば、暴行・痴漢・盗撮・住居侵入・死体遺棄・麻薬特例法違反(コントロールドデリバリーが実施された事案)などについては、被疑者段階での弁護の必要性が高い場合もありますが、被疑者国選弁護の対象事件にはなっておらず、被疑者段階で国選弁護を利用することはできません。
資力が十分あっても国選弁護人の選任がつきますか?
被告人が国選弁護人の選任を請求するためには、まず、資力申告書(現金、預金等の資産の合計額及びその内訳を申告する書面)を提出し、資力要件を満たすかの審査があります。国選弁護制度の資力要件は、現金や預金を合わせて50万円未満とされています(刑訴法36条の2・36条の3①、刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令1条・2条)。資力が50万円に満たないときは、そのまま選任請求することができます。
一方、資力が50万円以上の場合は、弁護士会に対して私選弁護人選任申出の手続をしたものの、申出を受けて接見をした弁護士が受任しなかった場合に限り、国選弁護人を請求できます(同法37条の3②、36条の3①)。
国選弁護人がつかない事件の場合、私選をつけるために援助制度はありますか?
逮捕・勾留されたものの、被疑者国選弁護対象事件でないため国選制度を利用できない場合があります。また、国選弁護人は勾留決定後に選任手続が始まるので、逮捕後、勾留決定までの72時間は国選弁護対象事件であっても国選弁護人が付きません。この場合、私選弁護人をつけることになりますが、十分な資力がなく、私選弁護人を依頼することもできない場合には日本弁護士連合会の刑事被疑者弁護援助事業の利用が可能な場合があります。