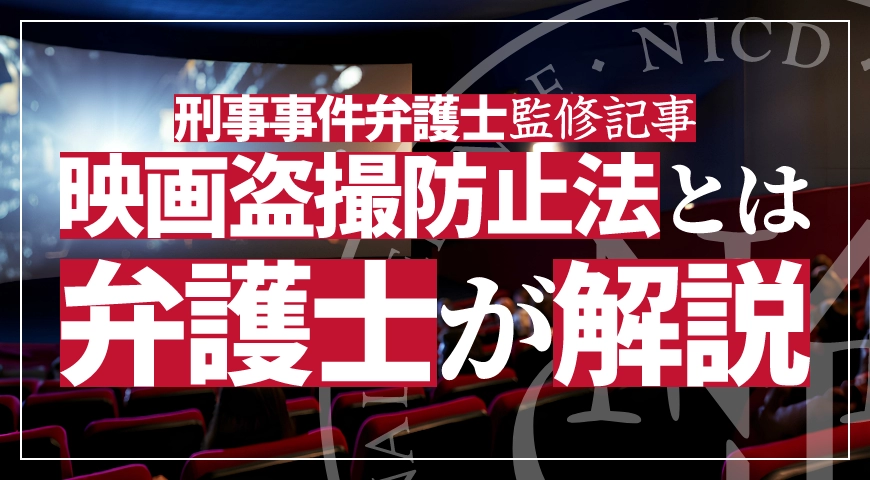近年、テレビドラマなどの影響で知的財産権という言葉を聞く機会が多くなっています。
知的財産権は、民法の土地や物の所有権などと異なり、形の無いものを保護するための権利です。
知的財産権は、企業や創作活動を行う個人にとっては馴染みがある言葉ですが、馴染みがない人にとっては、どのような権利であるのかを想像することが難しいのではないでしょうか。
しかし、知的財産権を侵害した場合には、懲役刑や罰金刑を科される可能性があるため、事前に知的財産権について理解しておく必要があります。そこで、知的財産権に関する刑事事件について、知的財産権の内容・刑罰の内容を示した上で、詳しく説明します。
知的財産権とは?
知的財産権とは、簡単に言えば、知的財産法で保護されている情報・発明・表現などに対して与えられる権利です。知的財産法とは、一般的に、特許法・実用新案法・意匠法・商標法(4つをまとめて工業所有権法と呼ばれます。)と著作権法を指します。そして、各々の法律で保護されている権利を総称して知的財産権と呼びます。そこで、各々の法律について簡潔に説明します。
特許法
特許法は、耳にする機会が多い「特許」を保護している法律です。特許とは、産業上利用可能である発明をいい、物の発明(発明が物に具現化されたもの)・方法の発明(発明がプロセスを要件としている場合)・物を生産する方法の発明(物の生産方法やその生産方法で作られた物)に分類されます。
発明とは、自然法則に則った産業上利用可能である新規性・進歩性などの認められる技術的思想をいいます。つまり、特許法とは、簡単にいうと、産業上利用可能である新しい技術的思想を保護している法律であるといえます。産業上利用可能である新しい技術的なアイデアであれば、複雑な仕組み・構造ではなく簡単な仕組み・構造であっても発明として認められることになります。例えば、アイスで知られる「雪見だいふく」は、独自技術により成分を調整した粘弾性物でアイスクリームを被覆するという特徴から、特許発明として認められています。
実用新案法
実用新案法は、物の形状・構造などの考案(発明より高度でないもの)を保護している法律です。簡単にいうと、発明に比べて日常的なアイデアなどが保護されています。特許法との違いは、特許権の権利期間が20年であるのに対して考案は10年であることや、権利登録の方法が特許権に比べて簡単であることなどが挙げられます。
そのため、ビジネス上の寿命が短い商品などの場合には、特許権より考案の方が迅速に対応できる場合があります。実用新案として身近に存在する具体的な例として、よく目にする「シャチハタ」のハンコが挙げられます。
意匠法
意匠法は、物品のより美しい外観やより使いやすい外観などのデザインを保護している法律です。具体的には、物の形状・模様・色彩などのデザインを保護しており、物の外観に現れていない構造的機能は保護の対象とはなりません。
商標法
商標法は、商品やサービスに付される目印である商標を保護している法律です。商標は、商品やサービスなどの出所を表示する機能・品質を保証する機能・広告機能などを有しているため、商標法により保護されています。商標は、具体的には、知覚により認識できる文字・図形・記号・色彩・動き・ホログラム・音・位置などをいいます。
著作権法
著作権法とは、著作物に対する著作権を保護している法律です。著作物とは、簡単にいえば、自分の思想や感情を自ら工夫して文字や音楽や形などで表現したものをいいます。具体的には、小説・漫画・楽曲などが挙げられます。
知的財産権侵害に対する刑事制裁の立法動向
特許法
特許権侵害の罪について(特許法第196条)
特許法では、特許権侵害の場合に、権利侵害罪として10年以下の懲役または1000万円以下の罰金のいずれか、または両方を科すと規定されています(特許法第196条)。また、法人の代表者・法人の使用人・法人の代理人などが法人の業務に関して、特許権侵害を行った場合には、3億円以下の罰金刑が科されます(特許法第201条第1項第1号)。
特許権のみなし侵害について(特許法第196条の2)
特許法は、特許権侵害を助長したり促進したりする行為を「間接侵害」として規定しています(特許法第101条各号)。そして、「間接侵害」にあたる場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金のいずれか、または両方を科すと規定されています(特許法第196条の2)。
虚偽表示の罪について(特許法第198条)
特許法は、特許表示の虚偽表示をする行為をした場合に、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科すと規定しています(特許法第198条)。虚偽表示とは、特許を受けていないにもかかわらず特許を受けたように表示する行為や特許を受けた物と勘違いするような紛らわしい表示をする行為をいいます(特許法第188条)。
詐欺の行為の罪(特許法第197条)
詐欺により特許を取得したり、延長登録などを受けたりした場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科されます(特許法第197条)。
実用新案法
実用新案法においても、特許法と同様の罰則規定があります。
実用新案権の侵害(実用新案法第56条)
5年以下の懲役または500万円以下の罰金のいずれか、または両方。法人の代表者などは、3億円以下の罰金。
詐欺の行為の罪(実用新案法第57条)・虚偽表示の罪(実用新案法第58条)
1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
意匠法
意匠法においても、特許法と同様の罰則規定があります。
意匠権侵害の罪(意匠法第69条)
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金のいずれか、または両方。法人の代表者などは、3億円以下の罰金。
みなし侵害の罪(意匠法第69条の2)
5年以下の懲役または500万円以下の罰金のいずれか、または両方。
詐欺の行為の罪・虚偽表示の罪
1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
商標法
商標法においても、特許法と同様の罰則規定があります。
商標権侵害の罪(商標法第78条)
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金のいずれか、または両方。法人の代表者などは、3億円以下の罰金(82条)。
みなし侵害の罪(商標法第78条の2)
5年以下の懲役または500万円以下の罰金のいずれか、または両方。
詐欺の行為の罪(商標法第79条)・虚偽表示の罪(商標法第80条)
3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
著作権法
著作権侵害の罪について(著作権法第119条第1項)
著作権法では、著作権侵害の場合に、権利侵害罪として10年以下の懲役また1000万円以下の罰金のいずれか、または両方を科すと規定されています(著作権法第119条第1項)。また、法人の代表者・法人の使用人・法人の代理人などが法人の業務に関して、著作権侵害を行った場合には、3億円以下の罰金刑が科されます(著作権法第124条第1項第1号)。
著作者人格権の侵害・みなし著作権侵害について(著作権法第119条第2項)
著作権法は、著作者の意に反した著作物の改変・著作者名の不表示などをされない権利を著作者人格権として保護しています。そして、著作者人格権を侵害した場合にも、5年以下の懲役または500万円以下の罰金のいずれか、または両方を科すと規定されています(著作権法第119条2項第1号)。
また、著作権法は、著作権侵害を助長したり促進したりする行為を「みなし著作権侵害」として規定しています(著作権法第113条)。そして、「みなし著作権侵害」にあたる場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金のいずれか、または両方を科すと規定されています(著作権法第119条第2項各号)。
その他の犯罪
その他、以下のような場合について罰則が規定されています。
著作物を違法ダウンロードした場合
2年以下の懲役または200万円以下の罰金のいずれか、または両方
著作権を保護している技術的手段を回避して複製したり複製物を譲渡したりした場合
3年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれか、または両方
著作者名を詐称して複製物を頒布した場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金のいずれか、または両方
親告罪について
なお、日本の著作権法において、著作権侵害の大部分は親告罪とされています(著作権法第123条)。親告罪とは、被害者などの親告(刑事告訴)がない場合には検察官が起訴することができない犯罪をいいます。しかし、検察官が著作権侵害を自由に訴追できれば、近年多発している海賊版を迅速に検挙することができるようになります。そこで、TPPなどの影響により、日本において著作権侵害について非親告罪化の動きが生じています。
どのような知的財産権侵害が刑事事件となるか
知的財産権侵害事犯の検挙数
知的財産権侵害事犯のうち、偽ブランド事犯などの商標権侵害事犯、海賊版事犯などの著作権侵害事犯については、インターネットを利用した犯罪行為である場合が多いため、警察のサイバーパトロールにより検挙されるケースが多くなっています。
平成28年度の知的財産権侵害事犯の検挙状況について、全体の総事件数は594件、総人員数は730人となっています。そのうち、偽ブランド事犯などの商標権侵害事犯については、事件数304件・人員数は381名、海賊版事犯などの著作権侵害事犯については、事件数238件・人員数267名となっており、知的財産権侵害事犯の検挙数の大半を占めています。つまり、知的財産権侵害事犯のうち検挙される事犯のほとんどが著作権侵害事犯と商標権侵害事犯であるということになります。
また、平成28年度における商標権侵害事犯検挙事件に占めるインターネット利用事犯の割合は、82.2%であり、著作権侵害事犯検挙事件に占めるインターネット利用事犯の割合は、91.2%となっており、ほとんどがインターネット利用事犯であるといえます。
特許権侵害事犯の検察庁新規受理人員が少ない理由
犯罪白書によると、平成28年度における特許法違反について、検察庁新規受理人員数は、3名です。また、平成27年度も3名であり、平成26年度は0名と著作権法違反・商標法違反に比べて極端に少ない数字になっています。特許権だけでなく意匠権・実用新案権も同様に、極端に少ない数字になっています。
特許権は、新しい技術的思想でなければ発明として保護されないため、以前から存在していた発明と同様のもの(公知例と呼ばれます)であれば事後的に無効になることがあり、侵害があったかを判断することが困難です。
事後的に無効になる可能性がある特許権の侵害により刑事罰を与えることは、リスクが大きく、刑事罰の適用について慎重に判断する必要があります。そのため、特許権などの検挙数・受理人員数が極端に少なくなっていると考えられています。
刑事事件となりやすい知的財産権侵害事犯
上記のように、インターネットを利用した著作権侵害事犯・商標権侵害事犯については、サイバーパトロールなどにより検挙されて刑事事件になる可能性が高いと考えられます。一方で、特許権侵害事犯などは性質上検挙されにくいと考えられるものの、数名は検挙されているため、検挙されて刑事事件になる可能性は十分に考えられます。
過去に起きた知財に関する刑事事件
知的財産権侵害事犯として検挙された事例
- 市販の音楽作成ソフトを無断複製した上でインターネットオークションに出品し、落札者にソフトをダウンロードさせ、約2千万円の収益を上げ、ソフト会社の著作権を侵害したとして著作権法違反の疑いで逮捕された事例(平成30年7月19日 大阪府警)。
- インターネットで海賊版漫画を無料で読むことができるリンク先を集めた誘導サイトを運営し、不特定多数の人が読める状況にして著作権を侵害したとして、サイトを運営していた5名と海賊版漫画を投稿していた4名が著作権法違反の疑いで逮捕された事例(平成29年10月31日 大阪・千葉・福岡などの9府県警)。
- 他社のゲームキャラクターを、漫画作品内において無断で使ったとして、ゲームソフトなどの製作で知られる漫画作品の発行元の会社と編集出版部門の役員・担当者15名と漫画作者が書類送検された事例(平成26年11月17日 大阪)。
- 高級ブランドに似た商標を付けたバッグをネットオークションで3ヶ月間にわたり約85点を販売していたことから、高級ブランドに似た商標を付けたバッグを販売目的で持っていたとして、商標法違反の疑いで逮捕された事例(平成30年7月25日 佐賀)。
- 警備会社大手の会社のロゴが印刷された偽のステッカーを自宅でパソコンやプリンターなどを用いて作成し、インターネットのオークションサイトで「防犯ステッカー」などと称して販売したとして商標法違反の疑いで逮捕された事例(平成30年8月2日 東京)。
知的財産権侵害事犯についての裁判例
- 配送業を営んでおり発売前の漫画を入手できる立場にあった被告人が、人気漫画の発売前作品をデジタル化してパソコンのサーバーに保存して海賊版サイトに公開し、著作権を侵害した事例(京都地決平成28年3月1日)。
→懲役10月、執行猶予3年 - 商標権者が販売した家庭用テレビゲーム機について、ハードウェアには一切改変を加えていないが、同機の書換え可能な内蔵メモリに記録されたファームウェアを改変して同機専用のプログラム以外のプログラムも実行できるようにして販売し、商標権を侵害した事例(名古屋高決平成25年1月29日)。
知的財産権侵害で告訴される可能性は?
知的財産権侵害は、著作権法違反の場合を例に挙げると、動画共有サイトにアップロードされている動画をダウンロードしたり、インターネットにアップロードされている写真を無断で使用したりすることなどにより容易に生じます。著作権法では、著作権法違反は親告罪となっていますが、突然告訴される可能性は十分に考えられます。
平成28年度の犯罪白書によると、著作権法違反で送検されてしまうと、206名が起訴されているのに対し111名が不起訴となっており、起訴率は65%となっています。また商標法違反で送検されてしまうと、357名が起訴されているのに対し200名が不起訴となっており、起訴率は64.1%となっています。つまり、著作権法違反や商標法違反で刑事告訴されてしまった場合には、約65%が起訴されてしまうことになり、刑事裁判に発展することになります。
もし刑事告訴されてしまったら?
知的財産権侵害で刑事告訴されて刑事事件になってしまった場合には、被害の程度によっては、弁護士に相談し、被害者との示談交渉を行って和解を成立させ、反省の態度を十分に示すことにより、起訴されないことも十分考えられます。
もっとも、身に覚えのない場合には、反省の態度を示すことにより裁判の際にかえって不利益を被る場合があります。いずれの場合にも、迅速かつ的確な対応が不可避となるため、直ちに弁護士に相談することが大事になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。知的財産権侵害は、インターネットが発達した現代社会において、誰でも巻き込まれてしまう可能性があり、対応を誤ると長期の懲役刑や多額の罰金刑という重い処分を受ける可能性が有ります。