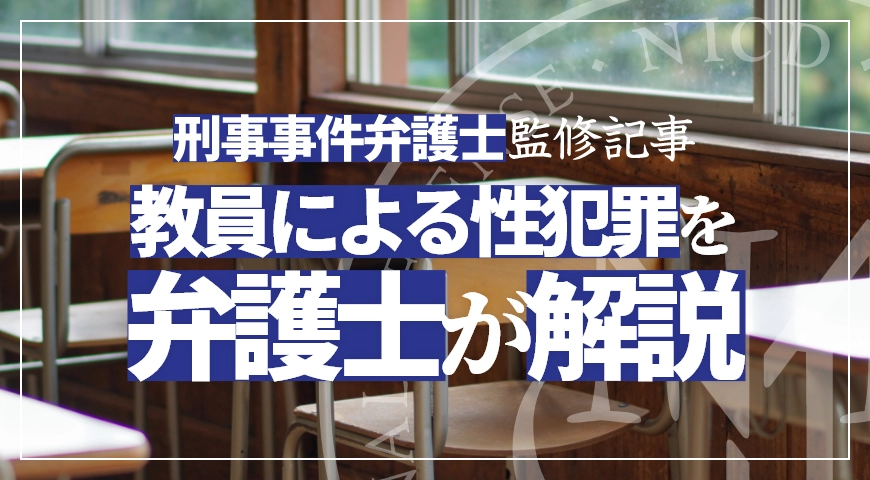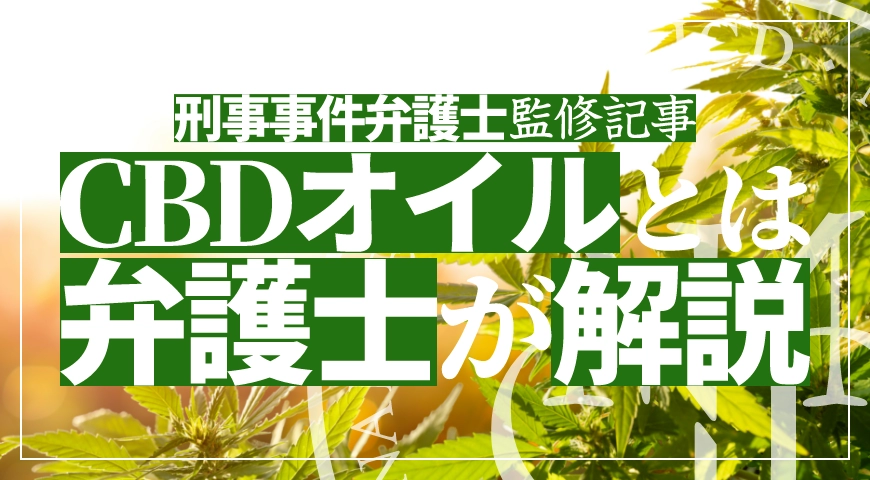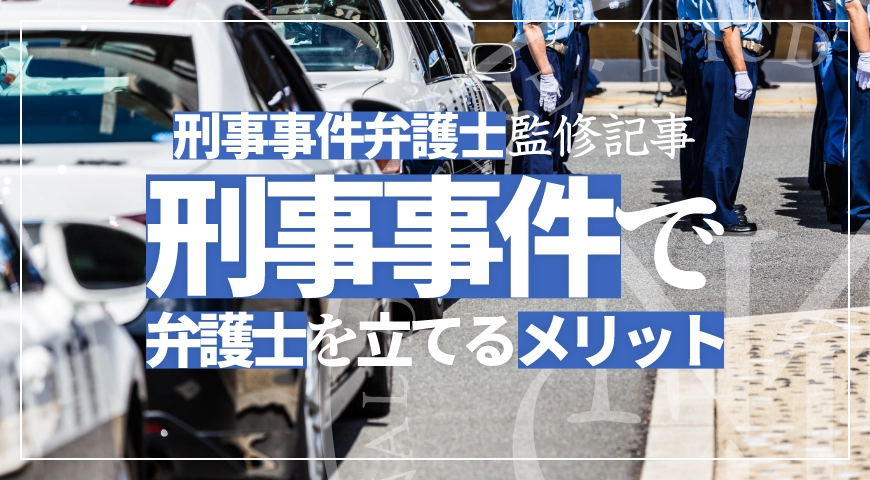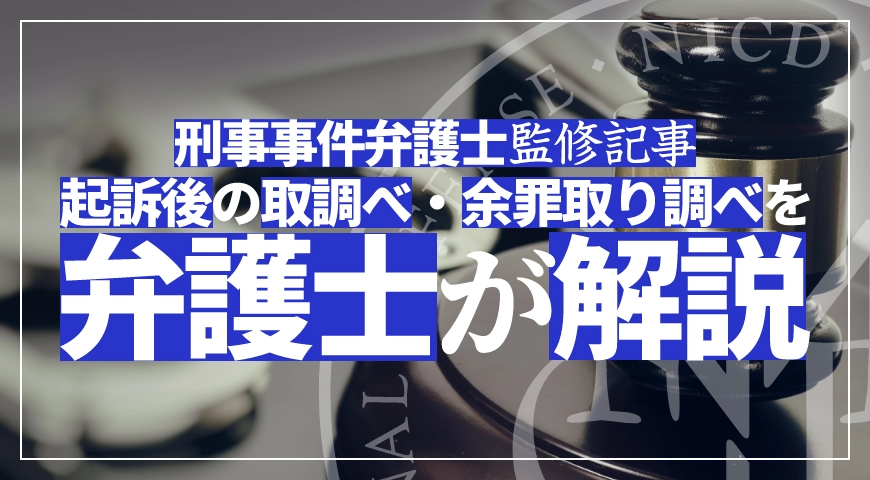
捜査が始まり、逮捕され、勾留されるとその後の重大関心事は起訴されるか不起訴となるかになります。
残念ながら不起訴処分とはならずに、「起訴」されてしまった方もいらっしゃるかと思います。
また、ご家族が逮捕・勾留され、起訴されてしまった方もいらっしゃるかと思います。起訴とは、裁判にかけられるという意味で、刑務所に行くか否かといった厳しい現実にさらされます。起訴が取り消される(公訴取消)ということはまずありません。実刑か猶予付き判決か、あるいは無罪か、この3つの可能性があるだけです。
ただ、起訴されて、それで終わりではありません。起訴されて、公判請求された場合には、裁判を受ける必要があります。また、裁判を受けるだけでなく、起訴後も警察から、再度取調べを受けることがあります。
起訴された後であっても、弁護士に相談するのは遅くはありません。裁判の対応だけでなく、起訴後の取調べの対応について、弁護士に相談することで、適切な対応を取ることができるのです。
このページでは、起訴後に取調べが行われるのはどんなケースか、起訴後の取調べにはどのように対応するべきか、ということを代表弁護士・中村勉が解説していきます。
起訴後の手続の流れ
まず、起訴後の手続の流れについて、簡単に解説します。捜査が終結し、事件について裁判所の審理を求めることを起訴(または公訴の提起)といいます。起訴は、検察官が、裁判所へ起訴状の提出をする方法によりなされます。
この起訴状の謄本が、裁判所から被告人(起訴前は「被疑者」と呼ばれますが、起訴後は「被告人」と呼ばれます)に送達されます。起訴状には公訴事実(罪となるべき事実)が書かれているので、被告人は、起訴状の謄本を受け取り、自分が何の事実で裁判を受けることになるのかを知ることができます。
起訴には、公判審理を求める公判請求と、簡易裁判所に公判審理によらずに100万円以下の罰金または科料を科すことを求める略式請求・略式命令があります。公判請求された場合は、(後に述べる公判前整理手続に付されるものはこれを経た後に、)指定された第一回公判期日に裁判が開廷されます。
第一回公判期日までは検察官、被告人側ともに可能な限り証拠の収集および整理をして審理が迅速に行われるように事前準備を行います。弁護人は、被告人その他関係者に面接をして事実関係を確かめたり、閲覧した証拠書類等についてこれに同意するか否か、人証等の取調べの請求に関し異議がないか否かの見込みを、裁判所書記官や検察官に通知したりします。
また、第一回公判期日に先立ち、裁判所が、弁護人と検察官を出頭させて、公判期日の指定その他訴訟の進行に関し必要な事項についての打合せを行うこともあります。
起訴後は、被告人は、警察の留置場から拘置所に移送され、保釈が認められない限り、身体拘束が継続されることになります。裁判となっている事件が、通常の自白事件1件の場合であれば、起訴された後、概ね1、2か月後には判決が下されることが多いです。
起訴後の取調べ
起訴後に取調べが行われるケースとしては、起訴された事実についての取調べ、もしくは、別件の余罪についての取調べが考えられます。以下、それぞれのケースについて解説していきます。
起訴された事実についての取調べ
起訴された事実について、起訴後に取調べを行うことは原則として許されません。しかし、被告人が任意に取調べに応じる場合や、取調べが被告人の防御権を実質的に侵害しないよう最小限度にとどめられる場合など、例外的な場合には許されることがあります。そのような、起訴後の取調べが許される例外的な場合について、判例をご紹介します。
大阪高判昭43.12.9判時574.83
「検察官(ないし捜査官)が起訴後において被告人を当該公訴事実に関して取り調べうるのは、被告人が自ら供述する旨を申し出て取調を求めたか、あるいは、取調のための呼出に対し、被告人が取調室への出頭を拒み、または出頭後いつでも取調室から退去することができることを十分に知ったうえで、出頭し、取調に応じた場合にかぎられる」
大阪高判昭50.9.11判時803.24)
「起訴後捜査官が当該事実について被告人を取り調べることは、被告人の防御権を実質的に侵害しないよう最小限度にとどめるべきであり、殊に被告人が現実に検察官と対等の当事者としての活動を開始する第一回公判期日以後は許されない」
このように、起訴後の取調べは無制限に許されるわけではないので、違法な起訴後の取調べが行われていないか、弁護士に相談することが必要です。
余罪についての取調べ
すでに起訴された事実以外にも事件を起こしている場合、その余罪についても取調べが行われることがあります。一般に、窃盗や特殊詐欺、性犯罪など、犯行を繰り返す傾向があるような犯罪類型については、余罪があることが多く、捜査機関も余罪の存在を念頭に捜査をします。そして、捜査の過程で、余罪に関する証拠が出てきた場合には、起訴後に余罪の取調べが行われることが多いです。
余罪の取調べについては、起訴された事実についての取調べとは異なり、原則として禁止されているわけではありません。しかし、すでに起訴されている事実についての身体拘束を利用して、余罪について本格的な取調べが行われるなど、いきすぎた起訴後の取調べは違法になることもあります。
また、余罪についての取調べに応じることで、余罪についても起訴されてしまう可能性が高まります。そこで、起訴後の余罪についての取調べにはどのように対応するべきなのか、専門家である弁護士に相談することが必要です。
起訴後に弁護士をつける必要性
起訴前に弁護士をつけることで、逮捕・勾留といった身体拘束からの解放を目指した弁護活動や、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動をすることができます。
しかし、起訴後であっても、弁護士をつける必要性があることには変わりはありません。起訴後に弁護士をつけることで、どのようなことができるか、起訴後の取調べや、余罪の不起訴処分を目指した弁護活動を中心に、ご説明いたします。
起訴後の取調べへのアドバイス
起訴された事実についての取調べを受けた場合
起訴された事実についての取調べを受けた場合、取調べに応じるべきか否かは、慎重に判断する必要があります。先ほど説明したように、そもそも原則としては、起訴後の取調べは許されません。さらに、安易に取調べに応じることで、例えば、犯情が悪い調書が作成されてしまうことがあり、その場合には、その調書が量刑を重くする資料として使われる危険性があります。
もっとも、取調べに応じることでメリットがある場合もあります。例えば、起訴前に否認していたことから保釈請求が認められなかったものの、その後、認めに転じて、再度の保釈請求をするような場合があります。その場合、起訴後の取調べに応じて自白調書が作成されることで、否認していた場合よりも、保釈される可能性が上がる場合もあります。
このように、専門家である弁護士に相談をして、起訴された事実についての取調べに応じるメリットとデメリットを考えたうえで、起訴後の取調べの対応を考える必要があるのです。
余罪についての取調べを受けた場合
余罪についての取調べを受けた場合に、仮にその余罪に心当たりがあるとしても、自己の判断で、余罪について安易に自白をしてしまうのは危険です。なぜならば、捜査機関の手元にどの程度の証拠があるかわからないので、余罪が立件されるかされないか、ご自身で見通しを立てることは困難だからです。
仮に、捜査機関の手元にある証拠が薄いにもかかわらず、安易に自白をしてしまうことで、捜査機関は、その自白を材料にして捜査を進め、証拠が収集され、余罪が立件されて起訴される可能性も十分にありえるのです。
このように、起訴後の余罪に関する取調べについて、どのように対応するのかをご自身で判断するのは危険です。すでに起訴されている事件の内容・性質、余罪の内容・性質、今までの取調べにおける供述状況、考えられる証拠などを、弁護士が経験と知識に基づいて総合的に考慮したうえで、起訴後の取調べにどのような対応をすべきか、弁護士からアドバイスを受ける必要があります。
余罪の不起訴へ向けての弁護
例えば、余罪について、捜査機関が十分な証拠が収集できていない可能性があるような場合には、起訴後の取調べにおいては、黙秘権を行使することが考えられます。黙秘権を行使することで、捜査機関に情報を与えず、証拠不十分による不起訴を目指した弁護活動を行います。
また、余罪について、起訴される前に被害者と示談を成立させることで、不起訴を目指す活動をすることができます。被害者がいる事件では、検察官の起訴・不起訴の判断には、被害者の意向をある程度尊重することが多いので、示談を成立させて、被害者が刑事処罰を望んでいないなどの意向を検察官に伝えることが大切です。
しかし、事件の内容や性質、起訴された事件や余罪における被害者の数、などの様々な事情よっては、起訴前に示談を成立させても、必ずしも不起訴とならないことがあります。
もっとも、仮に余罪が起訴されてしまった場合であっても、被害者との示談は、裁判で量刑を決める際に、量刑を軽くする方向に考慮される一事情となります。ゆえに、余罪についての被害者との示談成立は、検察官の起訴・不起訴の判断、あるいは裁判での量刑を軽くする事情として、有利に考慮されることになります。
まとめ
起訴後の取調べについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。安易に起訴後の取調べに応じてしまうことで、すでに起訴されている事実について量刑が重くなったり、余罪について立件され、起訴されてしまったりする可能性があります。
「もう起訴されてしまったのだから、今さら弁護士に相談しても遅い」などと、諦める必要はありません。起訴後であっても、弁護士に相談することで、今からでもとりうる適切な対応について、アドバイスを受けることができるのです。
起訴後の取調べについて、困ったことがありましたら、ご自身で判断せず、専門家である弁護士へ相談してください。