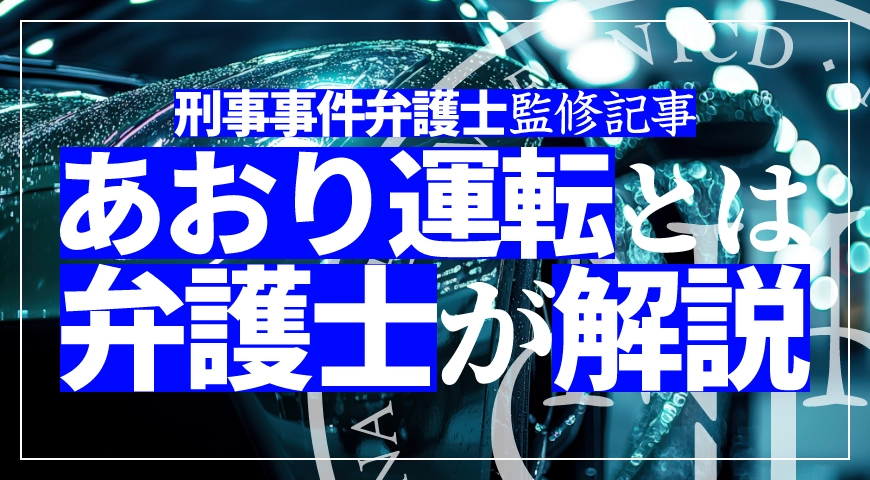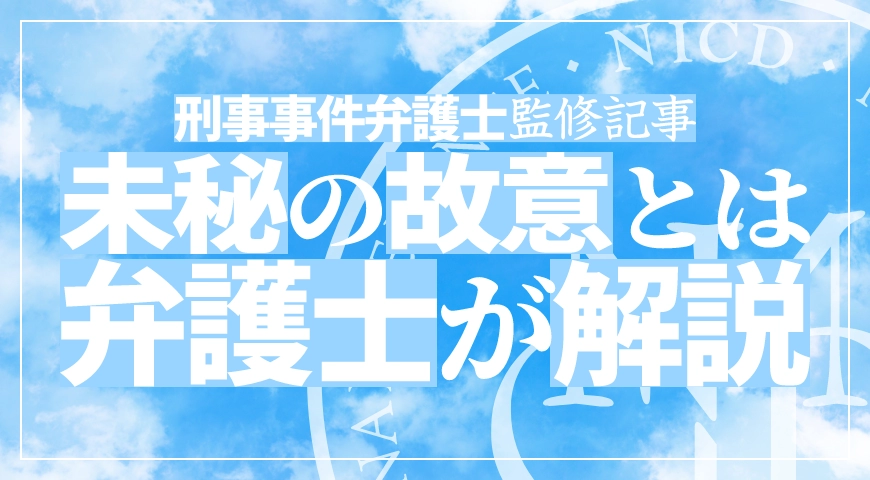
ここでは、未必の故意とはどのようなものなのか、故意が問題になった場合の量刑への影響について弁護士・中村勉が解説します。
未必の故意とは?故意が量刑に与える影響を弁護士が解説
最近はニュースでも見聞きするようになった「未必の故意」という法律用語。一般の方が耳にすると「密室の恋」というようにも聞こえ、ますます意味がわからなくなってしまうかもしれません。
未必の故意は、少なくともそのような故意があれば犯罪が成立する、というように使われることが多く、故意が争点となっている事件で主に問題となります。
例えば、殺人事件で「殺すつもりではなかったが、これをすれば死ぬかもしれないとは思っていて、死んでもいいと思っていた」場合に、被害者が死亡したとなると、「未必の故意」があったものとされて、故意が認められ、殺人罪で罰されることになります。
このように、未必の故意の有無は犯罪行為を成立させる重要なポイントとなります。
故意と過失
故意は犯罪の成立に基本的に必要な要件です。
故意がなくても犯罪が成立するのは、過失によって結果を発生させた場合にも罰する旨が法律上明記されているときに限られます。
法律上明記されているものとしては、過失傷害罪(刑法第209条)、過失致死罪(刑法第210条)、業務過失致死傷等罪(刑法第211条)、過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)などが挙げられます。
過失とは、必要な注意を怠って結果を発生させてしまうことをいいます。
例えば、金属バットで素振りをする場合、それが他人に当たってしまうと大けがをすることが考えられますので、素振りを始める前に近くに人がいないことを確認した上でそれをすべきといえます。
それにもかかわらず、そのような確認をせずに金属バットで素振りをして、金属バットが近くにいた人に当たってその人が怪我をすれば、必要な注意を怠ったことによりその人を負傷させたということができます。この場合、「過失により人を傷害した」(刑法第209条1項)といえますので、過失傷害罪が成立します。
これに対し、金属バットを他人の身体に当てるつもりで振って、金属バットがその他人の身体に当たってその他人が怪我をすれば、故意があるのが明らかですので、傷害罪(刑法第204条)が成立します。
それでは、金属バットで素振りをするのに、周囲を確認したところ、近くに人がいて、その場所で素振りをすればバットがその人に当たるかもしれないと思ったものの、その人に当たっても別によいと思って金属バットで素振りし、それがその人に当たってその人が怪我をした場合はどうでしょうか。
法律上は、この場合でも故意があると判断されて、傷害罪(刑法第204条)が成立します。
確定的故意と未必の故意
故意というと一般的に「わざと」「意図して」といった意味で用いられますし、そのような意味であると理解される方がほとんどだと思います。
しかし、法律上の故意は、その行為が犯罪の結果を発生させることになること、あるいは、発生させることになる可能性があることを認識しながら、あえてその行為をすることと解釈されています。
つまり、犯罪の結果が発生しても構わないと思っていること、すなわち結果の発生を認容していることが故意の成立に重要な点となります。
故意は大きく分けて、確定的故意と未必の故意の2種類があります。
確定的故意は分かりやすいと思います。「わざと」「意図して」というように、「故意」という言葉から自然に想像されるものがこれに当たります。犯罪行為をするつもりで行っているのであれば、確定的故意があるといえます。
これに対し、未必の故意はそれまでの意思はない場合で、「犯罪行為に当たるかもしれない」「犯罪の結果が発生するかもしれない」と思っていながら「犯罪行為に当たってもよい」「犯罪の結果が発生してもよい」とそのことを認容して行為にうつしている場合は、未必の故意があるといえます。
未必の故意が問題になる事例
では、未必の故意が問題になる状態とはどのような状況でしょうか。
拳銃で人を撃ったケースでみてみましょう。
「殺すつもりで、発砲した」場合には、故意が明確にあるため、故意の有無は争点にならず、殺人罪に問われます。問題になるケースは「殺すつもりではなかったが、結果的に銃弾が相手に当たり、死亡した」という場合です。
誤発砲して相手が死亡してしまった場合には、相手が死亡する可能性を認識していなかったといえますので、未必の故意は認められず、過失のみあったとして殺人罪ではなく過失致死罪に問われるでしょう。
脅しのつもりで相手の近くに向けて発砲したものの、銃弾が相手にあたってしまって相手が死亡した場合に、相手が死亡する可能性を全く予期していなかったのであれば、傷害致死罪に問われる可能性が高いです。
相手が死亡する可能性を全く予期していない点で殺人の故意は否定されますが、相手の近くに向けて発砲している以上、銃弾が相手の身体に当たってしまう可能性は認識・認容していたと言い得るからです。この場合、傷害の未必の故意が認められるとも言えます。
殊更に相手を殺害する意図はなかったとしても、相手と銃撃戦になっていた場合には、銃弾が相手に当たり、相手が死亡する可能性は予期できますし、それを認識しながらあえて発砲しているため、相手が死亡することを認容していたとして、殺人罪の未必の故意が認められ、殺人罪に問われる可能性が高いでしょう。
未必の故意は、殺人罪だけでなく交通事故や、大麻・覚せい剤の薬物事件、詐欺事件でもしばしば争点になり得ます。薬物の場合だと「覚せい剤か確実にはわからないが、覚せい剤であっても構わない」といった場合に未必の故意が認められ、覚せい剤取締法違反で罰せられることになるでしょう。
同様に「これは詐欺かもしれないが、お金がもらえるならいいか」と受け子などの詐欺行為に加担した場合も未必の故意があったとして詐欺罪に問われます。
未必の故意が成立すると量刑はどうなるか
傷害致死罪で問われていたのが、殺人の未必の故意が認められるとして、殺人罪となった場合の量刑を見てみましょう。
傷害致死罪の場合は、「三年以上の有期懲役」(刑法第205条)となっていますが、殺人罪では、「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」(刑法第199条)となりますので刑には大きな差が出てきます。
次に、過失致死罪で問われていたのが、殺人の未必の故意が認められるとして、殺人罪になった場合ですが、過失致死罪は、「五十万円以下の罰金に処する」とされており(刑法第210条)、罰金刑の規定しかないにもかかわらず、殺人罪に問われることとなれば、上述のとおり、「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」という非常に重い刑になってしまいます。
つまり、故意の認定、特に未必の故意の有無により、これだけ量刑に影響があるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。度々報道で話題になる「未必の故意」がどのようなものかを解説しました。
犯罪の成立には、故意が必要ですし、故意の有無は量刑にも大きな影響を与えます。
そのため、捜査機関は、故意の立証に力を入れて捜査をしています。故意でやったわけではないといった主張を一人で続けるのは険しい道になります。
刑事事件に詳しい弁護士に相談し、取調べでの受け答え方法や捜査機関の傾向等を把握することで安心を得ることができるでしょう。
中村国際刑事法律事務所は、関東近郊や東海エリアや関西エリアの刑事事件に対応しており、年間3000件を超える法律相談を承っております。
警察捜査の流れ、被疑者特定に至る過程、捜査手法、強制捜査着手のタイミング、あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し、判決予測も可能です。
初回相談は無料ですので、刑事事件でお困りの方はお問い合わせください。