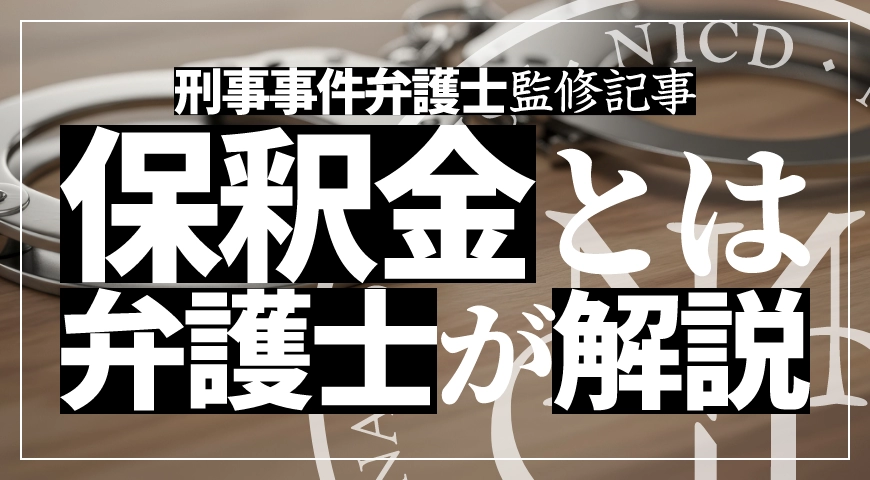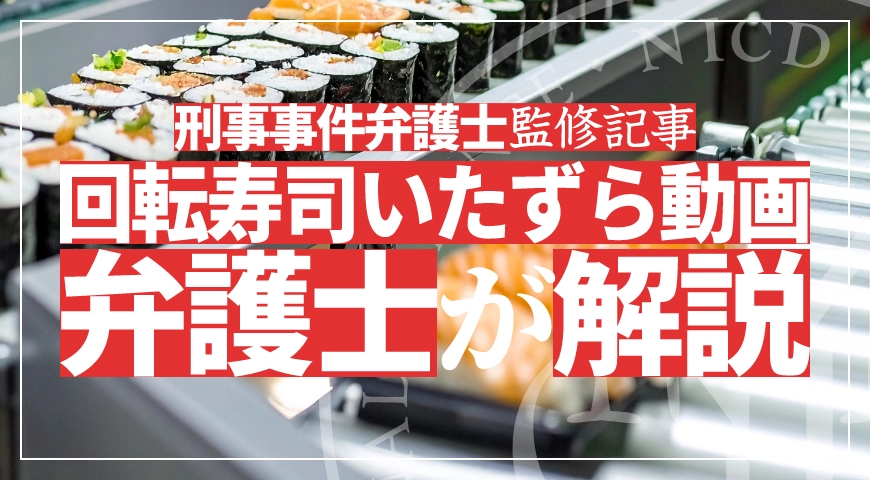刑事事件に巻き込まれたものの、最終的に「微罪処分」となった、そんな話を耳にしたことはありませんか。
ドラマのタイトルとしても有名ですが、検察官へ送致され「起訴」された場合、「99%」有罪となります。一方、微罪処分は、検察官への送致そのものを行わない、いわば例外的な処理と言えます。
しかし、具体的にどのような手続なのか、そして自分や家族が対象になった場合にどのような影響があるのかを正しく理解している方は多くありません。
一見すると「軽い処分で済んだ」という印象を受けがちですが、「前科・前歴として扱われるのか」、「今後の就職や資格取得に影響は出ないのか」、「記録が残ってしまうのではないか」といった不安を抱える方も多いです。
この記事では、微罪処分の定義、法的根拠、具体的な判断基準、そして微罪処分を獲得するために重要な弁護士による早期対策と示談交渉の重要性について詳しく解説します。
微罪処分とは? 刑事手続の例外的な処理
微罪処分の定義と全件送致主義の例外
微罪処分とは、犯してしまった罪が軽微である場合に限り、検察官に送致せず警察だけで処理する手続を指します。これは「不送致」とも呼ばれます。
日本の刑事手続においては、警察が認知した事件の「全件送致」が基本原則となっています(刑事訴訟法 第246条)。
警察が捜査を行った事件は、たとえ軽微であっても、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致(送検)しなければならないのが原則です。検察官は送致された事件の起訴/不起訴を判断します。
しかし、微罪処分は、この全件送致主義の例外であり、検察官への送致そのものを行わず、警察限りで事件を終結させる処理です。微罪処分となれば、検察官の手に事件は届かず、結果として、正式な刑事裁判手続には進むことなく事件が終結します。
微罪処分の趣旨と沿革
微罪処分が存在する主な理由は、刑事手続の効率性と被疑者への配慮にあります。概ね以下の点が趣旨とされています。
- 軽微な事件の場合、被疑者に対し必要以上の精神的負担を感じさせないようにする(ダイバージョン)
- 検察官の事務処理能率の改善: 警察が扱うすべての事件を検察官に送致してしまうと、検察の処理能力を超えてしまい、刑事手続の円滑な運用が困難になります。そこで例外的な制度として、微罪処分が設けられています。
歴史的には、昭和25年7月20日付の検事総長から各地検の検事正あての通牒「送致手続の特例に関する件」より、各都道府県に対して「微罪処分取り扱いの基準」についての指示がなされています。
微罪処分の法的根拠(刑事訴訟法 第246条 但し書き)
微罪処分の法的根拠は、刑事訴訟法 第246条 ただし書きに基づいています。
| 法律・規範 | 条文 |
|---|---|
| 刑事訴訟法 第246条 | 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 |
| 犯罪捜査規範 第198条 (微罪処分ができる場合) |
捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。 |
| 犯罪捜査規範 第199条 (微罪処分の報告) |
前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を一月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第十九号)により検察官に報告しなければならない。 |
| 犯罪捜査規範 第200条 (微罪処分の際の処置) |
第百九十八条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。 一 被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。 二 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。 三 被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。 |
| 犯罪捜査規範 第201条 (犯罪事件処理簿) |
事件を送致し、又は送付したときは、長官が定める様式の犯罪事件処理簿により、その経過を明らかにしておかなければならない。 |
微罪処分と不起訴処分の決定的な違い
微罪処分と混同されやすい処分に「不起訴処分」がありますが、両者は根本的に異なります。
| 処分名 | 判断主体 | 手続の段階 | 前科・前歴 |
|---|---|---|---|
| 微罪処分 | 警察 (検察官が基準を指定) |
警察段階で終結 (検察官に送致されない) |
前科: 付かない 前歴: 付く |
| 不起訴処分 | 検察官 | 検察段階で終結 (警察から送致された後) |
前科: 付かない 前歴: 付く |
微罪処分の基準 – 誰が「微罪」を決めるのか
微罪処分は「検察官が指定した事件」について警察が行う例外的な処理ですが、その基準や判断主体について詳細を理解することは、処分獲得の可能性を探る上で重要です。
決定権限の所在 – 警察が実施し検察官が基準を定める
微罪処分を行うのは警察ですが、その基準を定めるのは検察官です。
基準策定 – 検察官(検事正)
警察官によって「何を微罪とするのか」が曖昧にならないよう、管轄地域内の検事正が微罪とする基準を策定しています。
処分実施 – 警察
警察は、明らかに起訴猶予相当(不起訴相当)と認められる事件に限り、送致を行わず微罪処分を実施します。
警察は微罪処分を実施した場合、その都度検察官に送致する代わりに、被疑者の氏名、罪名、犯罪事実の要旨などを「微罪処分事件報告書」に記載し、月報で管轄地域内の検事正に報告する運用を行っています。この報告を受けた検察官が、被疑者の取調べを行ったり、何らかの処分を下すことは予定されていません。
非公開の基準 – なぜ公表されないのか
微罪処分の基準は、地方検察庁ごとにその管轄区域内の警察に指定されており、全国一律ではありません。さらに、各地方検察庁が指定する条件は非公開です。
これは、どのような犯罪が微罪処分の対象となるかを明らかにしてしまうと、それを逆手に取ろうとする人が出たり、かえって微罪処分を狙った犯罪を引き起こすおそれがあるためです。
他方、微罪処分の立件裁量が警察にあることから、警察による「自転車やバイクの盗難事件のでっち上げ」などの不祥事がありました。ノルマや手続の簡便さから、かえって好んで拡大利用された可能性も指摘されています。
微罪処分と判断されるための主な6つの基準
基準は非公開ですが、過去の通達や運用から、概ね以下の点が微罪処分となるための重要なポイントとして挙げられています。
犯罪が比較的軽微であること
被害額は、概ね2万円までで、5,000円を超えていれば悪質と判断され、微罪処分にならない可能性が高くなります。
犯情が軽微であること(偶発性)
犯情とは犯罪の具体的な事情そのものを指します。犯罪の性質、動機、態様、被害者の状況や被害の程度などが含まれます。偶発的犯行であること、犯情が軽微であることが微罪処分手続書のチェック項目にあります。
被害者との示談成立・被害回復
被害の回復が行われているか。被害弁償や示談が成立していることが必須条件です。被害回復していること、被害額が僅少であることが微罪処分手続書のチェック項目にあります。
被害者の処罰感情が厳しくないこと
被害者が処罰を望んでいないか。他の基準を全て満たしていても、被害者の処罰感情が強い場合、微罪とは認められません。被害者が処罰を希望していないことが微罪処分手続書のチェック項目にあります。被害届が出ている場合は処罰感情が強いと見なされます。
素行不良者ではないこと(再犯のおそれがない)
素行不良でなく偶発的か。前科や前歴がある場合、原則として微罪処分は認められません。素行不良者でないこと、再犯のおそれがないこと、全共犯者とも再犯のおそれがないことが微罪処分手続書のチェック項目にあります。
監督者がいること
今後の生活を監督する者がいること。親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者など、身元引受人が必要となります。
微罪処分手続書と判断プロセス
事件が微罪処分となる場合、司法警察員(警察)は「微罪処分手続書」を作成します。
この微罪処分手続書には、被疑者の本籍・住居・職業ほか、犯罪事実の要旨、犯歴などの記述・チェック項目が設けられており、微罪処分を検討するにあたっての観点がまとめられています。
チェックされる項目には、以下のようなものが含まれます。
微罪処分手続書の主なチェック項目
| 項目 | 記述・チェック項目 |
|---|---|
| 被疑者 | 本籍 住居 職業 氏名 生年月日 |
| 発覚の端緒 犯罪事実の要旨 犯行の動機 |
(記述欄) |
| 微罪処分の検討事項(1) – 被疑者 | 成人である。 前科・前歴はない。 素行不良者ではない。 公務員ではない。 |
| 微罪処分の検討事項(2) – 罪名 | 窃盗 詐欺 横領 盗品等 賭博 暴行 |
| 微罪処分の検討事項(2) – 条件 | 被害額はわずかである。 犯情は軽微である。 偶発的犯行である。 再犯のおそれはない。 盗品等の返還又は損害賠償がなされている 被害者が処罰を希望しない。(賭博の場合) 賭けた金品はわずかである。 共犯者のすべてが再犯のおそれがない初犯者である。(暴行の場合) 犯罪者宥恕 凶器未使用である。 |
| 微罪処分の検討事項(3) – その他 | 告訴・告発・自首事件ではない。 通常逮捕・緊急逮捕した事件ではない。 |
| 処分に伴う処置 | 被疑者に対し厳重に訓戒を加え将来を戒めた。 親その他の監督者又はこれに代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき注意を与え請書を徹した。 被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な措置を講じさせた。 |
このように微罪処分を検討するにあたって、いくつかのチェック項目が存在します。また、「被害者供述書」もあり、被害者側の供述や事情を記載します。微罪処分手続書のチェック項目による確認と、被害者供述書による処罰意思なしの確認によって微罪処分が決まります。
微罪処分の対象となりやすい事件と対象外の事件
微罪処分の対象となる犯罪は都道府県によって異なりますが、統計的には軽微な財産犯や暴行罪が多くを占めます。
微罪処分の対象となる主な罪名
微罪処分の対象とされている事件は、被害が僅少で、犯情軽微、被害回復が行われ、被害者が処罰を希望せず、再犯のおそれがない偶発的犯行であるものに限定されます。多くの場合、以下の罪名が対象に含まれます。
窃盗罪(万引き、自転車盗など)
例: スーパーやデパートでの少額商品(食材、化粧品類)の万引き。被害額は「おおむね2万円まで」が軽微とされますが、万引きの場合は5,000円を超えると難しくなる傾向があります。
暴行罪
暴行罪の微罪処分では、通常の基準に加え「凶器の不使用」がポイントとなっています。
例: 被害者と口論の末に肩を押して転倒させたものの軽傷で、治療費や慰謝料を支払い示談が成立したケース。また、酔った勢いで相手に接触したようなケースも、偶発的な行為として扱われることが多いです。
横領罪・詐欺罪
例: 「食い逃げ」のような単純な犯行であれば微罪処分となる可能性はありますが、手口が巧妙であったり、組織的に行われた犯行についてはその可能性はないと考えられます。
占有離脱物横領(遺失物横領)
例: 放置されていた自転車に乗り警察官に呼び止められたものの、本人が深く反省しており持ち主も処罰を望んでいないケース。
賭博罪
単なる客として偶発的に賭博に関与してしまった場合や、掛け金が少額であったり、一時的な娯楽の範疇に留まる場合など。
令和5年においては、全検挙人員に対する微罪処分の比率は「26.4%」と、約4分の1の事件が微罪処分となっています。
微罪処分の対象外となる主な犯罪・事案
軽微な犯罪であっても、以下のようなケースでは微罪処分の対象にはなりません。
告訴・告発・自首がある事件
被害者による告訴や告発、または被疑者自身が警察に出頭して自首した事件については、微罪処分の対象にはなりません。
性犯罪
痴漢や盗撮、不同意わいせつ等、不同意性交等の性犯罪は、微罪処分の対象にはなりません。性犯罪は検察官送致されることがほぼ確定しています。
計画的・組織的な犯行
衝動的ではなく、計画的な犯行や組織的な犯行の場合、犯情が重いと判断され、微罪処分になる可能性は低くなります。
強制捜査された事件
逮捕状(令状)を基に逮捕された事件や、強制捜査が行われた事件については、微罪処分の対象とはなりません。通常逮捕や緊急逮捕の場合には微罪処分を受けることはありません。
前科・前歴がある場合
原則として、前科・前歴がある場合、微罪処分は認められません。
外国人被疑者
外国人被疑者の場合、入管法違反等がある場合は、原則送致する運用となっています。また、入管法違反等ある場合、対象事件のみを微罪処分とすることはできません。
被害甚大または処罰感情が強い場合
被害が甚大で被害者の処罰感情が強い場合、微罪とは認められません。
微罪処分になった場合の流れとメリット
微罪処分が適用された場合、被疑者は迅速に刑事手続から解放され、大きなメリットを享受できます。
微罪処分となる場合の手続の流れ
微罪処分となる場合、警察段階で事件が終結します。代表的な流れは以下の通りです。
警察署での取調べ
何らかの犯罪の疑いをかけられているため、初めに警察署で事情聴取や取調べが行われます。この際、警察は「微罪処分手続書」や「被害者供述書」を作成します。
厳重な訓戒
微罪処分となる際には、被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒める処置がとられます(犯罪捜査規範第200条一)。
身元引受人を呼ぶ
微罪処分となるためには、監督者(身元引受人)が必要です。親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者、またはこれらに代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書(身元引受書)を徴します。
被害回復の諭し
被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭されます(犯罪捜査規範第200条三)。
釈放される
上記の手続がすべて終了した時点で身柄が釈放され、事件は終了します。
微罪処分は、逮捕や送検という大掛かりな手続を取らずに済むため、通常の手続で処理される場合に比べて早期に刑事手続から解放されます。
微罪処分がもたらす最大のメリット
微罪処分を獲得することは、被疑者にとって非常に大きなメリットがあります。
前科がつかない
微罪処分は警察段階で事件が終了するため、検察官に起訴されることが確定的に回避されます。起訴する権限を持っているのは検察官のみ(起訴独占主義)であり、起訴されない以上、刑事裁判を受けることもないため、前科はつきません。前科が付くと、履歴書の賞罰欄への記載義務が生じたり、国家公務員、地方公務員、警備員、建築士など一部職業の制限を受けたり、海外旅行の制限を受けることがあるなど、社会生活に多大な影響が生じるリスクを回避できます。
懲役や罰金などの刑罰を受けずに済む
微罪処分は、裁判を受ける必要がないため、懲役刑や罰金刑、拘留・科料といった刑事罰を受けることなく事件を終了できます。微罪処分は、いわゆる「厳重注意」で済むため、今後の影響も最小限に抑えられる点が大きなメリットです。
微罪処分をめぐる注意点と日常生活への影響
微罪処分は大きなメリットをもたらしますが、犯罪行為の記録は残り、いくつかの注意点が存在します。
前科は回避できても「前歴」は残る
微罪処分を受けたとしても、前歴は付きます。前歴とは、警察/検察官により逮捕された場合や検挙されて犯罪捜査を受けたときに付く「被疑者として捜査の対象になった履歴」を指します。
前歴は捜査機関のデータベース(前歴簿)に記録が残り、一生消えることはありません。
前歴の影響
前歴が付いたとしても、この記録が公開されることはなく、日常生活を送るうえで何らかの制約を受けることはありません。
再犯時の影響
しかし、将来的に類似の犯罪行為を起こした場合、過去の捜査記録(前歴)を参照されることで不利な扱いを受け、処分が重くなる可能性が高いです。また、原則として前科・前歴がある場合、2回目以降の微罪処分は認められる可能性が極めて低いと考えられます。
民事責任は消えない
微罪処分は刑事責任(刑罰)に関する処分であり、民事上の責任は消えません。
罪を犯した場合、刑事責任と民事上の責任を負います。微罪処分によって刑事責任は終結しますが、被害弁済や賠償金等、不法行為によって発生した損害に対する民事責任は残ります。例えば窃盗罪であれば、盗んだ物品相当額の返済や、それに伴って発生した損害の補填等を民事上の責任として負わなければなりません。
身元引受人への情報開示
微罪処分を受けるためには、被疑者の再犯防止を監督する身元引受人(監督者)の必要性が高いです。
身元引受人には、親権者、雇主、その他被疑者を監督する地位にある者が該当し、通常は家族が選ばれます。身元引受人には警察署まで来てもらう必要があるため、家族や上司に事件を起こしたことが知られてしまうというデメリットがあります。
ただし、これは微罪処分に限ったデメリットではなく、通常の在宅事件として捜査される場合でも身元引受人が必要となるため、周囲に事件が知られる可能性はあります。
民事訴訟への影響
微罪処分を受ける際は、罪を認め、反省を示すことが前提となります。
しかし、もし被疑者が「正当防衛」のように犯罪事実自体を争うべき事情があったにもかかわらず、微罪処分という不利益の少ない結末を優先して「反省しています」という調書にサインした場合、後日、被害者から民事訴訟を起こされた際に、その調書が不利な証拠として使われるリスクがあります。微罪処分は「犯罪の事実はあった」ということが前提の処分になるためです。
一度なされた微罪処分は取消ができません。正当防衛などを主張する可能性がある事案では、微罪処分ではなく「嫌疑不十分を理由とする不起訴」を狙うなど、慎重な対応が必要です。
微罪処分獲得のための対策と弁護士の役割
微罪処分を獲得するためには、警察の判断基準を満たすよう、迅速かつ適切な行動を取ることが不可欠です。
微罪処分を目指すために被疑者側がすべきこと
反省の意を明確に示すこと
事件を認め、反省していることは微罪処分の前提です。反省していない態度を示すと、再犯のおそれがあると疑われるだけでなく、被害者の処罰感情も高まる可能性があります。深く反省し、二度と罪を犯さないと誓う姿勢が大切です。
被害弁償と示談交渉を速やかに行うこと
微罪処分を受けるための最も重要な要素の一つが、被害者との示談の成立です。
被害者の処罰感情の有無は、微罪処分を考えるにあたって非常に重要であり、示談が成立すれば「示談金の支払い」という形で被害が回復されたといえます。被害者の処罰感情が和らぐことで、微罪処分となる可能性が高まります。
特に示談書に「許す」(宥恕条項)や「刑事処罰を求めない」という文言を入れてもらうことができれば、被害者が処罰感情を持っていないことを警察に納得してもらう上で効果が高くなります。
監督者の確保
監督者(身元引受人)を確保し、警察に対し、今後の生活を監督し再犯防止に努める旨を請書として提出することが必要です。
示談交渉における弁護士の役割
軽微な犯罪であっても、被害者との示談交渉は加害者本人やその家族が行うべきではありません。円滑な示談成立のためには、刑事事件に強い弁護士を選任することが重要です。
被害者との接触リスク回避
加害者本人や家族が被害者に示談を申し入れても、必ずしも受け入れられるものではありません。かえって被害者の不信感を招き、交渉の決裂や、「脅迫や口止め」と受け取られたり、被害者の処罰感情を再燃させてしまうリスクがあります。また、事件によっては、被害者が加害者との接触を拒む事態も考えられます。
弁護士は、加害者に代わって交渉を担い、冷静かつ適切な手段で話し合いを進めます。弁護士が間に入ることで被害者に安心感を与え、対話がスムーズに進みやすくなります。
適切な賠償額の算定と交渉
弁護士は、法律に基づく適切な賠償額(治療費、慰謝料、弁償など)の算定や、示談書の作成を行います。当事者同士の交渉では、被害者が法外と思えるような金銭の支払いを求めてくる事態も考えられ、トラブルの再発を防ぐためにも弁護士に任せるのが望ましいです。
早期解決と有利な処分への働きかけ
弁護士が示談交渉を行い、その成果(示談成立の事実)を警察や検察官に伝えることで、微罪処分や不起訴処分、あるいは寛大な処分を引き出す可能性が高まります。弁護士は、再犯のおそれがないことや、普段の素行に問題がないことなどを捜査機関に説明し、微罪処分になるよう働きかけを行うことが可能です。
刑事事件は「スピードが命」- 初動の重要性
微罪処分の可能性がある場合であっても、「微罪かどうか」と一人で悩むより、まずは弁護士に相談し、正しい知見から状況を判断し、示談の必要性を含めた早期対策を立てることが推奨されます。
弁護士は、微罪処分を受けられる状況であるかを予測し、必要な対応を迅速にとることが可能です。万が一、微罪処分とならなかった場合でも早めに弁護士に相談することで、その後の送致段階や検察段階での対応が変わってきます。
まとめ – 微罪処分の可能性があっても油断せず、早期に弁護士へ相談を
微罪処分とは、犯した罪が軽微である場合に、検察官に送致せず警察限りで事件を処理する手続であり、前科を回避し、早期に日常生活へ復帰できるという被疑者にとって大きなメリットをもたらします。
令和5年では全検挙人員の約4分の1が微罪処分となっています。
しかし、微罪処分が下されるかどうかは、被害の軽微性、犯情の偶発性、被害者の処罰感情の有無や示談の状況、そして被疑者の前歴や反省の度合いなど、総合的な要素を踏まえて警察の裁量で判断されます。自分自身で「微罪」だと思っても、必ず適用されるわけではありません。
「微罪とは言え、前歴の付いてしまう歴とした犯罪」であり、軽微な犯罪であっても油断して対策を怠ると、想定外に厳しい処分を招くリスクがあります。例えば、クレプトマニア(窃盗症)のような精神的な問題が背景にある場合、微罪処分で安心して専門家への相談機会を逃してしまうと、再犯に陥り今度は前科が付いてしまうという不幸な結果になることもあり得ます。
微罪処分を目指す場合でも、万が一送検されてしまった場合(不起訴を目指す場合)でも、被害者との円満な示談成立は、処分の軽重を左右する最も重要なポイントです。
刑事事件は初動が肝心です。身近な人に相談できない問題だからこそ、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、不安やリスクを正確に把握した上で、適切な早期対策を講じることが、明るい未来を取り戻すための鍵となります。
補足 – 微罪処分と再犯のリスク
微罪処分を受けたとしても、前歴は残ります。原則として、前科・前歴がある場合、2回目以降の微罪処分は認められる可能性がかなり低いといえます。
特に、常習性が高いとされる万引きなどの犯罪では、検挙時点で多数の余罪があることも考えられます。多数の余罪がある場合には、被害が軽微である等の微罪処分の要件に当てはまりにくくなります。
「万引きを繰り返してしまう」など、犯罪衝動と罪悪感の悪循環に陥っている場合、専門医による治療が必要となるケースもあり、弁護士と専門クリニックが連携することで、更生への環境づくりや再犯回避の第一歩が踏み出し易くなります。