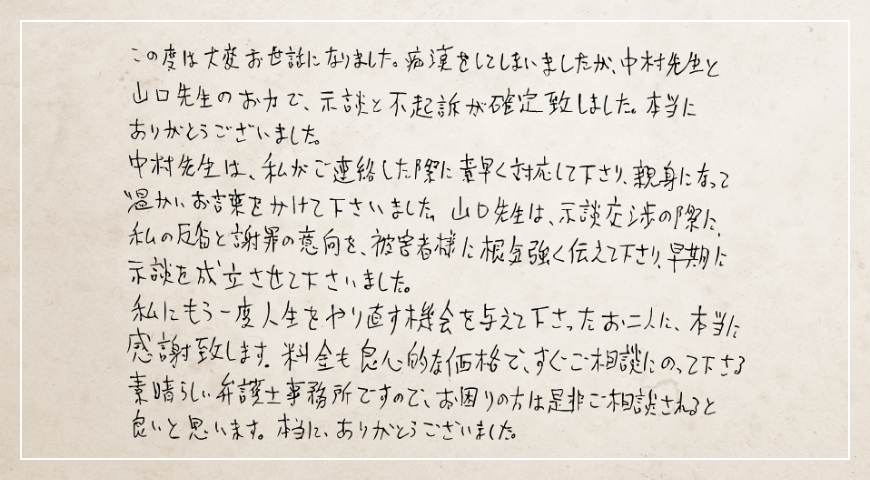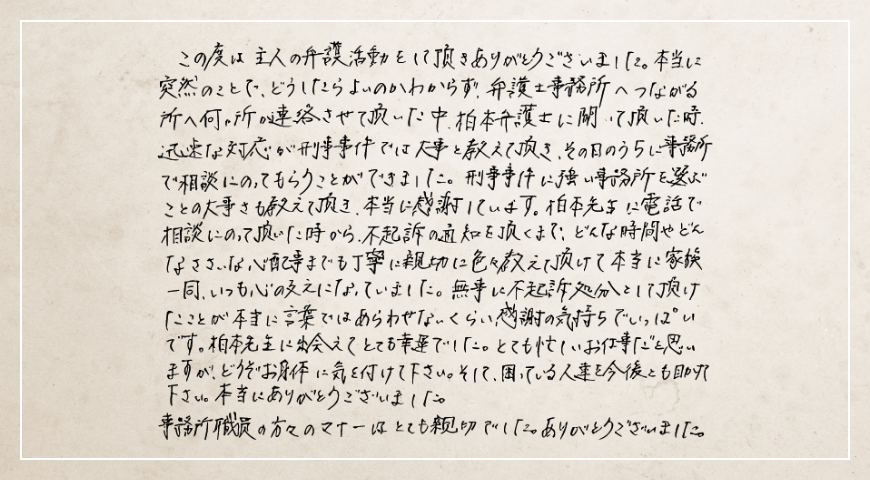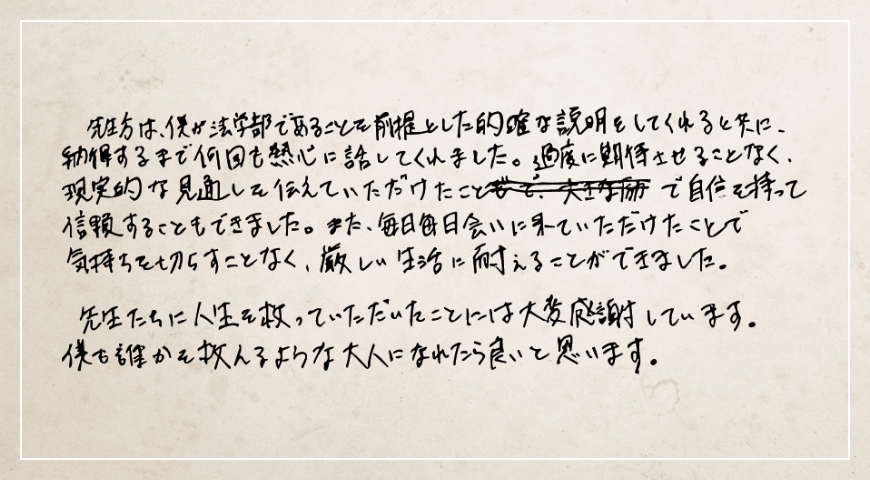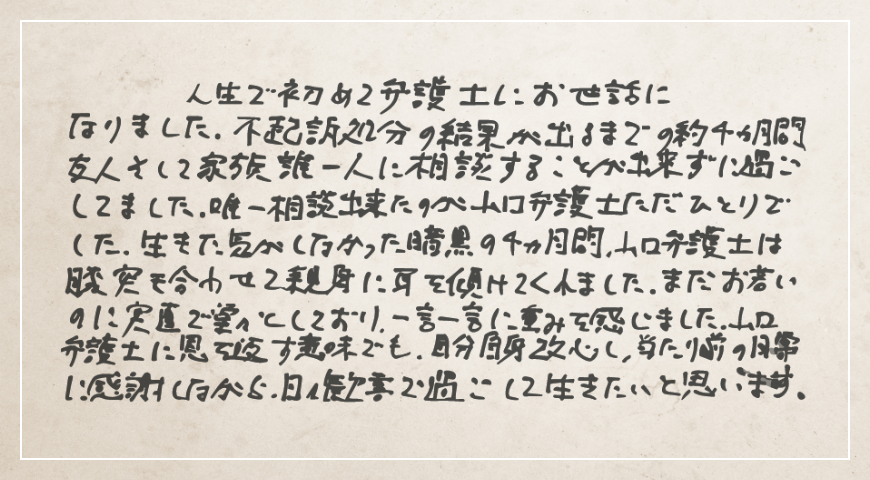豊富な経験から最善の方針を導き出し不処分獲得
大学のサークルで行われた合宿中、後輩の女子学生にわいせつな行為を行ったとして逮捕された強制わいせつ事件です。少年に非行歴はありませんでした。
逮捕当時、大学が夏季休暇中であったため、すぐに釈放されれば、少年は大学側に知られることなく復帰できると考え、付添人(弁護人)は早期釈放を目指すこととしました。
初回接見から勾留請求まで
初回接見時、付添人が少年の話を聞くと、逮捕事実の客観的部分は概ね間違いないようでしたが、被害者の同意があった旨を主張したので、少年の主張を前提として、検察官にどのように説明をしたら良いかを少年に助言しました。もし少年が嘘をついているのであれば翻意して欲しいとの思いから、否認した場合には拘束期間が長くなる可能性が高いことも付け加えて説明しました。
初回接見の翌日、検察官に勾留請求の可否を尋ねたところ、検察官の回答は予想通り勾留請求するというものでしたが、少年は検察官の前でも被害者が同意していたとの主張を繰り返していたとのことで、付添人は少年が被害者の同意に拘ることが気がかりでした。
2回目の接見から目撃者の事情聴取まで
2回目の接見の際、少年に「被害者の同意を裏付ける証拠があれば教えてほしい」と尋ねたところ、少年が目撃者の存在を告白しました。サークルの先輩が犯行現場とされる部屋にいて、少年と被害者の様子を見ていたというのです。
目撃者の連絡先がわかるとすぐに連絡をとり話を聞いたところ、被害者が少年を挑発するようなことを言ったことや、目撃者が部屋から出ていくときに、被害者が助けを求めなかったことが、具体的かつ詳細に述べられました。
また、被害者が今までにも飲み会で男性に絡むことが多かったことや、事件前日に被害者が少年の上にまたがり胸を揉ませようとしたことなどの話を聞くことができました。
付添人はこれらの供述をもとに供述調書を作成しました。
検察官に対する意見書提出から観護措置決定まで
検察官に対して、目撃者の供述調書を添付資料とした家裁不送致を求める意見書を提出し、電話でも直接伝え少年の無実を訴えましたが、「サークル関係者の話は信じられない」と切り捨てられてしまいました。
裁判官に対して観護措置の回避を求める意見書を提出したうえで、裁判官と面接し少年が無実であることを訴えましたが、あっさりと観護措置決定が下されました。
この時点で、大学からは無期限停学処分が少年に対して出されました。退学処分に付される方向でしたが、付添人の尽力により、退学は免れることとなりました。
裁判官との打ち合わせ
裁判所から事件記録閲覧の許可が下りたので、記録を閲覧したところ、唯一こちら側の証拠で足りなかった女子トイレでの少年の様子について、新たな目撃者がいたことがわかりました。急いで連絡をとったところ、少年が女子トイレで被害者を介抱していたこと、少年が介抱している最中にも被害者が抵抗している様子もなく、仲良さげに肩を組み、寝室へ向かったことを話してくれました。
翌日、裁判官と打ち合わせを行い、被害者と目撃者2人の証人尋問が不可欠であることを訴えると、裁判官は、非行事実を否定するとして、どの点を争うか尋ねてきたので、少年の主張に沿って、主位的に被害者の同意が存在した点、副位的に強制わいせつの故意の不存在を主張したいと話しました。
裁判官は、「もし、被害者の同意が存在したとして争うのであれば、被害者を証人として呼ばなければいけなくなり、日数がかかるので少年が鑑別所にいる期間が長引いてしまう可能性が高いうえ、被害者に対して精神的なストレスを与えることになって、ひいては少年が釈放された後にまたトラブルを生じさせる恐れも出る。ここは、強制わいせつの故意の不存在のみを争点とするわけにはいかないだろうか。そして、少年に対してのみ、事件当時の認識や客観的な状況を聞くという形ではできないだろうか。」と提案しました。
裁判官が事件記録を見たうえで、一定の理解を示してくれたこと、少年に対する配慮が感じられたこと、さらに、裁判官は故意無しとの心証なのではないかと感じとられたことから、付添人は裁判官の提案に従うことにしました。
審判準備
付添人と少年は、審判期日までに、非行事実に関する少年への質問に対する練習を重ねました。
そして、審判が行われる前日には、こちら側の主張をまとめた意見書を裁判所に提出しました。その意見書では、少年の言い分を時系列に沿って具体的に書いたうえで、被害者の主張の矛盾点を、目撃者の供述を挙げながら指摘しました。
結果
結果として、非行事実なしを理由とした不処分決定を獲得しました。
裁判官は、サークルの人間の供述に信用性があることを認め、被害者の同意があった可能性にも含みを持たせるような事実認定を行い、そのような客観的状況であれば、少年が被害者の同意があると思っていたことはやむを得ず、強制わいせつの故意はない旨を認定しました。
なお、大学側に本決定を伝えたことで、1か月を待たずにに大学への復帰が可能となり、欠席扱いにならないような寛大な措置も取られました。
事件のポイント
本件は当事務所らしい理想的な解決を実現した事例で、付添人としてはギリギリの判断が求められる難しい事例でした。王道は目撃者の証人尋問請求でしょう。10人弁護士がいれば9人はそのような方針を立てると思われます。
ポイントは裁判官面接です。裁判官の心証をしっかりとることが必須の事件です。ただ単に裁判官面接をすればいいというものではありません。裁判官は決して付添人に処分結果を事前に知らせることはありません。そのような条件下で裁判官の心証をしっかりと受け止めるには普段からあらゆる事件で裁判官面接を何十回も経験していなければならないのです。検事面接もそうです。
本件は情報戦と言っていい刑事弁護にあって、裁判官面接を通じた心証から拘束期間を可能な限り短く、かつ、最良の結果を導き出した高度な付添人活動であったと思います。
執筆者: 代表弁護士 中村勉