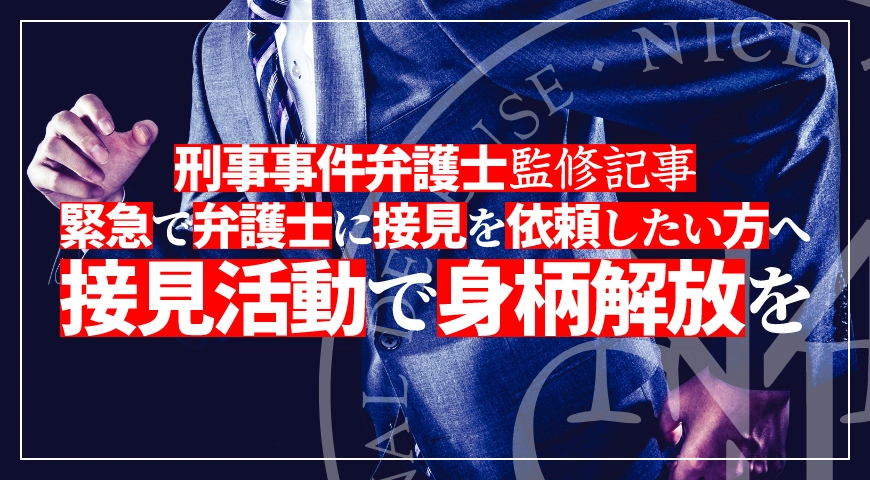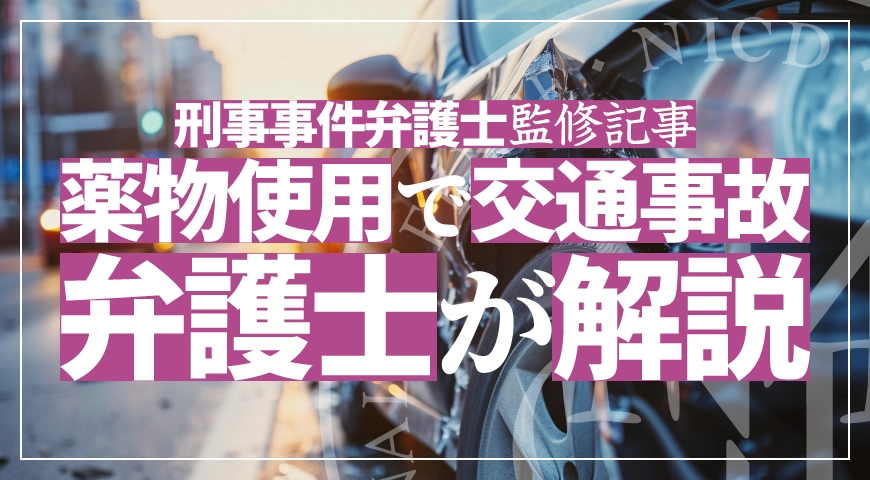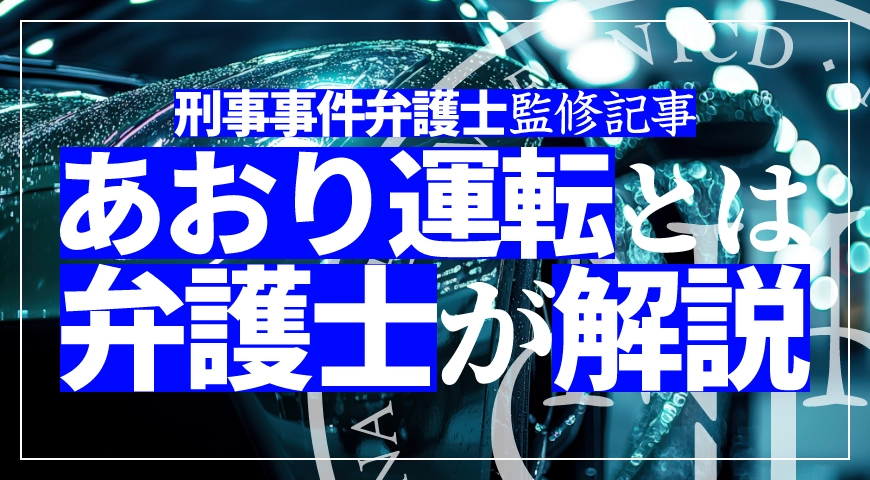「事件」という言葉を耳にすると、犯罪にかかわるものを想像される方が多いかもしれません。しかし、法律家が扱う「事件」には、一般的に、刑事事件と民事事件があり、これらは別個独立に手続が進んでいきます。
実は、犯罪によっては、刑事事件の側面のみならず、民事事件の側面もあります。まずは、刑事事件と民事事件の違いから代表弁護士・中村勉が解説していきます。
刑事事件とは
刑事事件とは、犯罪行為を行ったと疑われる一般市民の犯罪行為の有無を証拠から判断し、刑罰を科すか否か、科すとしてどのような重さの刑を科すかを決めるものです。
刑事事件の流れは、一般的に以下のとおりです。
- 警察や検察等の捜査機関が、犯罪を行ったと疑われる一般市民(被疑者)を捜査します。この際、必要に応じて被疑者は逮捕・勾留されます。
- 検察官において、上記被疑者が犯罪を行ったことを証明するのに十分な証拠があり、かつ、上記被疑者を起訴すべきと考えた場合、検察官は被疑者を起訴します(この時点で被疑者は「被告人」となります)。この際、勾留されていた被疑者(被告人)は、保釈が認められない限り、判決の時まで勾留が続きます。
- 裁判所において、事件の審理が行われます。
- 裁判所が判決を言い渡します。判決では、無罪の場合は「無罪」、有罪の場合には刑罰が言い渡されます。
このように見ていただくとお気付きいただけるかと思いますが、刑事事件(刑事手続)の目的はあくまでも、犯罪を犯した人を適切に取り締まり、刑罰を科すことにあります。刑罰を科す以外に、被害者に対する損害賠償を命じることは後述する損害賠償命令制度による場合以外にはありません。
刑事事件の当事者
刑事事件における当事者は、犯罪を行ったと疑われる一般市民(被疑者・被告人)と犯罪を捜査し起訴、不起訴の判断を行う検察官です。日本において、起訴をする権限(刑事裁判を提起する権限)は検察官のみ有しており(刑事訴訟法第247条)、犯罪の被害者には被疑者を起訴する権限がないことに注意が必要です。
もっとも、被害者の処罰感情等は検察官による起訴・不起訴の判断でしたり、裁判官による刑の判断において考慮されますので、刑事事件の手続きにおいて被害者のことが無視されるわけでは決してありません。
刑事訴訟法第247条 公訴は、検察官がこれを行う。
その他、刑事事件においては裁判官や弁護士も重要な役割を担います。
裁判官は被告人が有罪か無罪か、有罪の場合に、どのくらいの刑に処するかを法律の範囲内で決めます。まだ裁判となっていない捜査段階では、捜査機関に対して逮捕状や捜索差押許可状の各種令状を発付するかどうか、検察官による勾留請求に基づき勾留を決定するかどうか、弁護人による準抗告の申立てを認容するか棄却するか等を判断します。
弁護士は、法に精通していない被疑者・被告人をサポートするため、「弁護人」として被疑者・被告人側につき、被疑者・被告人にアドバイスをしたり、検察官や裁判官とやりとりをしたりします。また、被害者のいる事案では、弁護活動の一環として、弁護人が被疑者・被告人の代わりに被害者に対して示談や被害弁償の話を打診します。刑事事件における弁護人による示談活動の重要性は後述します。
民事事件とは
民事事件は、私法上のトラブルに関する事件で、主に権利の保護、被害の回復等を目的とするものです。
刑事事件と異なり、相手方に対する処罰ないし制裁を目的とするものではありません(この点、米国等では懲罰的損害賠償制度といって、実際の損害とは別に、相手方に制裁を加えるための高額な損害賠償を認める制度があります。これは実質的に民事事件においても相手方に対する制裁という考え方を認めるものですが、日本にはこのような制度はありません)。
また、民事事件は、裁判所を巻き込まずに終わるものや、裁判所に訴訟を提起しても、裁判所による判決を待たずして、訴訟の途中で当事者間の合意による和解で終わるものが多くあります。これに対し、刑事事件においては、一度公訴提起されると、公訴が取り下げられることは滅多になく、判決をもって終結します。
民事事件における当事者
民事事件における当事者は、通常、私人同士です。ここにいう私人には、一般市民や団体、企業などが含まれます。国や地方公共団体なども当事者となることがありますが、この場合も、あくまでも争っているのは私法上の権利などです。
民事事件は必ずしも法律家の介入は必要とされませんが、多くの事件で、弁護人が各当事者の代理人となって活動しています。
刑事事件と同様、裁判の場面になると、弁護士に加え裁判官もかかわってきますが、基本的に検察官が登場することはありません。
刑事事件が終結してから民事事件が提起されることも
被害者がいる犯罪をめぐっては、刑事事件のみならず、民事事件も別途進行する可能性があります。
なぜなら、犯罪は民法第709条の定める不法行為に該当しますので、被害者は加害者に対して、犯罪によって生じた損害の賠償を請求する権利があるからです。精神的苦痛のように財産以外の損害についても賠償請求することができます(民法第710条)。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
したがって、刑事事件で刑罰を受けたとしても、加害者は、なお被害者から民事的に損害賠償請求をされ、場合によっては民事訴訟を提起される可能性があります。
なお、刑罰の中には、罰金というお金を納付する刑がありますが、これはあくまでも国に対して納付されるものであり、罰金が納付されても、被害者には何らお金が入りません。被害者はなお、民事的に損害賠償請求をする権利を有していますので、罰金納付後に被害者から別途損害賠償請求されると、加害者は二重に出費することとなります。
冒頭で述べたとおり、民事事件と刑事事件とは別個独立して手続が進みますので、刑事事件について略式罰金命令や判決が出ていない状態であっても、被害者は別途民事事件として加害者に対して損害賠償請求をすることができ、民事裁判を提起することも可能です。もっとも、証拠による厳格な事実認定が求められる刑事裁判で有罪の判断がされれば、その事実をもって民事裁判においても、被告(加害者)による不法行為があったと認定されやすくなるため、被害者側としてはどちらかというと刑事事件の終結を待って民事裁判を提起することを考える方が多いでしょう。
なお、殺人や傷害致死、強制わいせつ、強制性交等の一部の重大犯罪については、損害賠償命令制度というものが設けられています(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第23条以下)。この制度は、刑事裁判を担当した裁判官が、刑事裁判で使われた記録を利用して、原則4回以内の審理で賠償金額を決定し、被告に対して損害賠償命令を下す制度です。これはまさに上記の考え方を取り入れつつ、被害者の別途の民事訴訟提起の負担を軽減するものといえます。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第23条(損害賠償命令の申立て)
次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者又はその一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。
一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪
二 次に掲げる罪又はその未遂罪
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等)の罪
ロ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪
ハ 刑法第二百二十四条から第二百二十七条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等)の罪
ニ イからハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く。)
2 損害賠償命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び刑事被告事件に係る訴因として特定された事実その他請求を特定するに足りる事実
3 前項の書面には、同項各号に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項以外の事項を記載してはならない。
刑事事件と民事事件になりうる事例
先述したとおり、被害者のいる犯罪はいずれも刑事事件と民事事件になり得ますが、中でも、以下の事例は刑事事件と民事事件が別個独立して進行するケースが見られるものになります。
交通事故
交通事故における加害者は、特に人身事故ですと、道路交通法違反や過失運転致死傷といった犯罪に問われ刑事事件として扱われることが多いです。
また、交通事故により被害者が入院・通院した場合には、加害者は、実際にかかった治療費や入院費、入院慰謝料・通院慰謝料等の損害賠償を被害者から別途民事事件で求められることになります。後者は加害者が保険に入っている場合には、基本的に被害者が保険会社に対して請求することになりますので、そういった意味でも、刑事事件とは切り分けて民事事件が進行しやすい傾向にあります。
企業相手の巨額の詐欺・業務上横領事件
多くの企業には顧問弁護士がいます。処罰感情が強いからこそ、顧問弁護士に頼んで刑事告訴をしてもらっているケースが多く、企業側には示談に応じる意思がないことが多いです。そのため、加害者は刑事事件とは別個独立して民事的な請求がされる傾向にあり、場合によっては民事訴訟を提起されることがあります。
刑事事件における示談の重要性
犯罪行為を行い、刑事事件としては終結したものの、いつ民事事件として当該犯罪行為が呼び起こされるかが分からない、そんな心理的負担を軽減する役割を担うのが「示談」です。
刑事事件における弁護活動の一環として行われる示談においては、被疑者/被告人が当該犯罪行為によって被害者に生じた一切の損害の賠償として一定金額の示談金を支払う代わりに、被害者においては被疑者/被告人の刑事処罰は求めないという約束をしてもらい、さらに、当該示談において定めるもののほかには被疑者/被告人と被害者との間に債権債務関係がないことを相互に確認する清算条項をおくのが通例です。したがって、被害者は示談金以上の額を示談後に請求することは基本的にできません。仮に示談後に被害者が示談金以上の額を請求する民事訴訟を提起してきたとしても、被疑者/被告人側は、当該示談の際の示談書を証拠として出せば被害者の請求は認められないでしょう。
そのため、刑事事件の中で示談が成立すれば、民事事件の側面も一挙に解決したことになります。
逆に、刑事事件の中で示談が成立しないと、刑事事件が終結した後も、被害者から別途民事訴訟を提起される可能性が残ります。ですので、単に「罰金を払えばいいや」では済まない可能性があるのです。
特に痴漢や盗撮、暴行や傷害等の事例では、示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高く、被害者に対する示談金の支出はあるものの、罰金は払わないで済む可能性が高くなります。それにもかかわらず、罰金を払えばいい、との考えで被害者との示談交渉をせずに略式罰金に服すると、後に被害者から民事訴訟等で損害賠償請求をされた場合に、国に対する罰金に加えて、被害者に対する損害賠償金も支払わなければならなくなり、示談が成立した時の場合と比べて、金銭的支出が多くなってしまいます。
つまるところ、刑事事件における示談は、前科回避等の刑事的な側面からの目的以外にも、民事事件の側面も一挙に解決し、事件全体としての心理的、経済的負担を軽減する重要な役割をも有するのです。
したがって、被害者のいる犯罪で刑事事件の被疑者/被告人となっている方は、刑事事件が続いている間に被害者との示談をできる限り試みるべきです。示談による不起訴の可能性を考えると、早期に弁護士に依頼し、捜査段階で示談を成立させるのが一番望ましいですが、仮にそれができなかった場合であっても、公判段階においても示談を試みるのがよいでしょう。示談の成否は量刑にも影響しうるからです。
示談をめぐる被害者側のメリット
上述のとおり、被疑者/被告人の立場からすると、刑事事件における示談は、刑事的側面のみならず、民事的側面でも重要な意味を有するものであり、被疑者/被告人には大きなメリットとなります。
もっとも、被害者にも相当のメリットがないと、特に処罰感情の強い被害者には示談に応じてもらえないでしょう。被害者にはどのようなメリットがあるのでしょうか。被害者が示談に応じるメリットとしては以下のような点が挙げられます。
民事訴訟を提起しなくても一定の額の損害賠償を受けることができる
被害者が加害者に対して、民事上の請求をしても、任意に支払ってもらえなければ、民事訴訟を提起する必要が出てきます。
民事訴訟を提起するのに弁護士は必ずしも必要ではありませんが、現実的には弁護士なしできちんとした訴訟活動をすることは非常に困難です。そうすると、弁護士を雇うことになってきますが、その場合、弁護士費用は被害者自身が負担しなければなりません(加害者による犯罪という不法行為に基づいて発生した損害として、このような弁護士費用も損害として一部認められますが、その額は弁護士費用以外の損害として認定された額の10%にとどまります)。
強制性交等致傷などの事案で、民事裁判の場でもそれなりに大きな損害賠償額が認められる事案であれば、弁護士費用の負担はそれほど心配する必要はないかもしれませんが、痴漢や盗撮等のケースですと、民事裁判の場においてはそれほど大きな賠償額は認められず、むしろ示談金額として提示された金額の方が大きい可能性があるため、後に民事訴訟で損害を回収しようとすると赤字になってしまう可能性があります。
民事訴訟を提起することについては、弁護士費用の問題以外にも、判決までに時間がかかるという問題もあります。そのような観点からも、できる限り早く事件のことを忘れたい被害者にとっては、刑事事件の中で民事的な損害賠償を受けることにメリットがあるといえるでしょう。
民事訴訟の場合、請求額の回収が期待できないが、示談の場合はほとんどのケースにおいて約束された示談金額を確実に支払ってもらえる
民事訴訟の場合、判決で請求額が認められても、その額を相手方に支払ってもらえる保証はありません。訴訟に先立ち別途民事保全手続をとったり、判決後に民事執行手続をとったりする必要があります。
他方で、刑事事件における示談の場合には、ほとんどのケースで、その交渉を加害者に代わって行う弁護士において、示談成立時にすぐ示談金を被害者にお支払いできるよう、加害者から示談金原資を預かっているものと思われます。また、示談書を交わしていても、実際に示談金が支払われていなければ、検察官に不起訴の判断をしてもらうための材料としては不十分です。したがって、約束された示談金額については確実に支払ってもらえると期待できるでしょう。
民事訴訟を別途提起しても、加害者に資力がなければ請求額を回収できないが、刑事事件における示談の場合は、加害者に資力がない場合にも約束された示談金額を受け取ることができる可能性が高い
不法行為たる犯罪を起こしたのは加害者ですので、それに基づく損害賠償責任を負うのは加害者本人のみです。加害者本人に資力がなければ、仮に加害者の家族に資力があっても、加害者家族に支払いを強制することはできませんので、民事訴訟を提起しても無意味になってしまいます。
しかしながら、刑事事件における示談の場合には、加害者本人に資力がなくても、家族である加害者に前科がつくのをできる限り避けたい、加害者が執行猶予付き判決を得られる可能性をできる限り高くしたいと考える加害者の家族が示談金を支出してくれることがあります。また、そのような親族がいなくても、同様に考える加害者自身が他者から借入れをするなどの努力をして示談金を捻出することがあります。つまり、刑事事件においては、加害者に示談金捻出のためのインセンティブがある分、被害者も示談金額の支払いを期待できるのです。
比較的重大な事件において、処罰感情の強い被害者が、捜査段階では示談に応じなくても、公判段階では応じることがそれなりにあるのは、この資力関係の観点から、別途の民事訴訟提起による債権回収に難があることが多いからだと思われます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。刑事事件と民事事件の手続は別個独立に進むことや、刑事事件における示談有する効果をきちんと理解していなければ、不利益を被ってしまいかねません。
刑事事件での示談は以上のとおり、とても重要な役割を有していますので、刑事事件を多く扱っている弁護に依頼するのがよいでしょう。