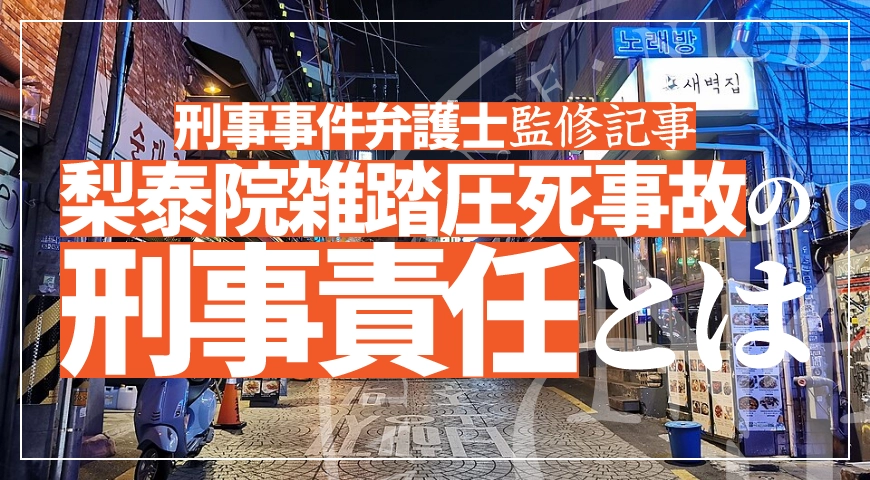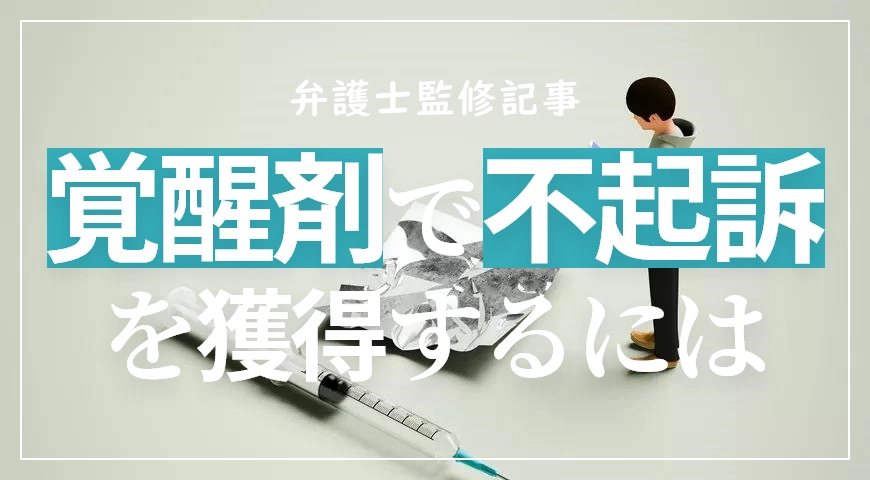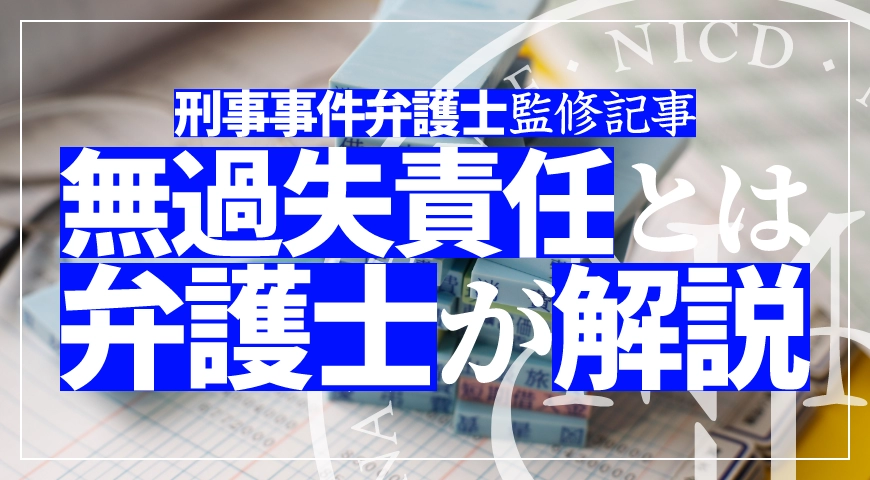
今回は、無過失責任(中間責任)の考え方、立証責任について、代表弁護士・中村勉が解説いたします。
無過失責任(中間責任)とは
刑法が保護法益として守っている生命、身体、自由、財産は、犯罪行為により毀損させられますが、その場合、故意によってなされることもあれば、過失によってなされることもあります。
刑事責任は、この態様を反映して、「故意責任」、「過失責任」と呼びます。
過失責任とは、過失による行為につき、民事上その損害を賠償する義務を負うことをいいます。
刑事上も過失により刑罰を科せられる犯罪類型もありますが、刑法は「故意犯処罰の原則」を採用しているため、過失によっても処罰されるのは「法律に特別の規定がある場合」に限られます(刑法38条1項)。
なお、刑事上は過失責任すら例外的であり、無過失責任で処罰するということはできないはずですが、両罰規定(法人に所属する役員や従業員らが、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定)は事業者等に無過失責任で処罰しているのではないかという批判があります。
ところで、我々の生活を支える民法の根幹となる基本原則には、所有権絶対の原則・契約自由の原則・過失責任主義があり、過失責任はその1つの考え方としても重要な役割を果たしています。
この民法の「過失責任主義」という考え方を言い換えると、「単に他人の行為により、損害を受けたというだけでは不十分で、原則として加害者に故意または過失がなければ損害賠償義務は発生しない」ということになります。
無過失責任の考え方
無過失責任とは、加害者に故意または過失がなくても、被害者は不法行為を理由とする損害賠償を請求できるという考え方になります。
民法が過失責任主義を採用しているにもかかわらず、なぜこのような考え方があるのでしょうか。そこで、無過失責任と呼ばれているものに、どのようなものがあるか見ていきましょう。
- 土地工作物責任(民法717条1項但書)
- 鉱害の賠償義務(鉱業法109条)
- 原子力事故の損害賠償責任(原子力損害の賠償に関する法律3条)
大気汚染防止法、水質汚濁防止法による賠償責任
こちらにあげているものは、どれも「危険責任の原理」を基礎に捉えたものと言われています。
つまり、社会生活における「特別の危険」に注目して、危険源の創造者・管理者に対して損害賠償責任を負わせている規定になります。
したがって、無過失責任とは、「特別の危険」=「科学の発展、生産手段の発展または機械や化学物質のメカニズム等の複雑化・高度化による発展段階では予想もできなかったような損害を生み出す危険」があり、過失責任だけでは被害者を救済しきれないことが起こることを想定して作られています。
また、どんな状況でもできる限り被害者を保護しようという考えに重きを置いている規定ということもいえます。
無過失責任と中間責任
上記のような規定で言われている無過失責任と似ているものに、中間責任と呼ばれているものがあります。
具体的には以下のようなものがあげられます。
- 責任無能力者の監督責任(民法714条)
- 使用者責任(民法715条)
- 土地工作物の占有者責任(民法717条1項本文)
- 動物の占有者責任(民法718条)
- 自動車運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)
上記の規定の場合は、加害者に故意または過失がなくても、被害者は損害賠償を請求できる無過失責任とは少し異なります。
原則として過失責任を取りながら、立証責任を被害者側から加害者側に転換しているのですが、加害者側が無過失を立証することが事実上困難であることから、実質的に加害者側の責任が認められやすくなり、したがって、無過失責任と同様の結果となることが多くなるというものです。
このように、過失責任と無過失責任との中間的な責任と言えることから、中間責任と呼ばれているのです。
交通事故の場面で言われる「無過失責任」は、実はこの「中間責任」なのです。順に解説していきます。
過失責任と中間責任の立証責任
過失責任と交通事故の場面にも適用される中間責任の最も重要な違いは、ズバリ被害者側と加害者側との「どちらに立証責任があるか」ということです。
例えば、皆さんが誰かに損害を与えられた場合、加害者に対して「損害賠償請求」をすることをイメージされるのではないでしょうか。
その場合の代表的な規定は、民法第709条です。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この規定に基づく損害賠償請求を裁判上行うには、被害者である皆さんが、加害者に過失があったとの評価を根拠づける具体的な事実を主張・立証することになります。
つまり、被害者が加害者の過失があったかどうかの主張・立証責任を負担することが損害賠償請求の原則となっています。
これに対して、中間責任の規定は、条文上、加害者に対してまず損害賠償義務を認め、例外的に加害者が「過失」がなかったことを立証したときに免責するとされているのです。
以上のとおり、通常の損害賠償請求では、被害者が加害者の過失を主張立証しなければならず、その労力も多大なものになりますが、中間責任の規定がある場合には、立証責任の転換がなされますから、被害者が加害者の過失を主張立証する必要はなく、過失がないと主張する加害者の方から自身に過失がないことを主張立証しなければ、その過失が認定されることになり、裁判における被害者の主張立証の負担は大幅に軽減されます。ここに過失責任と中間責任との間に大きな違いがあります。
交通事故における自賠法と立証責任
自動車をお持ちの方であれば自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が義務づけられていることはご存知と思いますが、これを定めているのが自動車損害賠償保障法(自賠法)であり、その第3条に中間責任の規定があります。
中間責任の規定を説明する前に、まず、この自賠責保険の趣旨を説明しておきます。
交通事故の被害者は、加害者に損害の賠償を請求する際に、相手にお金がなければ支払ってもらうことができません。
そのような被害者に対して最低限の保障を確保しようとしたのがこの自賠責保険です(ただし、自賠法が適用されるのは、傷害・死亡などの人身事故に限られます。
物損事故については、民法の不法行為で請求することになります。
自賠責保険については国土交通省のサイトにあるこちらをご覧ください)。
それでは、交通事故の中間責任の規定を見ていくことにしましょう。自賠法3条では以下のように明記されています。
自動車損害賠償保障法 第3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。
ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
自賠法の最大の特徴は、この3条にあるように損害賠償の責任を運行供用者(「自己のために自動車を運行の用に供する者」)に求め、故意または過失の立証責任を運行供用者に転換させたことにあります。
「運行供用者」とは、実際にその車両を運転していた加害者に限らず「車両の所有者」など、その車両の運行を管理・支配し、運行による利益を得る立場の者を広く含むと理解されています。
もっとも、仮に運行供用者が無過失であることを立証できれば損害賠償を負わないということも可能です。
具体的には、自己(運行供用者)及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを立証する必要があります。
しかし、この条文が無過失責任(実際は中間責任となります)呼ばれていることからも、加害者が無過失を立証することは事実上難しく、被害者が損賠賠償を受けやすくなっているのが実情です。
さらに、自賠法では賠償責任を運転者だけでなく、運行供用者にも負わせているところに特徴があります。
これにより、被害者は請求できる幅が広がることになり、損害賠償を受けやすくなっています。この場合も、この自賠法3条の中間責任が適用されることになります。
まとめ
今回は、無過失責任(中間責任)について解説をしてきました。
ここで押さえていただきたいポイントは下記3つです。
- 中間責任は、加害者側に過失の立証責任が転換される。
- 加害者が無過失を立証することは困難と言われている。
- 交通事故の場面でしばしば使われる「無過失責任」という言葉は自賠法3条の中間責任を指している。
無過失責任が問題となる事案は企業犯罪が多いです。
無過失責任が問題となる事案でお悩みの方は、企業犯罪の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。