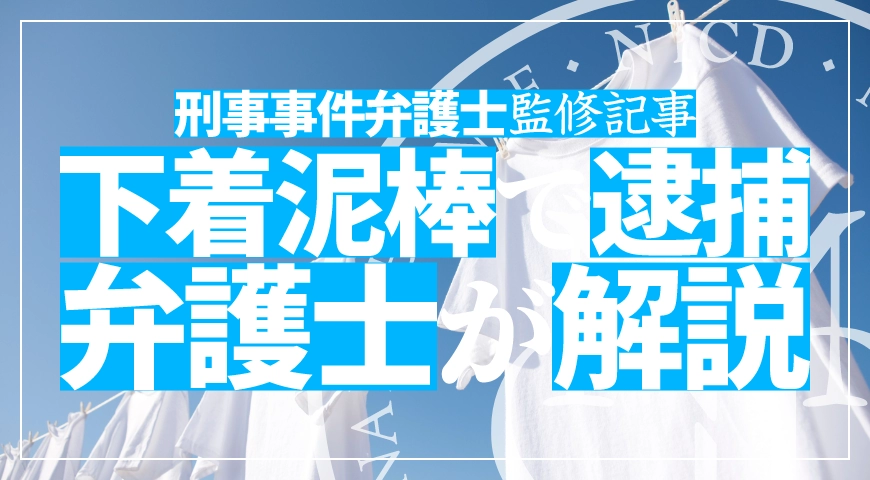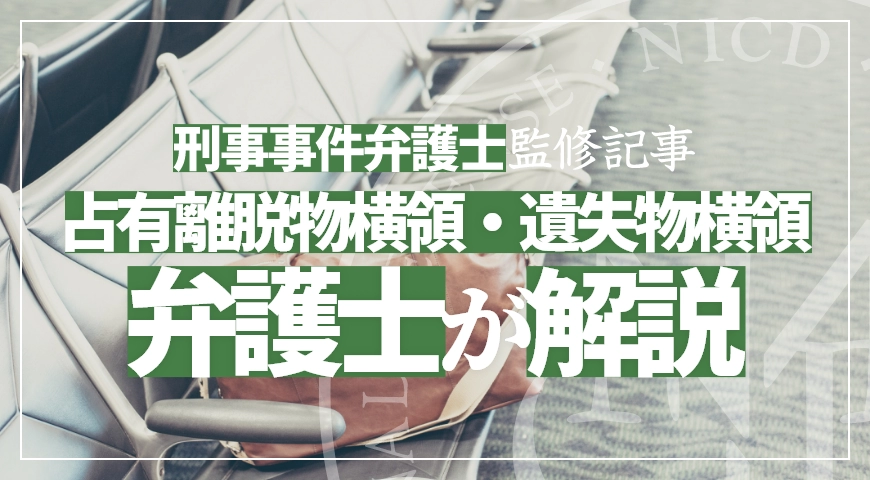「時効」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。ドラマでも時効が完成する直前に逮捕!といった場面もよくありますよね。この「時効」という言葉、実はいろいろな意味があります。
今回この記事では、身近で起こる可能性のある窃盗罪を例にとって、窃盗罪の「時効」について、窃盗罪の内容とあわせて詳しくお伝えいたします。
窃盗の時効は刑事と民事それぞれで問題となる
そもそも、「時効」には、①刑事の時効及び②民事の時効のふたつの種類に分けることができます。この二つの時効は意味も期間も全く異なるものですので、以下で一つずつ詳しく説明いたします。
窃盗の刑事における時効期間とは?
まず①窃盗罪の刑事の時効について説明します。刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことを意味します。公訴時効とは、刑事訴訟法で定められたものであり、検察官の公訴する権限を消滅させる時効のことです。この公訴時効が成立すれば、検察官は事件を起訴することができなくなります。
なぜ公訴時効がさだめられているのか
公訴時効が定められた理由については諸説あります。例えば、①時間の経過とともに「犯人が憎い」「厳罰に処すべし」といった社会の復讐感情が減少し、また刑罰により一般人に対して犯罪を思い止まらせる必要性や、犯人に対する再教育の必要性が減少することで、国家の刑罰権が消滅するという点に本質があるとする説や、②時間の経過とともに証拠が無くなる、または経年劣化による腐敗で長期間の保存と事実認定が困難になり、適正な審理ができなくなることを防止するため公訴権が消滅する点に本質があるとする説があります。
期間
公訴時効は犯罪ごとに定められている法定刑によって期間が異なります。公訴時効について定めた条文は刑事訴訟法第250条です。以下で、詳しく見ていきましょう。
1項 人を死亡させた罪について
まず人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪、例えば、殺人罪、強盗殺人罪などは公訴時効がないとされています。つまり、どれだけ時間が経ったとしても、検察官は起訴することができるのです。以前は、25年と公訴時効が定められていましたが、平成22年に刑事訴訟法が改正され、公訴時効が廃止されました。
次に、人を死亡させた罪であって無期の懲役又は禁錮に当たる罪、例えば、強制わいせつ致死罪、強盗・強制性交等致死罪などは公訴時効が30年とされています。そして、長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪、例えば、傷害致死罪、危険運転致死罪などは公訴時効が20年とされています。
最後に、上に掲げる罪以外の罪、例えば、過失運転致死罪、業務上過失致死罪などは、公訴時効が10年とされています。
2項 1項以外の罪について
250条2項では「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」以外の罪の公訴時効が規定されています。このように書いてあると何を指すのかよくわからないかもしれませんが、要するに、「人を死亡させなかった罪」と「人を死亡させた罪であって罰金以下の刑にのみあたるもの」(過失致死罪のみ)の二つについて定めた規定です。この規定では、以下のように法定刑の重さで7種類に分類して、公訴時効を定めています。
①死刑に当たる罪(1号。現住建造物等放火罪など)については、公訴時効が25年とされています。
②無期の懲役又は禁錮に当たる罪(2号。通貨偽造罪、身の代金目的略取等罪、強盗・強制性交等罪など)については、公訴時効が15年とされています。
③長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪(3号。強盗罪、傷害罪など)については、公訴時効が10年とされています。
④長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪(4号。窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、業務上横領罪など)については、公訴時効が7年とされています。
⑤長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪(5号。受託収賄罪、未成年者略取罪など)については、公訴時効が5年とされています。
⑥長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪(6号。名誉毀損罪、暴行罪、過失傷害罪、過失致死罪、脅迫罪、威力業務妨害罪、器物損壊罪など)については、公訴時効が3年とされています。
⑦拘留又は科料に当たる罪(7号。侮辱罪、軽犯罪法違反など)については、公訴時効が1年とされています。
窃盗罪の公訴時効
刑法に規定されている窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であります。ですので、上の④「長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に該当するため、公訴時効は7年となります。公訴時効は「犯罪行為が終わった時から」進行し始めます。
つまり、窃盗罪の公訴時効は他人の物を盗んでから7年が経過すると、公訴時効が成立し、それ以後はこの事件について検察官は起訴することができなくなります。この7年間という期間は、上で申し上げた通り、法定刑の重さで決まりますので、窃盗の被害額によっては左右されません。ですので、何億円もする宝石類を盗んだ場合であっても、駅前にあった中古の自転車を盗んだ場合であっても、公訴時効の期間は等しく7年となります。
公訴時効は「中断」することはない。
かつて旧法下での時効制度は、一定の事由によってそれまで進行していた時効が中断し、一定の事由がなくなってもまた1から時効が進行するという「時効中断」の方式を採用していましたが、現行法は、被疑者の利益を考慮し、「時効停止」という制度に変更されました。
どのような場合に公訴時効は停止するのか
時効の停止とは、一定の事由がある場合に、その事由がある限り時効の進行がストップし、その事由がなくなれば、引き続き残りの期間が進行するというものです。
刑事訴訟法では、公訴時効の停止事由として、①公訴が提起されたとき、②犯人が国外にいる時、③犯人が逃げ隠れしているために有効に起訴状が送れなかったときなどがあげられています。ここで注意して頂きたいのは、①公訴が提起された場合に初めて公訴時効は停止するのです。ドラマなどで、時効ギリギリに犯人を逮捕したという描写がありますが、逮捕しただけでは、公訴時効は停止しません。
窃盗の告訴期間とは?
刑事事件には、公訴時効のほかに、「告訴期間」というものも存在します。
刑事訴訟法第235条で、「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることはできない」と規定されています。
まずは、「親告罪」、「告訴」とは一体何かについて説明します。
親告罪
親告罪とは、告訴が無ければ、検察官が告訴することができない罪のことをいいます。以下、親告罪の例をあげます。
①事実が公になると、被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪
例 未成年者略取・誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等、名誉毀損罪・侮辱罪等
②罪責が比較的軽微であり、または当事者相互での解決を計るべき犯罪
例 過失傷害罪、器物損壊罪等
③親族間の問題のため、介入に抑制的であるべき犯罪
例 親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪、親族間の詐欺罪・恐喝罪等
告訴
告訴とは、犯罪被害者が警察官や検察官などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示を言います(刑事訴訟法第230条)。これに対して、被害者でない第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯罪者の処罰を求める場合を「告発」といいます(刑事訴訟法第239条1項)。両者の違いは、取消しなどの細かな点を除けば、意思を表示する主体にあります。告訴・告発は、検察官又は司法職員に対して、書面で行うのが普通ですが、口頭で行うこともできます。
窃盗罪の告訴期間
上記の例に挙がっていないように、窃盗罪は親告罪ではありません。ですので、窃盗罪に告訴期間は存在しません。そのため、6か月という期間は窃盗罪には関係が無く、7年の公訴時効のみが関係してきます。
窃盗の民事における時効期間は?
民事における時効とは
民事における時効には①取得時効、②消滅時効の2種類があります。まずはこの2種類の時効についてどのようなものなのか説明します。
①取得時効(民法第162条以下)
取得時効とは、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する人に、その権利を与える制度のことをいいます。この取得時効により権利を取得することを時効取得といいます。取得時効には長期取得時効と短期取得時効の2種類があります。
まず、長期取得時効とは、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を取得できるというものです。
次に、短期取得時効は、10年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した場合で、さらに占有を始めた時にそれが他人の物であることについて知らなかった場合や、知らないことについて過失がある場合に所有権を取得できるというものです。
②消滅時効(民法第166条以下)
消滅時効とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度のことをいいます。消滅時効により権利が消滅することを時効消滅といいます。例えば、商品を売った場合でも、一定期間なにもせずに経過すると、商品の代金を請求することができなくなるということです。
消滅時効は細かく規定されているので、詳しくは割愛しますが、一般の債権は10年間行使しなければ消滅するとされています。
窃盗の民事における時効期間
窃盗の民事における時効期間とは、損害賠償請求権の時効期間のことをいいます。
損害賠償請求権とは、ある違法行為によって損害を受けた者が、損害を与えた者に対して賠償請求することです。例えば、交通事故があった場合、その事故で怪我をした人が事故を起こした人に対して、治療費を請求することができるということです。
窃盗の被害者も、窃盗という違法な行為をした犯人に対して、被害額の請求をすることができます。これは、窃盗罪で警察に逮捕されたこととは、無関係であり、逮捕された後でも請求することができます。
そして、この損害賠償請求権は、厳密には不法行為に基づく損害賠償請求権というもので、通常の債権とは異なり、その消滅時効期間は3年となっています。つまり、窃盗の被害者であっても、損害および加害者を知った時から3年が経過した場合は、加害者に対して、損害賠償請求をすることができないのです。
窃盗の量刑相場は?
最後に、窃盗罪の量刑相場についてお話しします。
①初犯で被害金額が少ない場合
窃盗が初犯で、かつ被害金額も多額でないときの量刑の相場としては、略式手続により罰金となることが多いです。
②初犯であるが、余罪が何件もあったり、被害金額が多かったりする場合
今回の犯罪以外に、余罪を何件も犯していたり、また被害金額が大きかったりする場合には、罰金では済まず、公判請求されて正式な裁判となることもあります。この場合、余罪や被害金額によっては、執行猶予もつかない場合もあります。
③前科があるが被害金額が少ない場合
前科があり、今回が再犯である場合であっても、被害金額が少ないときは、被害弁償ができていれば、略式手続により罰金で済む可能性があります。ただし、公判請求されて正式な裁判になることもあるので注意してください。
④前科があり被害金額が大きい場合
再犯の場合で、被害金額が大きいときや示談ができていないときは、公判請求となることが多いです。公判請求される場合は、前科が多数あるときは実刑となるでしょうが、前科が多数に上らないときは、執行猶予つきの懲役刑が科されるのが通常です。その場合の刑期としては、懲役10カ月から2年6か月の間、執行猶予は2年から4年となることが多いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。時効は刑事の時効と民事の時効の2種類があり、使っている場面で全く意味が違います。ドラマや小説で時効という言葉が出てきたとき、どの意味で使っているのか考えてみるのも面白いかもしれませんね。