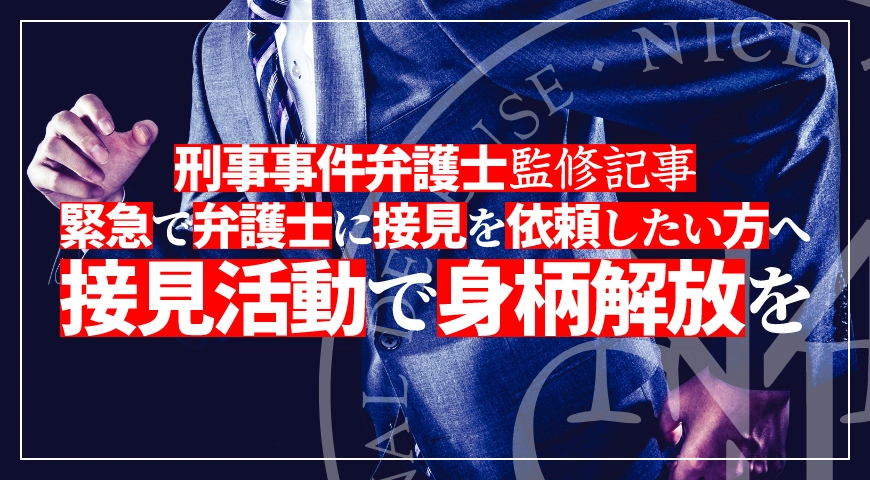毎年2月14日から、確定申告が始まります。領収書の整理等の会計処理に追われ、税務署に行ったら寒い中、税務署の外まで大行列。書類作成に苦労した確定申告で支払わなければならない税額に呆然とし、正直なところ「できれば払いたくない…」と思ってしまう人も多いのではないでしょうか。
しかしながら、払うべき税金を払わないと脱税という犯罪となってしまいます。そこでこの記事では、どのような行為が脱税に当たるのか、脱税をするとどんな処罰を受けなければならないのかについて、弁護士・中村勉が解説いたします。
租税に関する犯罪の種類
税に関連する犯罪は、脱税犯と租税秩序犯(租税危害犯)に分けられます。国家は法律によって国民から税金を徴収する権利(債権)をもちます。逆に国民は租税債務を負います。納税は、憲法で定められた国民の義務です。
この租税債権を直接侵害する犯罪を脱税犯といい、さらに逋脱犯(狭義の脱税犯)、間接脱税犯、不納付犯、滞納処分免脱犯に分かれます。
一方で、債権そのものではなく、国家の租税を確定させる権利や徴収する権利の正常な行使を阻害する犯罪を租税危害犯と呼び、これには単純無申告犯、不徴収犯、検査拒否犯等が含まれます。難しい用語が並んでいますが、これからその中身を詳しくみていきましょう。
脱税犯に該当する行為
逋脱犯(狭義の脱税犯)
皆様が真っ先にイメージされるところの脱税が、この逋脱(ほだつ)犯です。法的には、納税義務者や間接税の徴収・納付義務者が偽りその他不正の手段により租税を免れたり、還付を受けたりすることにより成立する犯罪です。
所得税法、法人税法、消費税法など、税の種類ごとに法律が定められており、各法律に租税犯に関する似たような内容の条文が規定されています。例えば、所得税法であれば238条1項、3項、239条1項に規定があります。以下、所得税法を例として挙げますが、他の種類の税法についても基本的には同様だと考えてください。
「偽りその他不正の手段」が何を指すかについて、判例では、「逋脱の意図をもって、その手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるようななんらかの偽計その他の工作を行なうことをいう」とされています(最大判昭和42年11月8日)。逋脱犯の成立のためには、なんらかの偽計その他の工作が行なわれる必要がある以上、単に申告しないだけでは、逋脱犯は成立しません(その代わりに、後で紹介する無申告犯が成立します)。
(故意の)申告書不提出逋脱犯(故意の無申告犯)
これは、平成23年度の改正で新設された罰則であり、確定申告書、修正申告書等の書類を法律で定められた期限までに提出しないことをもって租税を免れるという犯罪です(例えば、所得税法238条3項・4項)。「偽りその他不正の手段」を伴わない点で上記の狭義の脱税犯と異なり、租税を免れる故意が必要な点で下記の単純無申告罪と異なります。
間接脱税犯
突然ですが、酒の密造が禁止されている理由をご存じですか。それは、国家が酒税による税収を確保するためです。そうだとすると、酒の密造は、逋脱犯のように直接的に脱税行為をしているわけではないものの、密造行為そのものにより間接的に税を免れていると言うことができます。
このように、租税収入の確保を目的として一定の行為が禁止されているにもかかわらず、許可を受けずにその行為をした場合に成立する犯罪を「間接脱税犯」といいます。酒の密造(酒税法54条1項)のほかに、外国貨物の密輸入(関税法111条1項1号)などがそれに該当します。
不納付犯
たとえば給与所得者である労働者の場合、所得税は、労働者が直接税務署に納めるのではなく、雇用主が給料から源泉徴収し、それを税務署に納めることで、労働者(従業員)が租税を負担することとされています。雇用主は、源泉徴収・納付義務者ですから、源泉徴収したにもかかわらず、それを納付しないでいると、不納付犯が成立します(所得税法240条1項)。
虚偽申告犯
ここから先は、租税秩序犯(租税危害犯。徴税確保上の必要から設けられた手続規定に違反するもの。)です。虚偽申告犯は、その名のとおり、税務署等に虚偽の申告をすることにより成立する犯罪です。所得税法242条などがその例です。申告書等に虚偽があると、国家は正しい額の税を徴収できない危険が生じます。租税秩序犯(租税危害犯)に分類されるゆえんです。
単純無申告犯
単純無申告犯は、正当な理由がなく、納税申告書を法律で定められた期限までに提出しないことで成立する犯罪です(例:所得税法241条)。ただし、それが「偽りその他不正の手段」によって行なわれ、税を免れる故意もある場合には、この単純無申告犯ではなく、上記の逋脱犯(狭義の脱税犯)が成立し、「偽りその他不正の手段」を採ってはいないが、税を免れる故意はある場合には、同じく(故意の)申告書不提出逋脱犯(故意の無申告犯)が成立します。
この単純無申告罪は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に過ぎず、さらに、情状によりその刑を免除することさえできることとされています(所得税法241条)。
一方、同じ無申告であっても、逋脱犯(狭義の脱税犯)なら、所得税法で言えばたとえば同法238条1項が成立し、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下(場合によりそれ以上)の罰金、またはこの両方という重罰が科せられ、また、(故意の)申告書不提出逋脱犯(故意の無申告犯)でも、同じく所得税法238条3項が成立し、5年以下の懲役もしくは500万円以下(場合によりそれ以上)の罰金、またはこの両方というやはり相当の重罰が科されます。
この違いは、逋脱犯や申告書不提出逋脱犯が、単純無申告と違い、課税を免れる故意があり、逋脱犯の場合は更に「偽りその他不正の手段」を用い、現に租税を免れたり、還付を受けたりすることにより成立する犯罪だからです。
不徴収犯
徴収・納付義務者(例:雇用主)が納税義務者(例:従業員)から徴収すべき租税(例:所得税)を徴収しない場合、この不徴収犯が成立します(例:所得税法242条3号)。
検査拒否犯
税務署の職員等がする質問に答えなかったり、嘘をついたり、税務署の調査を拒否・妨害したりすると、検査拒否犯が成立します。検査拒否犯は、所得税法、法人税法などの各法ではなく、国税通則法128条、129条や国税徴収法188条といった、すべての種類の租税に適用される法律に規定されています。
故意でなく納税を忘れていたら
脱税する気など全くなかったのに、もしも税金を期限までに払い忘れてしまうと、何か犯罪が成立するのでしょうか。また自分で認識していないところで所得があった場合はどうでしょうか。
一般に、故意犯処罰の原則といって、罪を犯す意思(故意)のない行為は罰せられません(刑法38条1項本文)。ただし、(過失犯に関する)法律に特別の規定がある場合には、故意がなくても(過失犯であっても)例外的に処罰されます(同項ただし書)。刑法の条文は、刑法(一般法)に規定される犯罪だけでなく、他の法律(特別法)に定められた犯罪、罰則にも基本的に適用されます。
したがって、故意犯処罰の原則は、過失犯規定のない各種の租税法にも適用があり、単に申告を忘れていただけの場合、単純無申告犯は成立しませんし、自身の認識していない所得について逋脱犯が成立することもありません。
ただし、税金を納めなければならないという法律を知らなかったことを理由として、故意がなかったとすることはできません(刑法38条3項本文)。もっとも、情状により、その刑を減軽することはできます(同項ただし書)。したがって、所得の存在自体は認識していたものの、その所得について税金を支払わなければならないとは知らなかった、という主張は基本的には通りませんので、ご注意ください。
脱税で逮捕されるか
これまでに挙げた犯罪に該当するとしても、必ず逮捕・起訴されるのかといえば、実はそうとは言えません。たとえば、いわゆる税務調査によって経費の水増しや売上げを過小に帳簿に記録し、本来支払うべき税額を支払っていなかったことが発覚しても、逋脱額・逋脱税額が少なく、「偽りその他不正の手段」等犯行の態様がさほど悪質でないなどの事情により、逮捕・起訴といった刑事手続まで経ることなく、追徴課税され、加算税が課されて終了することもありますし、刑事手続に移行したとしても逮捕まではされず、在宅事件として起訴されるなどすることもあります。
刑事事件として処理されるのは、脱税額が多額で、態様が悪質なケースが多いと言うことはできるでしょう。だからといって、脱税行為が犯罪であることは確かですから、たとえ少額でも、税務調査が来ないことを期待して脱税を行い、もし調査されて発覚しても加算税を払えば済むだろうなどと考えるのは絶対におやめください。
脱税で逮捕された場合の罰則
租税犯の罰則は、租税の種類ごと、犯罪ごとに異なりますので、これまでにご紹介したものにとどめておきます。詳しく罰則をお知りになりたい方は、条文をご覧いただくか、弁護士にお問い合わせいただくのが確実です。
租税犯の罰則や裁判になった場合の量刑は、ますます重罰化傾向にあります。起訴されれば懲役刑が科され、場合によっては実刑となり、罰金額も多額になります。決して軽い刑罰ではありません。なお、注意を要するのは、税法にも両罰規定があるということです。両罰規定とは、行為者である代表者や従業員だけでなく、法人や使用者である個人事業主も処罰することを定めた規定です(例:所得税法243条)。
一例を挙げると、源泉徴収した所得税を納付するのは、従業員を雇用している会社(法人)または個人事業主ですが、実際に納税に関する事務を行なうのは経理等を担当する従業員個人であり、それを指示するのは法人の場合その代表者です(法人代表者や個人事業主がそれを指示すれば、その人は、両罰規定でなく脱税の共犯として処罰されます)。この経理担当者が適切な納税を行なわず、あるいは法人の代表者がそれを指示したなどとして脱税となった場合、行為者(従業員、法人の代表者)のほか法人自体または個人事業主自身も処罰され、法人または個人事業主には罰金刑が科されます。
租税犯の捜査
租税犯に関する事件(犯則事件)は、通常の刑事事件とは大きく異なる部分があります。それは、多くの場合、捜査(「捜査」でなく「調査」ということになりますが)が警察官ではなく、国税庁調査査察部(いわゆる「マルサ」)・各国税局所属の調査官等が行うという点です。
とはいえ、その「調査」の流れは通常の刑事事件の捜査とよく似ています。多くは内偵調査の上、裁判所が発する許可状によって臨検、捜索、証拠物の差押え等が行われます。調査によって犯則の嫌疑があると思料されれば、検察官に告発され(国税通則法155条)。場合によっては検察官により逮捕されます(検察官が逮捕の必要がないと判断すれば逮捕はされず、在宅事件として進行します)。 国税調査官には逮捕権限はありません。
間接国税の場合でも、情状が懲役の刑に処すべきものであるときと、犯則者が通告の旨を履行する資力がないときは、上記と同様の手続となります(国税通則法157条2項)が、そのようなときでなければ、検察官への告発が行われず、通告処分という簡易的手続によって終了することもあります。通告処分とは、国税局長または税務署長が罰金額、追徴金の相当する金額等を通告することであり、これが納付されれば検察官による刑事手続には進みません。
ただ、通告を受けた日の翌日から起算して20日以内に履行しないときは、検察官に告発されることがありますので、ご注意ください。
脱税で逮捕された場合の弁護活動
検察官は、留置の必要があると思料するときは、直ちに起訴するのでなければ、逮捕後48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求します(刑訴法204条1項)。裁判官が勾留を認めると、勾留請求の日から10日間、やむを得ない事由があると認められれば更に10日間勾留され、その間に検察官が捜査・取調べを行って起訴するかどうかを決めます(刑訴法208条)。
勾留が認められるのは、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由がある場合で、かつ、住居不定、②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由、③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由のうちいずれか一つの事情が存在することです(刑訴法207条1項本文、60条1項)。
したがって、弁護人としては、検察官及び裁判官に対し、上記の要件が欠けることを主張して勾留回避を目指し、もしくは勾留許可決定に対する異議を申し立て(刑訴法429条)、または、勾留された場合でも、検察官に対し、一刻も早い捜査・処分を求め、検察官及び裁判官に対しては勾留延長の理由がないことを主張し、もしくは勾留延長決定に対して異議を申し立てるなどしていくこととなります。
自白事件(脱税の事実を認めている事件)では、①ないし③の要件を満たさないことをいかに説得的に検察官に示すかが弁護人の腕の見せ所です。特に、脱税事件においては、一般に、会計帳簿等の証拠物の改ざん・処分、関係者との口裏合わせなどの罪証隠滅(いわゆる証拠隠滅)が既に行なわれ、あるいはこれが強制調査着手後に行われる可能性が非常に高く、検察官は、被疑者を勾留しないで捜査を続けることには消極的になりがちです。
したがって、弁護人としては、証拠収集や関係者への事情聴取等の捜査が既に十分に尽くされていることなどを理由に、被疑者が罪証隠滅する可能性が低いことを示していくことになります。また、身元引受人を選定し、その人に、被疑者を監督し罪証隠滅や逃亡などさせない旨の身元引受書を作成してもらうことも必要でしょう。
自白事件において、不起訴処分、裁判での執行猶予や刑の減軽を望む場合にもっとも大事なことは、速やかに、免れた税金を支払い、あるいは受けた控除を返還することです。もちろん、税金を全額支払い、控除を返還しさえすれば不起訴処分になるわけでも、ましては無罪になるわけでもありませんが、上記は情状面で決定的に重要なポイントです。
まとめ
この記事では、どのような行為が租税犯に当たるのか、租税犯の捜査はどのような手順で進むのか、逮捕されたらどうなるのかについて解説をしました。
当事務所代表弁護士の中村勉は、脱税事件を担当する東京地検特捜部財政経済班出身の元検事であり、脱税事件の捜査・公判を担当し東京地検特捜部に出向したこともある元検事であり、いずれも租税犯罪における検察の捜査手法について熟知しています。脱税に関する事件でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。当事務所の弁護士があなたをサポートいたします。