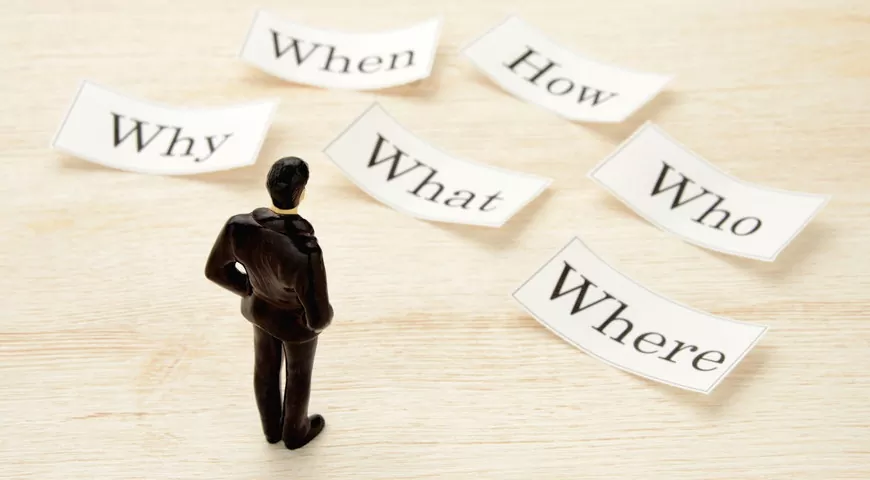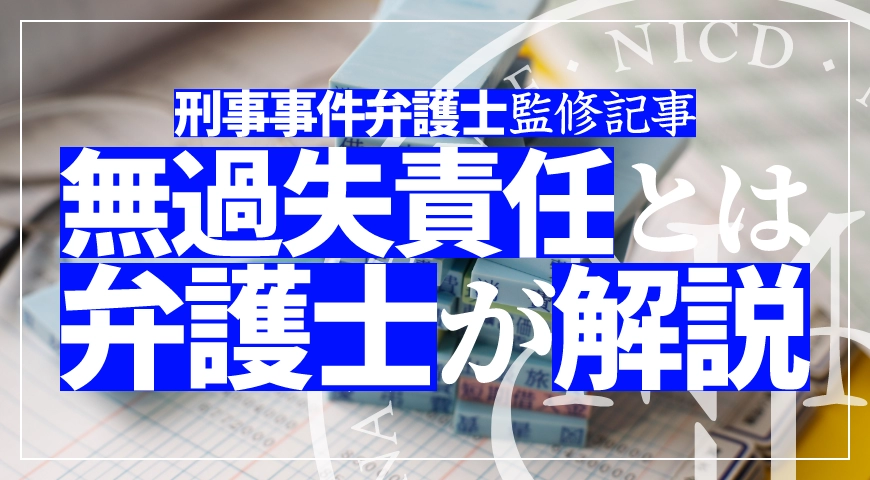「腹減ってるだろ?まぁ、とりあえず、カツ丼でも食え。」
刑事ドラマのワンシーンなどでこのような台詞を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。みなさんは、取調べと聞いて、どのようなものをイメージするでしょうか。
取調べを実際に受けたことがある人ならイメージがつくかもしれませんが、受けたことがない人も多いと思います。そこで、今回は、取調べとは何か、その特徴や実際に行われた際について詳しく解説します。(なお、現実の取調べでカツ丼が提供されることはありません。)
取調べとは?
「取調べ」とは、捜査機関が対象者に問いを発し、これに応答する供述を得て、その内容を記録・保全する活動をいいます。ニュース番組や刑事ドラマなどでは、「取調べ」、「任意取調べ」、「事情聴取」といった言葉がよく使用されます。これらの言葉はどのように違うのでしょうか。
「取調べ」という概念には、任意取調べや事情聴取の意味も含まれているのですが、「任意取調べ」という言葉は、逮捕前の被疑者に対する取調べを、「事情聴取」という言葉は、被疑者以外の者に対する取調べを指す際に使用されることが多いです。
もっとも、任意取調べ、事情聴取という言葉は、法律上の用語ではないため、明確に定まった定義はありません。単に、「取調べ」という言葉が使用される場合、逮捕後の被疑者に対する取調べを指していることが多いです。以下では、最も問題になることが多い、逮捕後の被疑者に対する取調べをメインに、解説していきたいと思います。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
刑事訴訟法223条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ…ることができる。
取調べの実情
被疑者は、逮捕され身体拘束されると、通常、捜査官から取調べを受けることになります。日本の捜査実務では、被疑者に対する取調べが重視されています。被疑者の供述は、起訴するか否かの決定や、起訴された場合に後に開かれることとなる裁判などで、非常に重要な役割を果たすからです。
取調べ受忍義務
現在の実務では、身体拘束された(逮捕・勾留された)被疑者に対する取調べについては、強制力がある、すわわち、取調べを拒否できないという運用がとられています。これを、実務では、取調べ受忍義務がある、といったりします(学者や刑事弁護人などの間では、被疑者に取調べ受忍義務を認めるべきではないという見解も有力です)。なお、前述の任意取調べはその言葉のとおり任意であり、事情聴取についても、対象者が取調べに応じる義務はありません。
弁護人の立ち会いは認められていない
取調べには、弁護人が取調べ室に入って立ち会うことは認められていません。したがって、基本的には、取調官と被疑者の二人だけの空間で取調べが行われることになります。取調べをしているまさにそのときには、弁護士に相談することができないのです。
取調べの内容
取調べで質問される内容については、被疑事実についてはもちろん、事件の経過や、動機、事件後の行動についてなど、様々なことが含まれます。余罪があるときには、余罪について質問されることもあります。
取調べの時間
警察官、検察官による1事件あたりの被疑者取調べの平均時間は、約20時間となっています。取調べの時間は、犯罪の性質や、被疑事実を認めているか否かなどによって左右されます。一般的には、重大犯罪の場合や、否認する場合などに、取調べ時間は長くなるといえます。なお、1日の取調べ時間については、原則として、深夜に行うことや長時間にわたり行うことは控えられなければなりません。
犯罪捜査規範168条3項
取調べは、やむを得ない理由のある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。
黙秘権とは?
被疑者には、憲法および刑事訴訟法によって、「黙秘権」という権利が保障されています。黙秘権とは、簡単にいうと、質問に対して何も答えない権利、です。この黙秘権は、被疑者が有する刑事手続上の権利の中で、最も重要な権利の一つです。なお、黙「秘」権と書くのが正しく、黙「否」権とするのは誤りです。つまり、黙秘権とは、「否」認するためだけの権利というわけではなく、一切のことを「秘」密にしておくことができる権利なのです。
憲法38条1項
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
刑事訴訟法198条2項
…取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
黙秘権はいつ行使するの?
では、黙秘権は、どのような場合に行使するのでしょうか。制度上は、何時でも行使してよいことになっているのですが、黙っておくことが常に被疑者の利益になるとは限りません。
一般的には、記憶があいまいなときや、事件を否認する場合などには、黙秘権を行使した方が良い一方、警察の調べ内容には間違いがない場合であって罪を認め早期の身体拘束の解放を望むときなどには、黙秘権を行使せず質問に素直に応じた方が良いといえます。
個々の事件において、実際に黙秘権を行使すべきかどうかの判断は極めて難しいのが通常です。したがって、黙秘権を行使するかどうかについては、弁護士の適切なアドバイスが重要になるといえるでしょう。
供述調書とは?
取調べが行われると、通常、「供述調書」というものが作成されます。供述調書とは、取調官が、被疑者の発した供述の内容を書面にまとめたものをいいます。被疑者の供述調書は、後の裁判において、一定の要件を満たせば、証拠として使用することができます。証拠としての使用が許された場合、供述調書に書かれている内容を覆すことは非常に難しいものとなります。
簡単に署名・押印をしてはならない
供述調書を、裁判で証拠として使用するためには、被疑者の署名・押印が必要となります。上記のとおり、一旦証拠としての使用が認められると、供述調書に書かれた内容を裁判において覆すことは難しいので、被疑者が供述調書の内容を確認し署名・押印した場合でないと、そもそも、供述調書を裁判で証拠として使用することはできない仕組みとなっているのです。したがって、取調官は、供述調書を作成すると、必ず、調書に署名・押印するよう被疑者に対して求めてきます。
署名・押印をするかどうかは、被疑者の自由な判断に委ねられているので、取調官によって供述調書にまとめられた内容が、自分が話した内容・ニュアンスと少しでも違うと感じた場合は、署名・押印を拒否するか、調書に記載された内容の訂正を求めるべきです。このような署名・押印をなすかどうかも、実際には極めて難しい判断を伴うため、黙秘権の行使をするかどうかの判断と同じく、弁護士の適切なアドバイスが重要になるといえます。
刑事訴訟法198条3項
被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
刑事訴訟法199条4項
前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
刑事訴訟法199条5項
被疑者が、調書に誤がないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
取調べの可視化
これまで、取調べは密室で行われ、外部から取調べの様子を裁判官や弁護人などが事後的に確認することはできませんでした。そして、このことが、取調官による自白の強要、ひいては無実の者を罰する冤罪の大きな原因の一つとなっていました。
そこで、近時の刑事訴訟法改正により、一定範囲の重大事件で身体拘束処分を受けている被疑者の取調べについては、原則として、被疑者の供述及びその様子を記録媒体に記録しておくことを捜査機関に義務付ける法制度が導入されました。簡単にいうと、「取調べの録音・録画」が義務付けられたわけです。
しかし、録音・録画の対象となる取調べは、一定の場合に限定されており、全事件の録音・録画はいまだ実現されていません。自白の強要の危険が、必ずしも重大事件の場合に限られないことからすれば、全事件の録音・録画制度の導入が望ましいというべきでしょう。
弁護士に相談しよう
逮捕後になされる取調べは、簡単に終わるものから連日取調べが続くものまで、事件によって様々であるといえます。また、逮捕後、勾留の段階にまで至ると、接見禁止といって、家族などに自由に会えなくなる可能性もあります。そのような状態での取調べは、身体的・精神的に非常につらいものになることが予想されます。被疑者の置かれた精神状態や、被疑者と取調官との間に大きな力の差があることからすれば、黙秘権を自由に行使することや署名・押印を拒否することには大きな困難を伴うのが実情です。
したがって、専門的なアドバイスを得ることができるという観点からはもちろんのこと、精神的な負担を少しでも小さくするための「良き相談者」という観点からも、取調べに臨む際には、弁護士に相談することをおすすめ致します。弁護士は、きっとあなたの力になってくれるはずです。
刑事訴訟法80条
勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
※この条文自体は「被告人」となっていますが、刑事訴訟法207条1項により、「被疑者」の場合であっても同様となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。取調べがどういったものであるのか、少しでもイメージしてもらうことができたでしょうか。取調べは、否認事件などにおいて、厳しい態様になることも珍しくはありません。また、既に説明したように、黙秘権を行使して何も話さないほうが良いのか、署名・押印をするべきかどうか、といった判断は、非常に難しいものとなります。したがって、取調べについて何か疑問が生じたときには、遠慮せずに何でも弁護士に相談しましょう。
「取調べ」がどういったものであるのか、実際に取調べを受けた場合にどうしたよいのか、あなたの疑問・不安を少しでも解消することができれば幸いです。