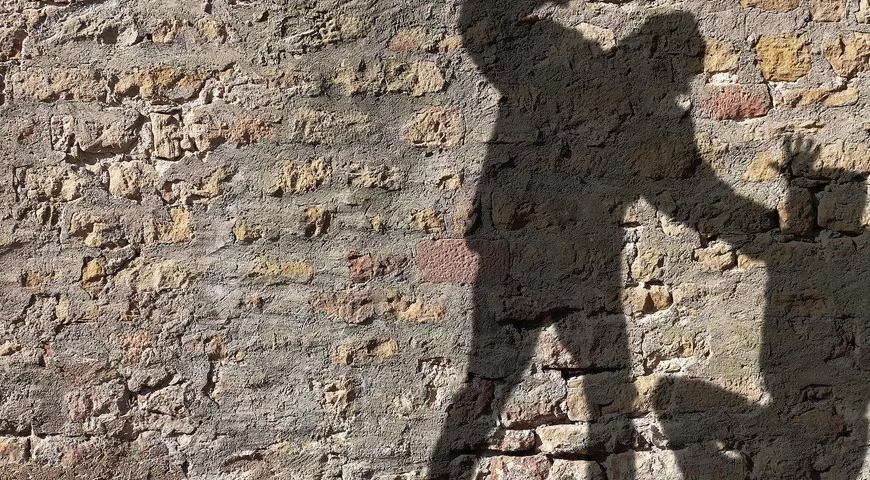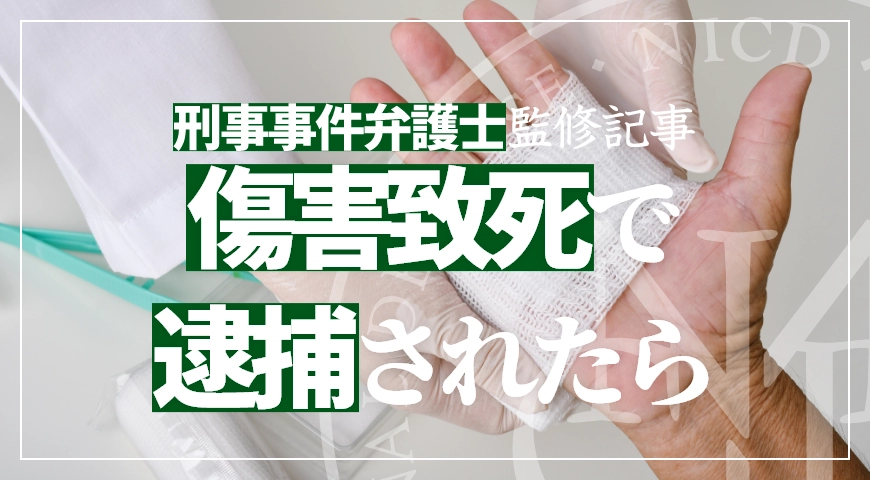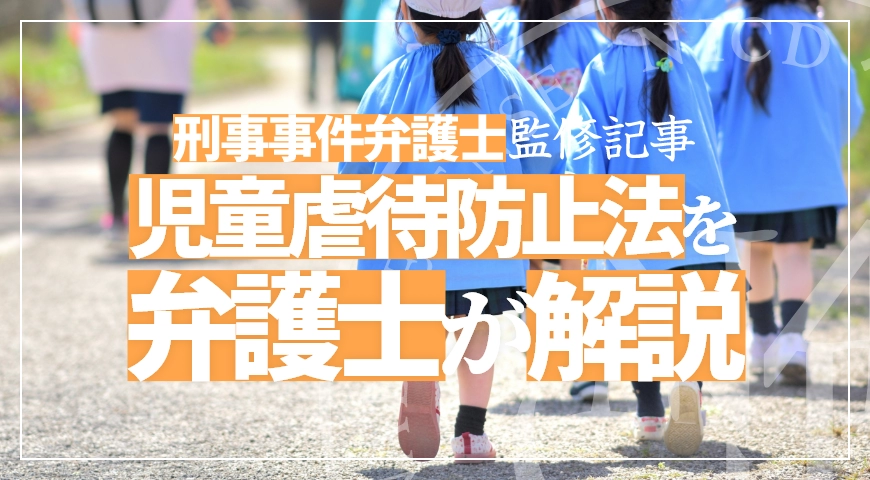
児童虐待は、親の子供に対する犯罪です。「虐待」は親だけの居る場、普通は家庭内において、いわば密室下でなされます。誰も虐待を受ける子供を助けることができず、周囲の人々は、そのような悲劇が現在進行形で進んでいることさえ知りません。そこから、児童虐待は繰り返し行われることを特徴とします。
児童虐待から子供を守る第一のポイントは、まず周囲の者が虐待事実に気づくことです。父親が加害者であるときは母親が気づきますが、母親も同時に虐待、いわゆるドメスティック・バイオレンスの被害者であることもあり、恐怖から警察に訴え出ることができないときがあります。
そこで、ついで身近に虐待事実に接する医師、あるいは教師の対応が重要になってきます。児童がベッドから落ちたなどと救急搬送されたときに、ベッドから落ちるだけでは説明が付かない多くのあざが体中にあった場合、医師は虐待を疑い、警察に報告します。学校教師も子供に身近で接していることから虐待事実に気づくことがあります。
このように、児童虐待はまずその被害事実をいち早くつかむとことから始まります。
そもそも「児童虐待」とは法的にどのような行為を差しているのか、その防止のために、法はどのように規定しており、そして、どのような問題点があるのでしょうか。
また、児童虐待には、どのような犯罪が成立しうるのでしょうか。犯罪が成立する場合、その刑はどの程度のものなのでしょうか。児童虐待を繰り返さないために、予防するために、何が求められているのでしょうか。
この記事では、児童虐待の様々な問題点について、代表弁護士・中村勉が弁護士の視点から解説いたします。
「児童虐待」とは
「児童虐待」とは、法的にどのような行為を差しているのでしょうか。
児童虐待防止法2条は、1~4号において、「児童虐待」に当たる行為を定義づけています。
児童虐待防止法 第二条
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
児童虐待にあたる行為
以下より、上記の児童虐待防止法第二条を詳しく見てまいりましょう。
①身体的な虐待
児童の身体に外傷が生じる、あるいは生じるおそれのある暴行を行なうことです。
例えば、殴る、蹴る、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、投げて落とす、溺れさせる、首を絞める、縄で拘束する等です。
②性的な虐待
児童にわいせつ行為をすること、あるいは児童にわいせつな行為をさせることです。
例えば、児童への性的な行為、児童に性的な行為を見せる、児童の性器を触ったり触らせたりする、性的な写真・映像の被写体にする等です。
③ネグレクト(放任)
長時間放置すること、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、保護者を除く同居人による虐待を放置すること、その他の保護者としての監護を著しく怠ることです。
例えば、食事を与えない、家に閉じ込めて外へ出させないようにする、不潔にする、車の中に長時間放置する、病気になっても病院へ連れて行かない等です。
④心理的な虐待
児童への著しい暴言、拒絶的な反応、児童が同居する家庭での配偶者に対する暴力、その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことです。
例えば、脅す言動、無視、きょうだい間で差別的に扱う、児童の前で家族へ暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス)等です。
特殊な「児童虐待」
以上の例は、一目で「児童虐待」とわかりそうな類型かと思います。しかし、最近では、一見すると医師でも児童虐待と見抜くのが難しい特殊な児童虐待が話題になっています。
たとえば、神奈川県大和市で2019年8月、小学1年の次男(当時7歳)を窒息死させたとして殺人の疑いで逮捕された母親について、県や市が「代理ミュンヒハウゼン症候群」(MSBP)の疑いがあるとみて対応していたことが明らかになりました。MSBPと言われてもあまり聞き覚えはないと思いますが、日本小児科学会ウェブサイトは、MSBPについて「子どもに病気を作り、かいがいしく面倒をみることにより自らの心の安定をはかる、子どもの虐待における特殊型」と説明しています。
厚生労働省の資料によると、子どもに薬を飲ませたり、口を塞いで呼吸困難にしたりして実際に症状を起こすケースと、虚偽の症状を訴えて子どもに不要な検査や治療を受けさせるケースがあるそうです。保険金目的の詐病などと異なり、親が自分自身を認めてもらおうと子どもを懸命に看病しており、医師でも見抜くのは難しいと指摘されています。
厚労省の「子ども虐待対応の手引き」は、MSBPへの対応を「一時保護などによって親子分離をすることで症状が消失することを確かめる」としています。日本子ども虐待医学会副理事長は、「詐病と見分けることで正しい対応をしなければならず、医療機関による早期発見が大切だ。ただ、虐待を暴くだけでは根本的な解決にはならず、加害者に寄り添う形での支援も必要だ」と述べております。加害者のケアについては、後ほど詳しく見ていきます。
児童虐待防止法の運用と問題点
このような児童虐待について、児童虐待防止法はどのような措置を定めているのでしょうか。
同法は、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに…市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない」と通告義務を定めています(6条1項)。通告があった場合、出頭要求(8条の2)、立入調査(9条)が行われます。この立入調査が拒否された場合、再出頭要求がなされ得ます(9条の2)。そして、児童虐待が行われている疑いがあるときは、令状発付を受けて、実力行使を伴う臨検・捜索が行うことができます(9条の3)。
この再出頭要求は、平成28年の法改正まで義務的でした。しかし、緊急時には、保護者の同意が得られない場合でも、虐待を受けていると思われる児童の安全を迅速に確保する必要があるとし、臨検・捜索手続の簡素化が図られたのです。
ところが、この臨検・捜索は、平成20年に導入されて以来、10年間で17件しかなされておりません。ある児童相談所OBは「臨検で職員と保護者が対立してしまうと、その後の継続的なフォローが難しくなる」と述べています。臨検・捜索手続の簡素化が図られた現在でも、慎重な運用が続いているのが現状です。
児童虐待防止法改正と問題点
2019年3月、児童虐待防止法の改正案が閣議決定され、2020年4月から改正法が施行されています。改正案には、体罰禁止の法定化、関係機関間の連携強化などが盛り込まれています。しかし、体罰禁止の法定化や関係機関間の連携強化は、児童虐待に対する抑止効果は得られるかもしれませんが、増え続ける児童虐待問題の抜本的解決になるような法改正といえるかは疑問が残ります。
抜本的な解決のためには、臨検・捜索の運用についての見直しが不可欠ではないでしょうか。児童虐待を行う保護者から任意で児童虐待に係る情報を得ることは難しいため、実力行使を辞さない姿勢が必要だと思います。臨検・捜索後の保護者との関係を過度に気にしすぎるあまり、手遅れになってしまっては、元も子もありません。2016年改正の簡素化に甘んじることなく、より実施しやすい臨検・捜索の運用が求められると思います。
児童虐待に成立しうる犯罪
児童虐待と一口に言っても、先ほど述べたとおり、児童に暴行を加えるもの、わいせつな行為をする又はさせるもの、長時間放置するもの、心理的外傷を与えるものなど、その類型は様々ですが(児童虐待防止法2条1号ないし4号)、以下、児童に暴行を加えるものに絞って見ていきたいと思います。
故意に人の身体へ危害を加える基本的な犯罪は、暴行罪(刑法208条)→傷害罪(同法204条)→傷害致死罪(同法205条)→殺人罪(同法199条)が挙げられ、この順に刑が重くなります。このうち、被害者が死亡した場合に成立しうるのは傷害致死罪か殺人罪であり、両者は殺意の有無によって区別されます。児童を死なせる虐待なんて殺人罪が成立して当たり前だと思うのが、一般的な感覚かもしれません。
児童虐待の裁判例傾向
しかし、児童虐待における殺意の立証は難しく、児童が死亡した事案でも、殺人罪ではなく傷害致死罪が成立するとする裁判例が非常に多いのです。
殺意が認められるためには、被告人が、児童が死ぬかもしれないことを認識しながら虐待行為をしたことを立証する必要があります。もし、児童を刃物で突き刺したり、長時間首を絞めたりした場合には、殺意を肯定するのは比較的容易です。
児童虐待では、武器を使用せず、素手で殴る、足で蹴る、のしかかる、体を揺さぶる、壁に打ち付けるなど、その行為から死亡結果が生じる危険性が高いとは一概にいえない暴行が多いのです。こうしたケースでは、「まさか死ぬとは思わなかった」との被告人の弁解が、全く不合理とまではいえないでしょう。
殺人罪の量刑は死刑又は無期もしくは5年以上の懲役であるのに対し、傷害致死罪の量刑は3年以上の有期懲役です。傷害致死罪も決して刑法に規定された犯罪の中では軽いものではありませんが、死刑や無期懲役があり得る殺人罪に比べれば、相対的に軽い犯罪とみることができます。
近年の裁判例では、児童を虐待死させ、傷害致死罪の成立を認めた事案について、概ね懲役4年~7年程度の刑を言い渡しているケースが多いといえます。
再犯防止策
以上見てきたとおり、児童を虐待死させたケースでも、親の多くは、7年も経たずして出所します。児童が死亡していないケースでは、当然ほとんどの親がそれより短い期間で出所します。
親子の縁を切るというのは容易ではありませんから、出所後、死亡に至らなかった子どもに対して、親は無関係ではいられません。もちろん、親子の分離を図るケースもありますが、親子の関係は子どもが成人してからも続くものであり、また、一般的に子どもは施設よりも家庭での成長が望ましいといえますので、分離さえしておけば万事解決とはいえません。しかし、何のケアもせずに出所させてしまうと、また虐待を繰り返すおそれがあります。そこで、受刑中の段階で、十分な再犯防止策を実施する必要があります。
法務省は現在、殺人や傷害致死、傷害などの事件の加害者に対し、刑務所や保護観察所などで暴力防止プログラムを実施しています。自身が暴力を振るうまでの道筋を振り返ったり、心の落ち着かせ方やコミュニケーションの方法を学んだりするものです。「虐待の加害者は、自身が過去に虐待の被害者だったケースもある」(法務省幹部)など、児童虐待の特性も考慮し、児童相談所や医療機関、民間の支援団体から情報収集した上で、刑事施設で導入しやすい新たなプログラムの内容を検討しています。
加害者のケア
受刑中だけなく出所後も、あるいは犯罪を起こしてしまう前にも、加害者ケアが必要です。
児童虐待における在宅援助としては、やはり児童相談所が大きな役割を果たします。児童相談所には、児童福祉司や心理職員、精神科医等の専門職がおり、その専門性を活かした援助を行っています。
具体的には、「対応の難しい子どもに対して、保護者がいかに努力してきたか」を話題の中心にし、「虐待という方法でない子どもの育て方」を一緒に考える保護者サポートや、遊戯療法の一種として、ままごと、トランプ、ゲームなど家庭でできる親子遊び訓練などを行っています。
児童相談所以外にも、精神科クリニックや、自助グループなどの援助機関があります。虐待をする親は、過去に自分も虐待を受けていた人が多く、グループミーティングを行うことで「このような経験をしたのは自分ひとりではなかった」ことに勇気づけられる人も少なくありません。
児童虐待問題では、虐待される児童の被害者ケアに重点が置かれることが多いですが、問題解決のためには、加害者ケアにもきちんと目を向ける必要があります。
児童虐待問題における弁護士の役割
弁護士が、虐待をした保護者の代理人として、子どもを一時保護した児童相談所との話し合いに同席したり、家庭裁判所の審問期日に出席したりすることが、しばしばあります。児童相談所としても、保護者の意向が法的に整理された上で話を進めることができるため、専門家である弁護士が保護者の代理人として就くことは望ましいことです。
刑事事件化された場合に、弁護人として活動することも弁護士の役割です。児童虐待問題が深刻化する昨今では、刑事事件の被疑者・被告人となった親に対する世論が厳しくなってきています。これまでの量刑傾向から一層厳しい刑が言い渡されることも十分に考えられます。それに伴って、今後、児童虐待の加害者側の弁護人の役割や責任も、大きくなっていくことでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。昨今大きな話題となっている児童虐待問題は、児童虐待防止法のあり方をはじめ、成立する罪名、量刑傾向、加害者のケアなど、着目すべき点がたくさんあります。また、児童相談所といった福祉機関、裁判所をはじめとする司法機関、精神科クリニックのような医療機関など、様々な期間が関与しており、とにかく複雑です。結局どこに相談すればよいのかわからないという方もたくさんいらっしゃることでしょう。
そのようなときは、児童相談所はもちろんですが、専門家である弁護士に相談するのもよいでしょう。弁護士は、児童虐待問題の様々な場面で関与することができ、各種の機関へとつなぐことのできるパイプの役割を果たすことができます。1人で抱え込まず、まずは思い切って相談してみることが問題解決の第一歩となるでしょう。