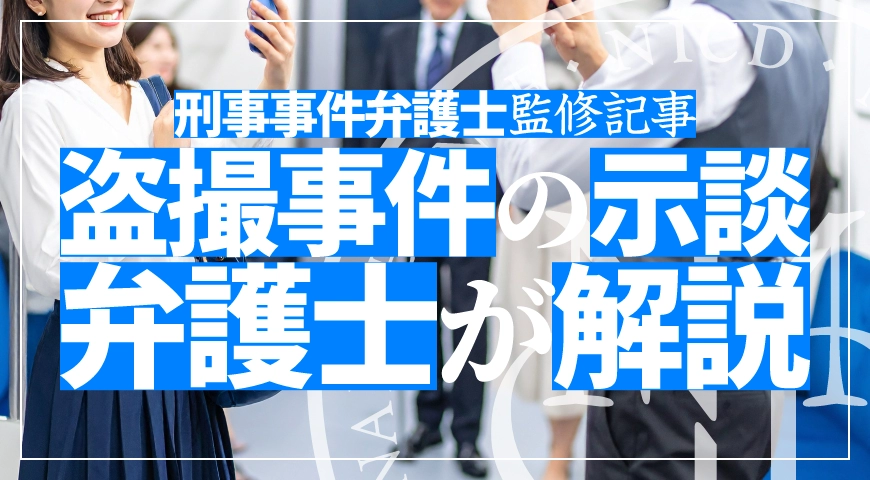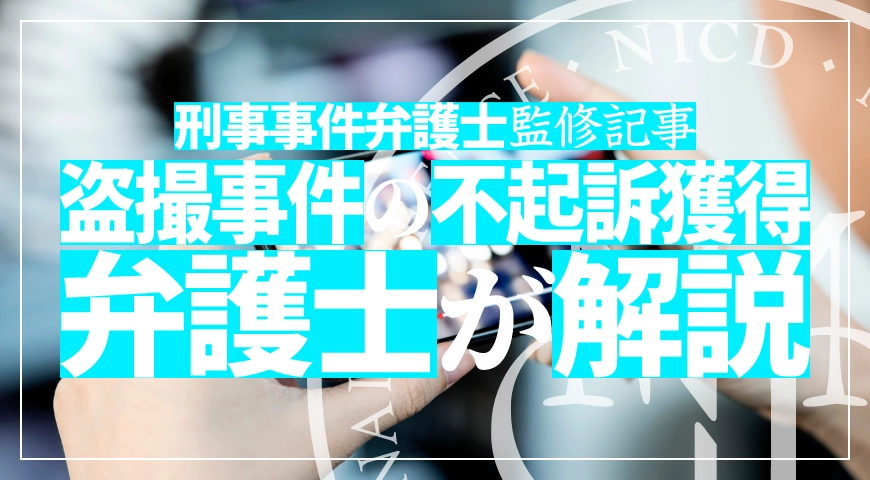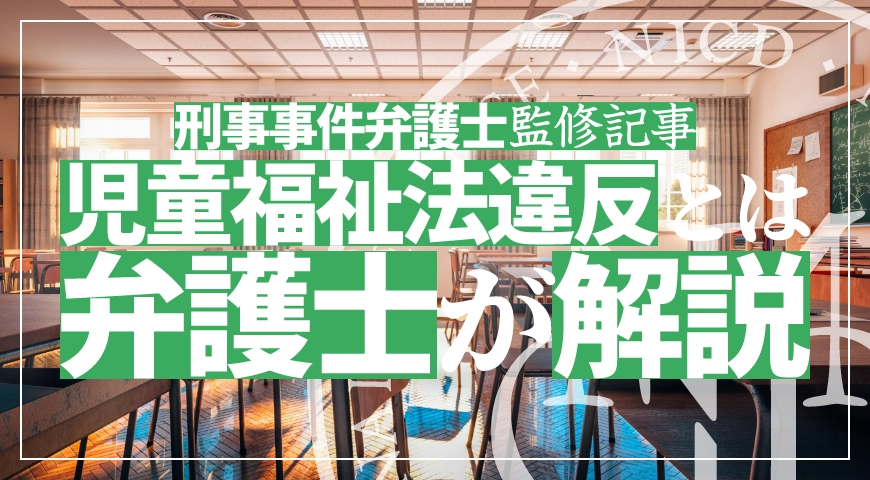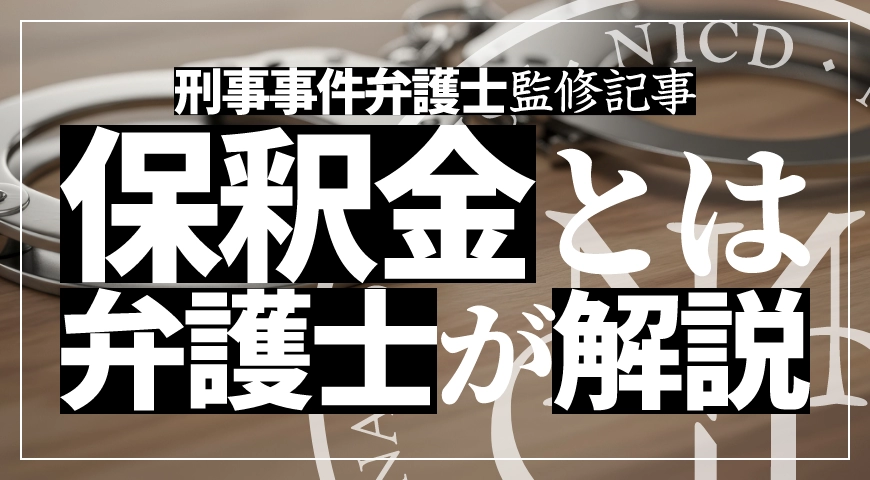
裁判を受けるにあたって、少しでも自身の負担を減らし、また、弁護人と充実した協議を行うことが重要です。保釈は、それを実効的に担保するために非常に重要な手続きとなりますが、皆さんはその内容や条件をご存知でしょうか。
そもそも保釈とは一体何か
保釈とは、一定の保証(保証金・有価証券・保証書)を条件として、被告人を勾留による拘禁状態から解放する裁判とその執行を言います。保釈されると、被告人の身柄が解放されることになります。
勾留状の効力自体を消滅させるものではないため、「勾留の取消し」(刑事訴訟法第87条)とは異なります。
被告人が保釈条件に違反した場合、「保証金」の没取という経済的苦痛が加えられることを担保に、被告人の逃亡や罪証隠滅を防止しつつ身柄拘束から解放して自由を保障する制度です。
保釈請求は、起訴された後しか行うことができず、逮捕や起訴前の勾留の段階では、認められていません。
保釈が許可されると元の生活を送りながら裁判に対応することができ、弁護人との充実した打ち合わせも容易となり、裁判に向けた弁護活動を積極的に行うことが可能となります。
保釈金について
一般によく言われる保釈金とは、上記の一定の保証として納められる保証金のことを言います。
保釈が執行されるためには、保釈保証金の納付が条件となります。そのため、事前準備として、保釈保証金を確保することが必要となります。保釈が認められる場合は以下のとおりです。
保釈が認められる3パターン
保釈の中には、(1)権利保釈(必要的保釈)(刑事訴訟法第89条)、(2)裁量保釈(職権保釈)(刑事訴訟法90条)、(3)義務的保釈(刑事訴訟法第91条)の3つがあり、種類ごとに保釈が認められる条件が異なります。
(1)権利保釈
被告人は、有罪判決を受けるまでは、「無罪の推定」を受けることになるので、適法な保釈の請求があった場合には、裁判所は、刑事訴訟法第89条第1号から第6号に規定する事由(除外事由)がある場合を除いては、必ず保釈を許さなければなりません。これを必要的保釈(権利保釈)と言います。
つまり、以下の6つのいずれにも当てはまらない場合は、保釈は認められるということです。
なお、逃亡のおそれがあることは、必要的保釈の除外事由にはなりません。そもそも保釈とは、保証を立てさせて、保証金の没取という経済的苦痛を威嚇として、逃亡を防止するものであるためです。
除外事由
1号
「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」と定められています。
法定刑の重い一定の罪については、逃亡のおそれが強く推定され、保釈保証金の担保によっては逃亡を防止することが容易ではないと考えられるために、権利保釈の除外事由として定められています。
2号
「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。」と定められています。
「前に」とは、保釈決定のときを基準にしてそれより以前という意味になります。「有罪の判決を受けたことがある」とは、判決の宣告がされていればよく、必ずしも判決が確定していることは必要ありません。
そのため、刑の執行猶予や免除があった場合であっても、本号に該当します。執行猶予期間の経過や特赦等によって、刑の言渡しが効力を失った後は、これらの制度の趣旨に鑑みて、本号の適用はありません。
3号
「被告人が常習として長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。」と定めています。
「常習として」とは、常習性(犯罪を反復する被告人の属性)が犯罪構成要件になっている場合だけでなく、広く常習性が証拠資料によって認められる場合も含みます。
常習性の判断は、諸般の事情から認められれば足り、前科・前歴(同種の前科・前歴に限られない。)の有無は、これを判断するための資料の一つとして考慮されることになります。
4号
「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」と定められています。
勾留の目的の1つが罪証隠滅の防止です。そのため、保釈をしたとしても罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があるときは、権利保釈は認めないという考え方がとられています。
実務上は、一定の証拠や証言が収集された上で公訴提起されていることから、裁判所が被告人を保釈した場合に罪証隠滅の可能性が全くないと考えることは少なく、4号の該当性が否定されることは多くありません。
そのため、実際上は、上記4号の該当性が認定され、権利保釈は認められず、後述する裁量保釈により保釈が認められることが殆どとなっています。
5号
「被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当の理由があるとき。」と定めています。これは、罪証隠滅の一態様である、いわゆる「お礼参り」を防止するために設けられた規定です。
6号
「被告人の氏名又は住居が分からないとき。」と定めています。氏名か住居のいずれか一方がわからないときは本号に当たり、住居不定もこれに当たります。
(2)裁量保釈
裁量保釈とは、権利保釈の要件を満たさない場合であっても、裁判所の裁量によって保釈が許可される場合を言います(刑事訴訟法第90条)。
裁判実務としては、保釈請求があった場合には、まず権利保釈に当たるかどうかを判断し、当たらないと認められる場合には進んで裁量保釈の当否についても判断すべきであり(東京高決昭29・4・21判特40号73頁)、かつ、抗告ないし準抗告に当たっては、裁量保釈の判断の不当性についても主張しうるとされています(最決昭29・7・7刑集8巻7号1065号)。
裁量保釈の拒否の判断基準
裁判所は、「保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる」とされています(刑事訴訟法90条)。
従前は、「適当と認めるときは」という抽象的な規定でしたが、裁量保釈の判断基準を明確化する目的で、2016年に法改正が行われて上記の文言のとなりました。
事件の軽重、事案の性質・内容、犯情、被告人の性格、経歴、行状、前科・前歴、家族関係、健康状態、審理の状況、勾留期間及び共犯者があるときは共犯者の状況等、諸般の事情を考慮した上で、上記の要件に沿って裁量保釈の可否が判断されます。
(3)義務的保釈
義務的保釈とは、不当に勾留が長引いたときに、請求または職権によって保釈される場合を言います(刑事訴訟法第91条)。
「不当に長く」というのは、単なる時間概念ではなく、事案の性質・態様、審判の難易、被告人の健康状態その他諸般の状況から、総合的に判断される相対的概念であるとされており(名古屋高決昭34・4・30高集12巻4号456頁)、具体的な場合に応じて判断されることになります。
判例
不当に長い拘禁に当たるとした判例としては、単純な1回の窃盗の事案において、被告人に逃亡のおそれもなく、弁論も終始一貫しているのに、その身柄を逮捕後109日間拘禁し、108日目に被告人が初めて犯行を自白した場合において、この自白は不当に長く抑留又は拘禁された後の自白に当たるとした最高裁判例(最大判昭23・7・19)があります。
また、単純な2個の窃盗事件で、被告人が拘置所の病舎に収容される程の健康状態であったにもかかわらず、逮捕後6か月10日間拘禁され、その後に初めて犯行を自白するに至った場合には、この自白は憲法38条2項の不当に長く拘禁された後の自白に当たるとした最高裁判例(最大判昭24・11・2)等があります。
保釈金の相場
保釈保証金の金額の相場は、主に事案の重大性とそこから考えられる逃亡や罪証隠滅の程度によって決定されます。
事案が重大であればあるほど、刑罰を逃れたいとして逃亡する可能性や、自己に不利な証拠を隠滅する可能性が懸念されるからです。
例えば、前科のない薬物の単純所持事案など、執行猶予付きの判決が高い確率で見込まれる事案のような場合には、保釈金は150万円程度が一般的です。
一方で、示談が成立しない限り実刑判決の可能性が高い不同意性交等罪の事案や、多くの関係者が存在し口裏合わせ等が懸念される企業犯罪に関する事案などでは、500万円や1000万円に至るような高額な保釈金が定められることもあります。
保釈金の金額はどのように決まるのか
保釈金の金額については、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない」と規定されています(刑事訴訟法93条2項)。
実際には、その中でも特に「犯罪の性質」と「被告人の資産状況」が重視されます。
まず、保釈金の役割は先述の通り、「逃亡を防ぐための保証」にあります。仮に逃げてしまった場合には保釈金が没収されるため、被告人にとって「逃げたら損をする」と思わせる金額でなければ意味がありません。
そのため、重大犯罪であればあるほど処罰も重くなるため、逃亡のリスクも高いと判断され、高額になりやすい傾向にあります。逆に比較的軽微な事件では、保釈金が低く抑えられることもあります。
また、被告人の資産状況も重要です。
財産が豊富な人にとって、100万円程度の保釈金では「没収されても痛手ではない」ため十分な保証になりません。このため、被告人が「絶対に失いたくない」と思う水準まで金額が設定されます。
保釈金が高額になるケースとは
保釈金の金額は一律ではなく、事件ごとに裁判所が判断します。その中でも、次のような場合には金額が高くなる傾向にあります。
(1)重大な犯罪の場合
殺人、強盗致傷、不同意性交等事件など、刑罰が重いとされる事件では、被告人が「厳しい処罰を避けたい」と考えて逃亡を図る可能性が高いと見られます。そのため、逃亡を防ぐために高額の保釈金が設定されることがあります。
(2)被告人に資産が多い場合
資産を豊富に持つ人にとっては、数百万円程度の金額では「逃げても構わない」と考えかねません。保釈金は「没収されたら大きな痛手になる」金額でなければ意味をなさないため、資産状況に応じて金額が高く設定されます。
(3)逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと判断される場合
過去に逃亡歴がある、海外に強い人脈を持つ、証拠隠滅を行う可能性があるといった事情があると、裁判所はより高額な保釈金を設定し、被告人に強い抑止をかけます。
保釈金を納付するタイミング
保釈がなされるまでの手続の流れとしては、以下となります。
- 保釈請求書の提出
- 検察官への求意見(刑事訴訟法第92条1項)
- 保釈許可決定
- 保釈保証金の納付
- 保釈の執行
裁判所が保釈を許可する決定を出した後、速やかに保釈金を納付する必要があります。納付が完了して初めて被告人の保釈が執行されるため、「保釈許可決定=即時釈放」ではない点に注意が必要です。
通常は、裁判所の指示に従って当日または翌日に納付手続を行います。
保釈金は後から返って来るのか?
保釈金は制裁として科されるものではなく、あくまで被告人の身柄を確保し、裁判に出廷させることを目的とするものですので、没取されなければ、たとえ有罪判決を受けたとしても全額返還されることになります(刑事訴訟法規則第91条2号参照)。
場合によっては保釈金が没収されてしまう?
先述の通り、没取された場合には、保釈金の一部又は全部が返還されないことになります。
没取される場合についても刑事訴訟法に規定があり、以下の5つ(刑事訴訟法第96条1項各号)のいずれかに当たる場合には、裁判所は、保釈を取り消し、決定で保証金の全部又は一部を没取することができます(刑事訴訟法第96条2項)。
- 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき
- 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき
- 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき
保釈金を用意できない場合の対処法
被告人は資力に乏しいことも多く、このような保釈金を到底用意できないこともあります。そのような場合に、保釈金を用意するために利用することができる手段があります。
協会(民間団体)による立替え制度
協会にはいくつか種類がありますが、例えば日本保釈支援協会は後述の保証書の発行も行うほか、保釈保証金の立替えも行っています。
日本保釈支援協会の場合、被告人の関係者が同協会に保釈金の立替えを申し入れ、同協会が審査を行い、立替え可能と判断した場合には、関係者と同協会との間で立替えに関する契約を締結して、同協会から弁護人に立替金が振り込まれるという形がとられています。
その後保証金が還付されたのち、再び弁護人から同協会に立替金を返還するというシステムになっています。詳細は、各協会のウェブページなどを参照してください。
保釈保証保険制度
また、これまでは、保釈保証金については、通常被告人やその親族、配偶者、雇用主等が納付してきましたが、2013年夏より、一部地域において、日本弁護士連合会による「保釈保証保険制度」が実施されています。
保釈保証保険制度とは、全国弁護士協同組合連合会に対して、被告人の弁護士や親族その他の関係者が申し込みを行って、申込者が納付する保証金について、全国弁護士協同組合連合会が連帯保証するというものです。
その他の手段
保釈保証金を納付する以外の手段として、保釈保証金に代えて有価証券あるいは被告人以外の者の保釈保証書を提出することもできます(刑事訴訟法第94条3項)。そのため保釈保証金を準備できない場合には、これによってカバーすることを検討することも考えられます。
まとめ
保釈金制度の概要について解説をしてきました。保釈が認められるかどうか、認められるとしても保釈金をいくら・どのように用意すればよいのか等、事件によって具体的な条件は異なってきます。
ご家族の一日でも早い保釈をお考えの方は、刑事事件に強い弁護士へできるだけ早くご相談ください。