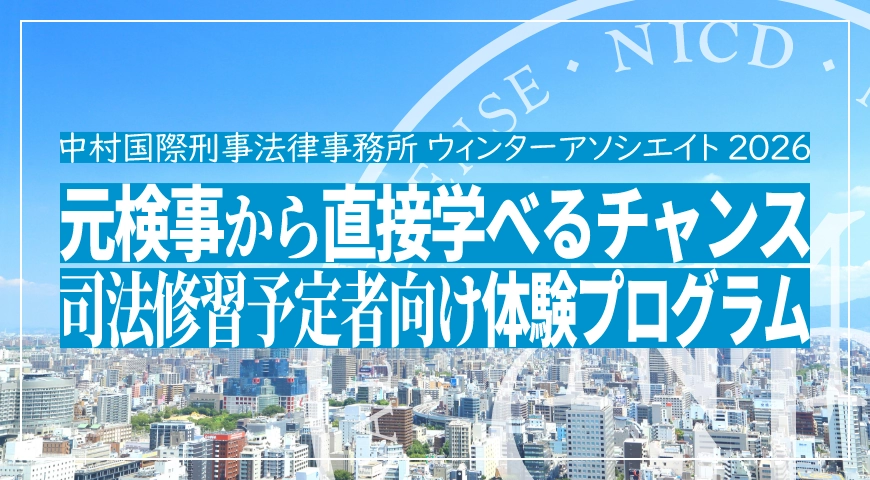サマーアソシエイト 参加者感想文 K.M.さん(2025年)(神大ロー在籍)
私は、2025年8月末に行われた中村国際刑事法律事務所様のサマーアソシエイトプログラムに参加いたしました。
私がこのプログラムに応募した理由は、将来の進路として検察官を志望しており、刑事司法に関わる法曹として刑事弁護士の仕事を体験しておくことは非常に良い経験であると考えたこと、元検事の中村先生のご指導の下、起案をするという唯一無二の経験ができると考えたことにあります。
本プログラムに応募する際には、検察官志望であるにもかかわらず応募してもよいのかと考えていましたが、この5日間を通して応募してよかったと改めて感じました。
この5日間では、たくさんのことを経験させていただきました。弁護士として模擬の依頼者相談を受けるところから始まり、捜査段階での弁護、検察官の公訴提起、公判手続きなど、そのすべての段階でたくさんの起案をして、そのすべてにコメントをいただきました。
ここで書くにはあまりにも多すぎると思いますので、なかでも特に印象に残ったことについて書いていきたいと思います。
まず、プログラムでは、依頼者からの模擬相談から始まり、その後は、模擬接見を行い話を聞くという流れで刑事弁護人の職務の流れをつかんでいきました。
相談を受ける際には電話対応に焦り、相手方の聞くべき情報を漏れなく聞くことができていなかったことを指摘していただき、普通は聞くべきであると自分の中ではわかっているのに、いざ実践してみると忘れてしまうという対応の難しさを実感しました。
その中で、なぜそのようなミスをするのかを考えると、実際の事件ではないということから、心の中で気を緩めていたことが原因の1つであると考えました。
しかし、気を緩めていれば、得られるものも少ないであろうし、成長もなく、なにより学ぶ姿勢としてふさわしくないと猛省し、模擬的とはいえ、目の前の依頼者は実際に家族を逮捕された人であり、手続はもう始まっているという意思でプログラムに臨むこととしました。
プログラムの中では、勾留請求を回避する意見書や勾留却下決定に対する準抗告申立書、勾留決定に対する準抗告申立書、起訴状、証拠意見書、冒頭陳述、論告などの書面を起案しました。
起案したものを中村先生に提出し、添削をしていただきました。私は起案するにあたって、配布された記載例を参照して記載する事項を考えていました。
しかし、中村先生は繰り返し何度も、1つとして同じ事件はないこと、事件にはそれぞれ「顔」があること、その「顔」を踏まえて事件の事案、事実に肉薄することが法律家として重要であるとおっしゃっていました。
今考えてみますと、最初の方の起案はこのような点を意識することができておらず、配布された記載例に記載された事項を単に含めていただけでした。
中村先生にご教授いただいて以降は、プログラムには、この点を最重要視して取り組むことを意識していました。その甲斐あってか、公判手続の論告はしっかりと事件と向き合っての起案を意識することができていたと思います。
事案に即した起案をするということは、司法試験受験生にとっても大切なことであると思いますので、今後の大学院生活においても問題を解く際には、意識し続けようと考えています。
私が、プログラムの中で、最も苦労した点は公判準備や公判手続における証人テスト、証人尋問及び被告人質問でした。これらのうち、被告人質問だけは学部時代の模擬裁判で経験があったのですが、その模擬裁判で扱った事案では、検面調書が不同意でないという設定だったので、証人が出てこないものでした。
そのため、証人尋問の主尋問については経験がありませんでした。最初は自分なりに尋問事項案を作り、何を聞くべきであるかを考えていました。
いざ、証人テストに臨んでみると、証人役の中村先生は調書にある通りに証言してくれないこと、誘導をおそれてあまりにもオープンすぎる質問をしてしまい、どのような証言をしていいかわからないと言われてしまったことなどがあり、証人テストの時点でかなり心が折れかけていました。
挙句の果てには、「何を聞きたいのか分からない。」「こんな尋問じゃダメ。」というお言葉を先生からいただくことになってしまいました。
このような証人テストでは到底OKが出るはずもなく、やり直しとなりました。そして、再び尋問事項案を練り直し、証人テストを行いました。
1回目の尋問よりはましになったと思いますが、どこかぎこちなく実際の調書に書かれている事実関係をかなり端折ったような尋問になってしまったことを覚えています。
証人テストが終わってから、中村先生に講評をいただきました。その中で、主尋問では時系列順に何が起こったのかを聞かなければならないこと、主尋問は、裁判官の心証を形成するために裁判官に対するプレゼンテーションであり、裁判官が頭の中で具体的にイメージできなければならないこと、これらの点を意識して臨む必要があるとおっしゃっていました。
それらの点を踏まえて、翌日の模擬裁判の証人尋問に臨もうと考えていましたが、やはり尋問技術は経験が重要であり、完璧な尋問をするためには、一朝一夕では足りないことを痛感しました。
この5日間で最も大変であったのは、以上で述べた証人尋問関連に取り組むことでした。その中では、私自身がうまくできないことに対する挫折感、無力感を強く感じていました。
私は、検察官役として模擬裁判に取り組んだので、主尋問がうまくいかなかったことで立証ができていないことを不安に覚えました。今は、この模擬裁判に当事者意識をもって、真剣になって取り組めていたからこそ上記のような感情を抱くことができていたと思います。
検察官として被告人の犯罪を立証するために主尋問を行い、それが失敗すれば立証ができていないことになるというプレッシャーの下、法廷に立つという当事者ならでばの緊張感をもって取り組めていたのではないかと思います。
最後に、お忙しい中でプログラムの5日間という長い間お世話になりました中村先生をはじめとする大阪事務所の皆様には、このような貴重な体験をさせていただいたことに関しましてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
先生方には愛のあるご指導をいただけましたこと、今後の一生の財産になると思います。本当にお世話になりました。