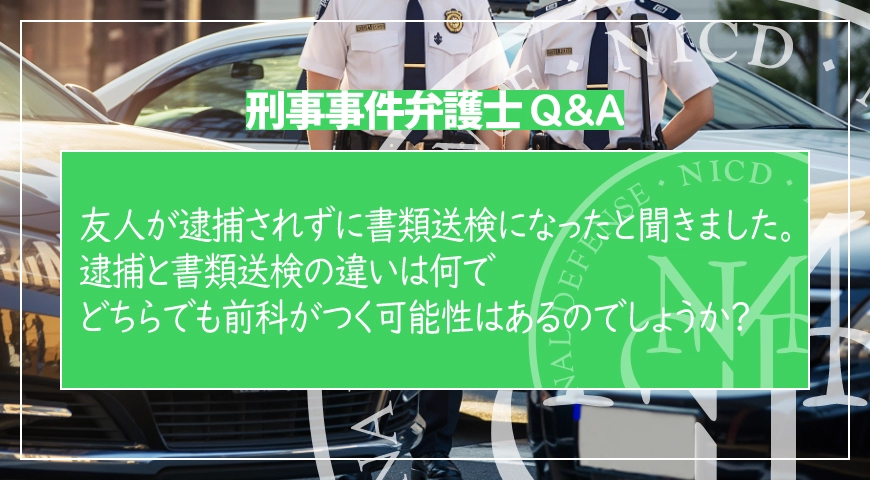
ご友人が「逮捕されずに書類送検された」という状況は、刑事事件の手続きにおいて「在宅事件」として扱われていることを意味します。逮捕の有無と、その後の起訴・不起訴の判断、そして前科が付く可能性には密接な関係があります。
逮捕と書類送検の定義と違い
刑事事件の捜査は、大きく「身柄事件」と「在宅事件」に分けられます。
逮捕と身柄事件
逮捕は、被疑者の身柄を拘束することであり、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。
逮捕されると、被疑者は通常、警察署の留置場に入ることになります。逮捕後の手続きには期限があり、逮捕から勾留決定までのおよそ2~3日間(最長で23日間)は、弁護士を除き、家族であっても面会ができないことが多いです。逮捕された後、この一連の手続きに付される事件を「身柄事件」といいます。
逮捕の要件は、犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由があることと、逮捕の必要性(証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれなど)が認められることです。
書類送検と在宅事件
「書類送検」は法令上の用語ではありませんが、警察が捜査を終えた事件を、被疑者の身柄(逮捕された状態)を伴わずに検察官に送ることを指します。
また、身柄が拘束されていない事件を「在宅事件」といいます。在宅事件では、被疑者は日常通りの生活を送りながら、警察や検察からの呼び出しに応じて取り調べなどの捜査を受けます。
- 逮捕の有無の違い: 在宅事件では、逮捕・勾留による身体拘束を受けません。
- 判断基準の違い: 逮捕されるかどうかは、事件の重さ(重大性)だけではなく、主に証拠隠滅のおそれがあるか、逃亡のおそれがあるかで決まります。そのため、在宅事件であっても、必ずしも事件の重大性が低いと決まっているわけではありません。なお、警察が事件を検察に送致せずに捜査を終結させることを微罪処分といい、これは法律上定められた一定の極めて軽微な事案について、被害回復が行われたり、被害者が処罰を望んでいなかったりする場合に採られます。
書類送検(在宅事件)後の手続きと前科が付く可能性
書類送検された後(在宅事件として捜査が継続した後)、最終的に検察官が起訴するか不起訴とするかを判断します。
前科が付くのはどのような場合か
前科とは、有罪として刑罰(拘禁刑、罰金、拘留、科料など)を科されたことを指します。
逮捕の有無に関わらず、起訴されて有罪判決(正式裁判または略式裁判)を受ければ前科が付きます。
- 正式起訴と有罪判決: 公開の法廷で刑事裁判が行われ、有罪判決が出ると前科が付きます。
- 略式起訴と罰金刑: 検察官が公判手続きを経ずに書面で審理を行うことを請求する手続きで、罰金刑が科されるます。罰金刑であっても前科となります。
前科を回避するためのポイント
前科を回避するためには、検察官による不起訴処分を獲得することが最も重要です。
在宅事件であっても、身柄事件と同様に起訴される可能性は十分にあるため、不起訴を目指すための弁護活動が不可欠です。
示談交渉の重要性
被害者がいる事件の場合、被害者との示談交渉の成立が不起訴処分を得るための大きな鍵となります。示談によって被害者が被疑者の処罰を求めないこととなった場合、検察官は不起訴とすることが多いです。在宅事件では、通常、被害者本人は被疑者本人との接触を拒むため、弁護士を介して示談交渉を行うことが得策です。
弁護活動の重要性
被害者がいない事案でも、警察や検察の取り調べに対して弁護士のアドバイスに基づき適切に対応することで、不起訴の可能性を高めたり、裁判で不利になる供述調書が作成されるのを防いだりすることができます。
在宅事件の場合、逮捕されている身柄事件と異なり捜査の期限がないため、捜査が長期化するデメリットがありますが、事前に弁護士に相談して取り調べの方針を決定しやすいという利点もあります。弁護士に依頼することで、刑事手続きの状況を正しく把握しやすくなるというメリットもあります。

