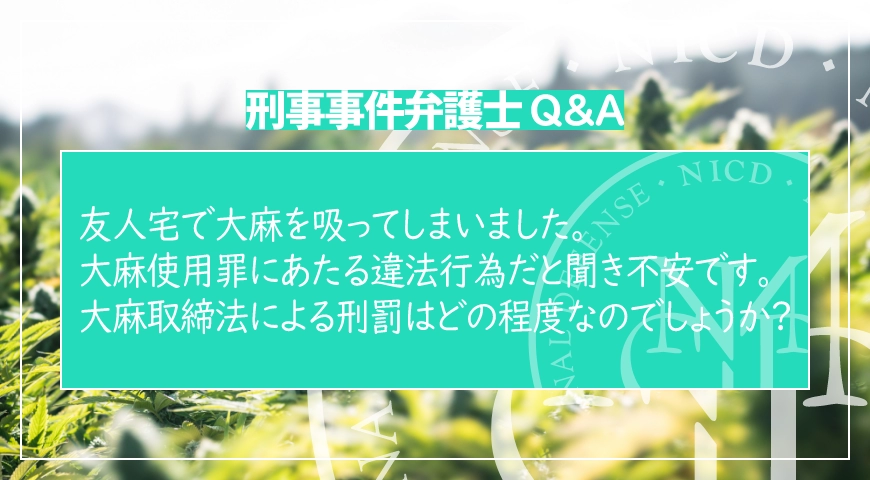
現在の日本の法律において、大麻の使用行為は刑罰(刑事処罰)の対象となっています。
以前の大麻取締法では、大麻の所持、譲り受け、及び譲り渡しなどが規制の対象であり、大麻の「使用」自体には罰則が規定されていませんでした。
しかし、大麻を使用するには、通常、大麻を第三者から譲り受けて所持することが前提となるため、使用自体が罪でなくとも、多くの場合、所持、譲り受け、又は譲り渡しといった行為により処罰の対象となっていました。
その後、規制の見直しの声を受けて、令和5年12月13日に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部の改正が成立し、この改正の趣旨の一つとして「大麻の施用(使用)等の禁止」が盛り込まれました。
大麻取締法、麻薬取締法の改正内容について
| 改正前(旧大麻取締法) | 改正後(改正麻薬取締法) | |
|---|---|---|
| 単純な使用 | – | 7年以下の拘禁刑 |
| 所持・譲受・譲渡 | 5年以下の拘禁刑 | 7年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の所持・譲受・譲渡 | 7年以下の拘禁刑 、情状により200万円以下の罰金 | 1年以上10年以下の拘禁刑、情状により300万円以下の罰金 |
| 輸出入・製造・栽培 | 10年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の輸出入・製造・販売 | 10年以下の拘禁刑、情状により300万円以下の罰金 | 1年以上の有期拘禁刑、情状により500万円以下の罰金 |
大麻をはじめとした薬物犯罪における処分(量刑)の傾向
大麻取締法違反のような薬物犯罪は、再犯率が高い犯罪であると見なされています。そのため、裁判官は再犯のおそれを強く懸念し、再犯のおそれがないことを説得的に主張することが、量刑判断において非常に重要となります。
薬物犯罪の場合、一般的に初犯は執行猶予が付く可能性が高い傾向があります。執行猶予判決を獲得できれば、直ちに刑務所に収監されることはなく、日常生活の中で薬物治療などの更生を図ることが可能になります。一方で、再犯で執行猶予が付く可能性は低いのが実務上の傾向です。
起訴後の活動
起訴されてしまった場合には、刑の減軽や執行猶予判決を目指すことが重要です。執行猶予を獲得するためには、再犯防止プログラムの実践など、更生への具体的な取り組みを示すことが欠かせません。
大麻での逮捕や今後の対応について
大麻などの薬物事件で刑事手続きが進む場合、常習性や罪証隠滅のおそれが問題となり、逮捕・勾留される可能性があります。
逮捕、勾留と保釈
逮捕・勾留は最大23日間に及ぶ可能性があります。起訴後は保釈請求が可能となり、初犯で実刑判決の可能性が乏しい事案では保釈される可能性が高いです。保釈を獲得し、家族や専門機関のサポートを受けながら、社会という現実の環境の中で更生を図ることが重要です。
弁護士によるサポート
薬物犯罪について不安がある場合は、一刻も早く専門的知見を持った経験豊富な弁護士に相談し、適切な対応を知ることが重要です。
弁護士は、ご本人やご家族とともに、薬物に手を出すことになった経緯や動機、環境などを考え、再犯防止のための環境構築や治療に関する相談に乗ります。こうした活動は、裁判で執行猶予判決を得る上でも重要です。

