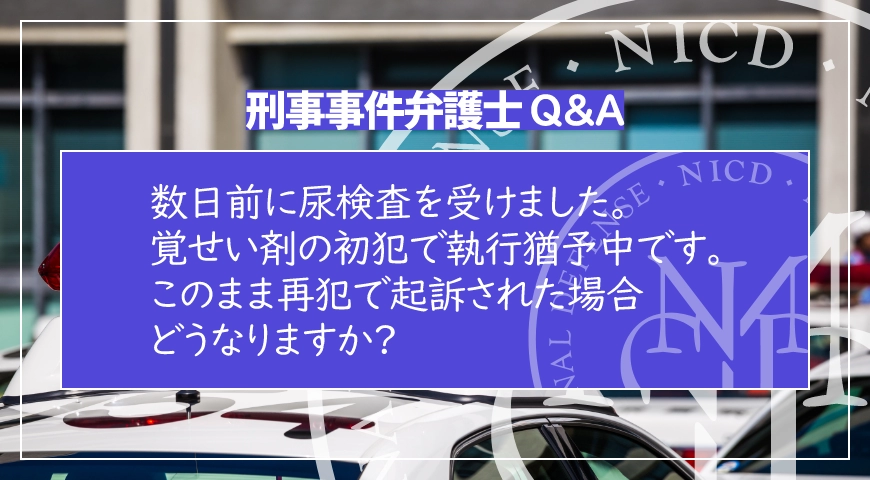
数日前に尿検査を受けられたとのことですが、薬物の正式鑑定には数週間から数ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあります。
そして、鑑定結果が陽性であった場合、警察から連絡があり、警察署への出頭が求められるでしょう。出頭に応じない場合や逃亡のおそれがあると判断された場合、逮捕状を持って警察官が自宅にやってくる可能性が高まります。
多くの場合、逮捕後、警察署の留置場に身柄を拘束され、その後検察庁に送致されます。検察官は、被疑者の身柄を最大で10日間勾留するよう請求し、さらに最大10日間の延長が可能なため、合計で最大23日間の身体拘束が続くことになります。逮捕の時点で既に正式鑑定が終わっている場合、勾留延長なしに10日間で起訴に至る可能性もあります。
また、現在、執行猶予中であるとのことですので、今回の再犯で起訴され、有罪となった場合、前回の執行猶予判決は「必要的取消」となる可能性が極めて高いです。
これは、新たな故意犯で禁錮以上の有罪判決を受けた場合、前回の執行猶予は必ず取り消され、前回の刑罰に加えて今回の刑罰も服役しなければならないことを意味します。
また、執行猶予期間中に前の事件と同種の犯罪(覚せい剤の再犯)を行った場合、特に薬物事件の場合には、再度の執行猶予が認められることは殆どありません。
薬物事件の場合、10年のような極めて長期間が前刑から経過しない限り、同種再犯での執行猶予獲得は非常に困難です。
覚せい剤事件の再犯で起訴された場合の刑罰
覚せい剤の所持、譲り受け、譲り渡し(単純)の法定刑は10年以下の懲役です。
営利目的があったと認定された場合は、1年以上の有期懲役、またはこれに500万円以下の罰金が併科されるという、さらに重い罰則が適用されます。
覚せい剤取締法違反の事件では、起訴される可能性が非常に高く、罰金刑ではなく懲役刑が科されることが一般的です。そのため、公開の法廷での正式な裁判となるでしょう。
覚せい剤事件の保釈と弁護活動とは
起訴前段階では保釈は認められませんが、起訴後は保釈請求が可能となります。
薬物事件において保釈が認められるかどうかは、常習性や罪証隠滅のおそれが重要な判断要素となります。初犯であれば保釈の可能性は高まりますが、再犯の場合、否認事件や長期の実刑判決が予想される場合には保釈を獲得することは容易ではありません。
保釈金は、初犯の単純所持や個人使用の事案であれば概ね150万円程度が相場とされていますが、再犯の事案ではより金額も高くなる傾向にあります。複数の起訴事実がある場合や所持量が多い場合は高額になることもあります。
保釈が認められれば、社会内で薬物依存症の専門治療を受けるなど、更生に向けた環境を整えることができます。
こうした社会内での治療実績は、裁判官が刑の減軽や執行猶予判決を検討する上で重要な要素となります。
弁護士は、警察官の立ち会いなしで逮捕されたご本人と接見し、取調べへの対応について具体的なアドバイスを行い、不利な供述調書が作成されるのを防ぎます。
また、警察の職務質問や所持品検査が適法であったかどうかの調査を行い、違法な捜査が疑われる場合には不起訴を主張する弁護活動も可能です。
ご家族が逮捕された場合、弁護士はご家族からの差し入れの代行や、ご本人の現在の状況を伝えるなど、精神的なサポートも行います。
現在、執行猶予中での再犯の可能性があるという非常に厳しい状況ですので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の弁護方針について慎重に検討することが極めて重要です。

