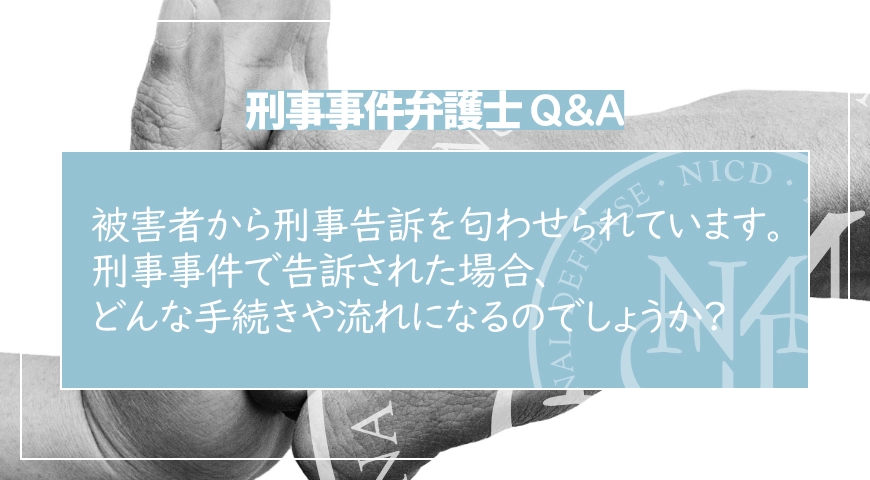
被害者から刑事告訴を示唆されている状況は、刑事事件化のリスクが非常に高まっていることを意味します。
刑事告訴は捜査開始のきっかけの一つであり、告訴が受理されると、警察や検察による本格的な捜査が開始され、逮捕や起訴に至る可能性があります。
刑事告訴とは何か、告訴された後の刑事事件の流れ
刑事告訴は、被害者またはその遺族が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすることです。捜査機関が被害届や告訴を受理すると、捜査が開始されます。刑事告訴された後の刑事事件の一般的な手続きの流れは、以下の通りです。
捜査開始(警察・検察)
捜査機関(警察や検察など)が、犯罪を行ったと疑われる一般市民(被疑者)を捜査します。捜査は、被害届や告訴の受理によって開始されることが一般的ですが、受理の必要性を判断するための前提となる捜査が行われることもあります。
逮捕・勾留(身柄拘束)の可能性
捜査の過程で、被疑者は逮捕・勾留されることがあります。告訴が受理され捜査が開始されると、特に罪証隠滅や逃亡のおそれが大きいと判断される場合、逮捕・勾留される可能性が高まります。逮捕されずに捜査が進む場合(在宅事件)もありますが、逮捕は突然、外出前の早朝に容疑者宅を訪れるなどの方法で執行されることが多く、事前に予想することは困難です。
検察官への送致(書類送検)と取調べ
警察による捜査がある程度進むと、事件は検察官に送致されます。検察官は、捜査内容を検討し、被疑者を再度呼んで事情聴取(取調べ)を行うことがあります。
起訴・不起訴の判断
最終的に、捜査機関が収集した証拠と被疑者の供述をもとに、検察官が起訴するか不起訴とするかを判断します。検察官が起訴すると判断した場合、被疑者は「被告人」となります。
裁判と判決
起訴された場合、裁判所において事件の審理が行われ、有罪か無罪か、有罪となる場合は具体的な量刑が決定されます。有罪の場合は刑罰が、無罪の場合は「無罪」が言い渡されます。
告訴された場合に逮捕される可能性
告訴された後、捜査が進む中で逮捕される可能性は十分にあります。逮捕の要件は、犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由と、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれ、そして逮捕の必要性(逮捕による不利益が罪証隠滅や逃亡のおそれに比して過大でないこと)(主に罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれ)が認められることです。
このような要件がありますが、捜査機関が裁判所に逮捕状の発布を請求すると殆どが認められているのが実情です。
不同意わいせつや不同意性交等などの重い性犯罪や高額の詐欺・横領事件など、一定の重大性のある事件については、告訴が受理され捜査が始まると、逮捕の可能性は高まってしまいます。
告訴前に被害者側と話し合うことが可能であれば、弁護人を通じて示談交渉を行うことが有用です。被害者(告訴人)が加害者(被疑者)に対し処罰感情を抱いていることが明確になるため、捜査機関は逮捕の必要性があると判断しやすくなります。特に、逃亡や証拠隠滅のおそれが大きいと判断された場合、逮捕・勾留される可能性が高まります。
不起訴処分を得て前科を回避するための対応
前科(有罪判決による刑罰)を回避するためには、検察官による不起訴処分の獲得が最も重要です。不起訴処分であれば、前科はつきませんし、逮捕・勾留されている場合には釈放されます。不起訴処分を目指すためには、事態が深刻化する前に一刻も早く弁護士に相談することが非常に重要です。
被害者との示談交渉の重要性
被害者がいる刑事事件では、被害者との示談が、検察官による処分(起訴・不起訴)との関係で特に重要になってきます。
不起訴の可能性の向上
検察官は、起訴・不起訴の判断をする際に被害者の処罰感情を重視します。被害者が被疑者の真摯な謝罪を受け入れて許してくれるような場合(示談が成立した場合)、国家権力が別途刑罰を科す必要はないとも考えられ、不起訴になる可能性が高まります。特に、被害者の個人的法益に対する意向を重視する犯罪類型(窃盗、横領などの財産犯や、暴行や傷害、痴漢、盗撮、不同意わいせつなどの性犯罪など)では、示談の成立は重要です。
示談交渉
被害者は、加害者本人やその家族との接触を拒むことが通常であり、警察や検察官も被害者の連絡先を被疑者本人には原則として伝えません。そのため、弁護士を介して示談交渉を行うことが事実上必須となります。
示談のタイミング
示談は、被害者の損害を少しでも早く回復するため、できるだけ早期に、できれば告訴される前に行うことが肝要です。告訴された後であっても、示談は可能であり、起訴前であれば起訴・不起訴の判断に大きく影響し、起訴後であれば裁判所によるその成立は量刑の判断において有利に考慮されます。
謝罪文の作成
示談交渉の際には、被疑者の誠意ある謝罪の気持ちを伝えるため、直筆の謝罪文を作成し、弁護士を通じて被害者に渡すことが一般的です。謝罪文には、被害者の苦痛や日常生活への影響を想像し、配慮した記載が必要です。
弁護士によるその他の活動
刑事事件に精通した弁護士は、告訴された事案において、逮捕の回避や不起訴処分を目指すために多岐にわたる活動を行います。
逮捕回避活動
逮捕の可能性が高い場合、弁護士は依頼人と一緒に警察署に出頭して自首し、逮捕回避を求める意見書を持参するなどして在宅捜査となるよう説得します。
取調べへの適切な対応
弁護士は、取調べでの受け答えについて詳細にアドバイスを提供し、不利な内容の供述調書に署名押印してしまわないよう支援します。取調べ対応の方針は、法律の知識のない被疑者本人が考えるのではなく、起訴前の段階から弁護人と相談の上で慎重に決定することが重要です。
否認事件における対応
もし身に覚えがなく告訴された(冤罪の)場合でも、弁護士に依頼して無実を主張し、嫌疑不十分による不起訴・釈放を勝ち取るための活動を行う必要があります。否認事件の場合、虚偽の自白を強いられないために、徹底的な取調べ対応が重要になります。事案によっては、否認事件であっても、不起訴処分の獲得を狙い、相手方に示談の申し入れを行うこともあります。

