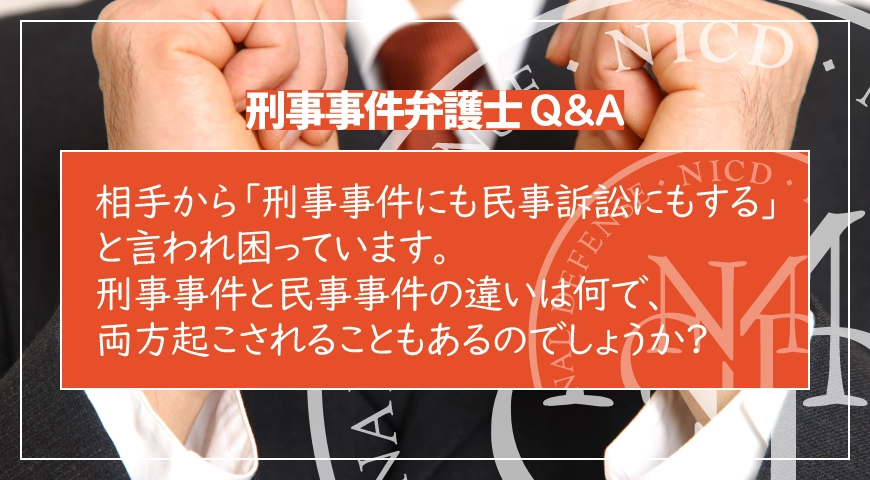
相手から「刑事事件にも民事訴訟にもする」と告げられた場合、これは、行為に対して刑事上の責任(刑罰)と民事上の責任(損害賠償)の両方を追及するという意図を示しています。
一つの行為に対して、刑事と民事の二つの異なる法的な責任が生じる可能性は十分にあります。
刑事事件と民事事件の目的と役割の明確な違い
刑事事件と民事事件は、その目的、訴えを起こす主体、そして結果が大きく異なります。
刑事事件の目的と責任(刑罰)
刑事事件は、犯罪行為に対して国家が刑罰を科すことを目的としています。日本においては、検察官のみが公訴(刑事裁判の提起)を行う権利(公訴権)を持っています(国家訴追主義または起訴独占主義)。
刑事事件で有罪となった場合、拘禁刑、罰金、拘留、科料などの刑罰が科されます。
民事事件の目的と責任(損害賠償)
民事事件(民事訴訟)は、私人(個人や企業など)間の紛争を解決することを目的とします。
犯罪行為によって被害が生じた場合、その行為は民法上の不法行為(民法709条)損害賠償責任を負います。民事事件の主な目的は、被害者に生じた損害(被害の弁償や精神的苦痛に対する慰謝料など)を回復することです。民事訴訟は、被害者またはその遺族など、損害賠償請求権を持つ当事者が、加害者に対して訴訟を提起します。
刑事事件と民事訴訟が両方起こされる可能性について
一つの行為が犯罪に該当する場合、通常、それは刑事責任だけでなく民事責任も発生させます。そのため、両方の訴訟を起こされる可能性があります。
例えば、横領行為は、刑事罰(業務上横領罪など)の対象となるだけでなく、民法上の不法行為(民法709条)にも該当するため、会社側から刑事罰を問われるほかに、不法行為に基づく損害賠償請求という民事上の責任追及を受けることがあります。
示談交渉による両面の解決
刑事事件の手続きの中で、加害者と被害者の間で示談が成立することにより、刑事・民事の両方の問題が解決されることになるのが一般的です。
- 示談の内容: 刑事事件における示談では、被害の弁償や精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)、その他の損害賠償として示談金を支払い、解決に向かいます。
- 民事責任の清算: 示談が成立した場合、通常、示談書には清算条項というものが含まれます。この清算条項は、「示談書に定めるもののほかに、甲と乙との間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった文言で記載され、示談成立後に追加的な金銭の請求など、主に民事的な紛争の蒸し返しを防止するための条項です。これにより、刑事手続きの示談を通じて、民事上の責任追及も同時に解決されることが大半です。
示談のインセンティブ
加害者にとって、刑事事件での示談は、前科回避や量刑の軽減につながる重要な活動です。このため、加害者本人に資力がなくても、家族が示談金を支出したり、借入れをするなど、示談金捻出のためのインセンティブが働くことがあります。
示談が成立しなかった場合、被害者側の加害者に対する損害賠償請求権は残るため、被害者またはその遺族は加害者に対して民事上の損害賠償請求の訴訟を提起することが可能になります。もっとも、加害者が目ぼしい財産を有しておらず無資力の場合、民事訴訟で勝訴したとしても金銭を回収することは実質的には困難です。そこで、被害者側からしても、刑事事件の段階における示談で示談金の支払いを受けることがメリットとなる場合があります。
弁護士に相談する重要性
刑事・民事の両面での問題に直面している場合、弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉を通じて、刑事・民事両面の解決を図ることができます。示談交渉の経験豊富な弁護士は、被害者の心情に配慮しつつ、真摯な対応で交渉を進めることが可能です。

